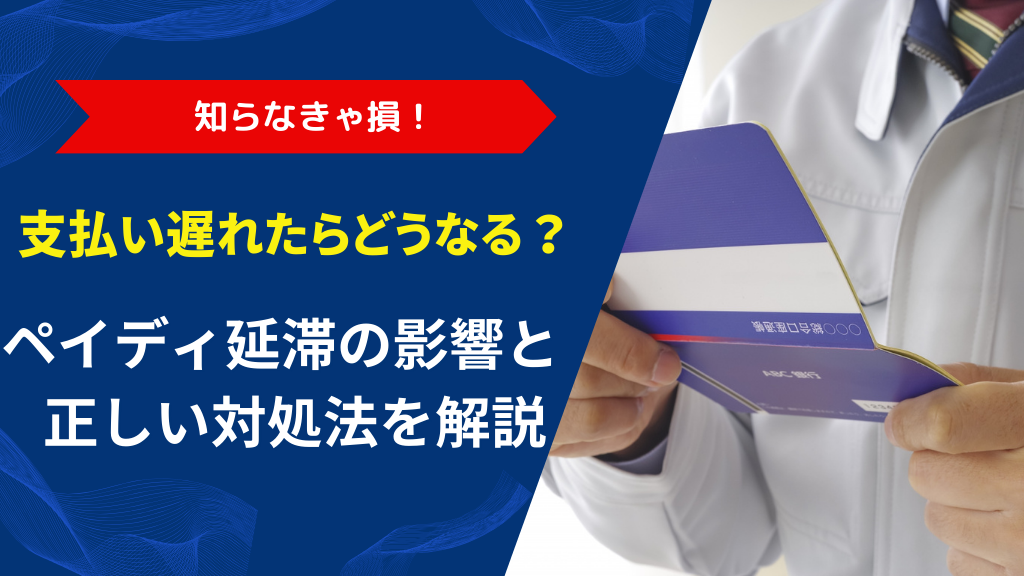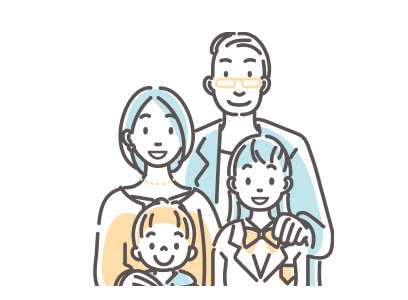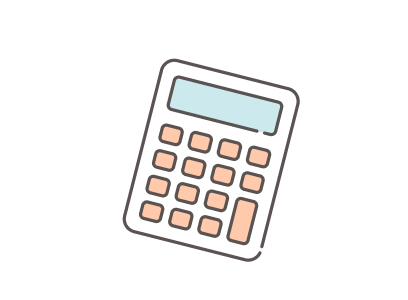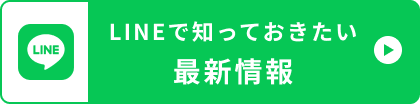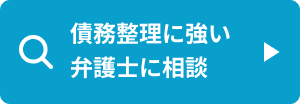過払い金の条件とは?|3つの必須条件と自分でできるチェック方法を解説
過払い金 請求
2025.09.29 ー 2025.10.20 更新
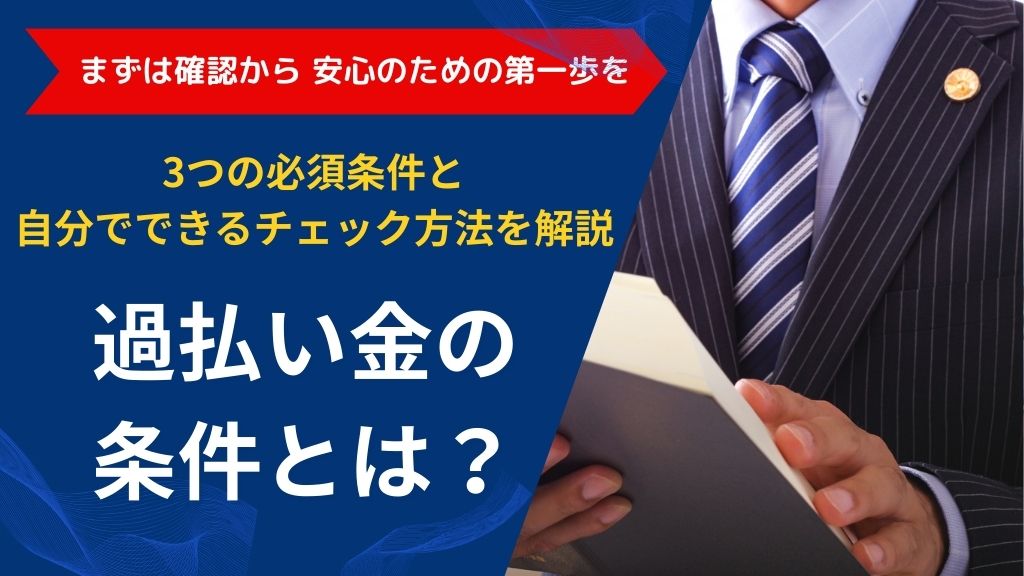
「借金を払いすぎたお金が戻ってくる」という話、気になっていませんか?もしかしたら、あなたも過払い金を受け取れる条件を満たしているかもしれません。
この記事では、過払い金が何なのか、そしてなぜ返還されるのかといった基本的なことに加え、過払い金請求ができる具体的な条件と自分でできるチェック方法を分かりやすく解説していきます。
こんな人におすすめの記事です。
- 毎月の返済に追われて、どうしたらいいか悩んでいる
- 払い過ぎた利息(過払い金)があるか知りたい
- 自分で請求できるか、専門家に頼むべきか迷っている
- 相談したいけど費用や手続きが不安で一歩踏み出せない
記事をナナメ読み
- 過払い金が発生する条件と、自分で確認する方法がわかります
- 時効や注意点を知り、損をしないためのポイントがつかめます
- 請求の流れや専門家に依頼するメリット・デメリットがわかります
- 無料相談を活用して、安心して返済問題を解決する第一歩を踏み出せる
過払い金とは何か?わかりやすく解説
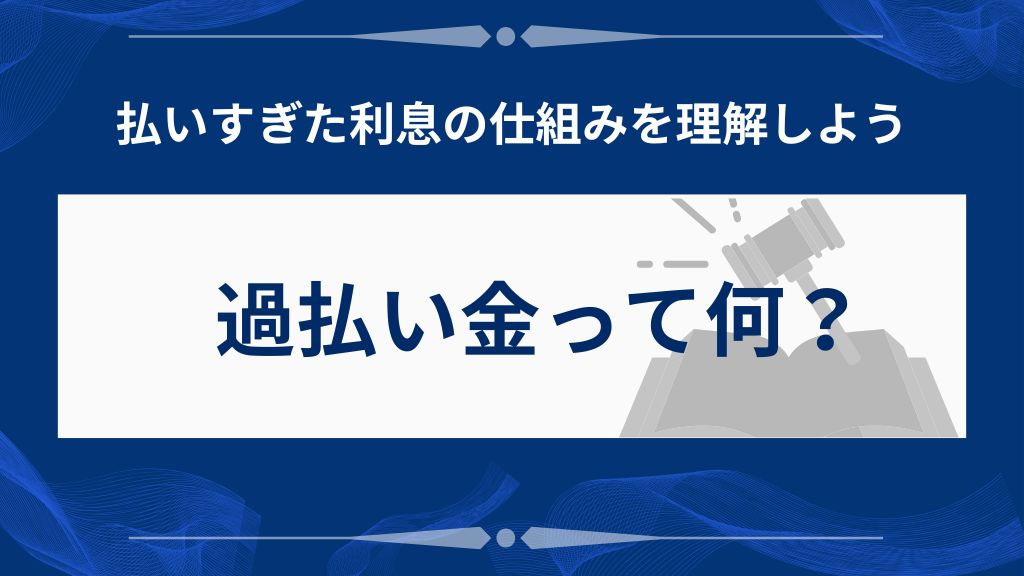
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社に、本来払う必要のなかった利息として多く支払ってしまったお金のことです。法律で定められた上限金利を超えていた利息分がこれに当たります。
ここでは、なぜこのような過払い金が発生するに至ったのか、その具体的な仕組みや原因、そしてなぜそれが法的に返還されることになったのかを、詳しく見ていきましょう。
過払い金の仕組みと発生理由
過払い金が発生する仕組みを理解するには、日本の金利に関する法律について知る必要があります。日本では「利息制限法」という法律により、借り入れ金額に応じた上限金利が定められています。
具体的な上限金利は以下の通りです。
【利息制限法の上限金利(年率)】
| 借入金額 | 上限金利 |
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
しかし、以前は「出資法」という別の法律で年29.2%まで認められており、多くの業者がこの高い金利で貸し付けを行っていました。この利息制限法の上限金利と出資法の上限金利との間にあった金利帯が「グレーゾーン金利」と呼ばれ、過払い金発生の主な原因となりました。
例えば、利息制限法で年18%が上限とされる借り入れに対し、年25%で契約していた場合、この7%分の差額が長期間の返済を通じて積み重なり、過払い金として返還請求できる金額になっていくのです。
この状況は、2006年の最高裁判決(通称「シティズ判決」)によって大きく変わり、グレーゾーン金利での取引が事実上無効と判断され、過払い金返還請求の道がひらけました。
2010年6月に法改正が実施され、グレーゾーン金利は完全に撤廃されています。
過払い金が返ってくる理由
過払い金が返還される根拠は、民法の「不当利得返還請求権」にあります。これは、法律上支払う義務がなかったお金を支払ってしまった場合、「そのお金を返してください」と主張できる権利です。
前述の2006年の最高裁判決が大きな転換点となりました。この判決で、グレーゾーン金利での取引が事実上無効と判断され、過払い金返還請求が本格的にスタートしたのです。裁判所は「利息制限法の上限を超えた部分は無効で、借り入れをしていた人に返還されるべきだ」と明確に示しました。
返還される過払い金には、通常5%の利息がプラスされます。これは、本来戻ってくるはずのお金を業者が持っていた期間に対する利息として認められているからです。
過払い金が発生する3つの必須条件
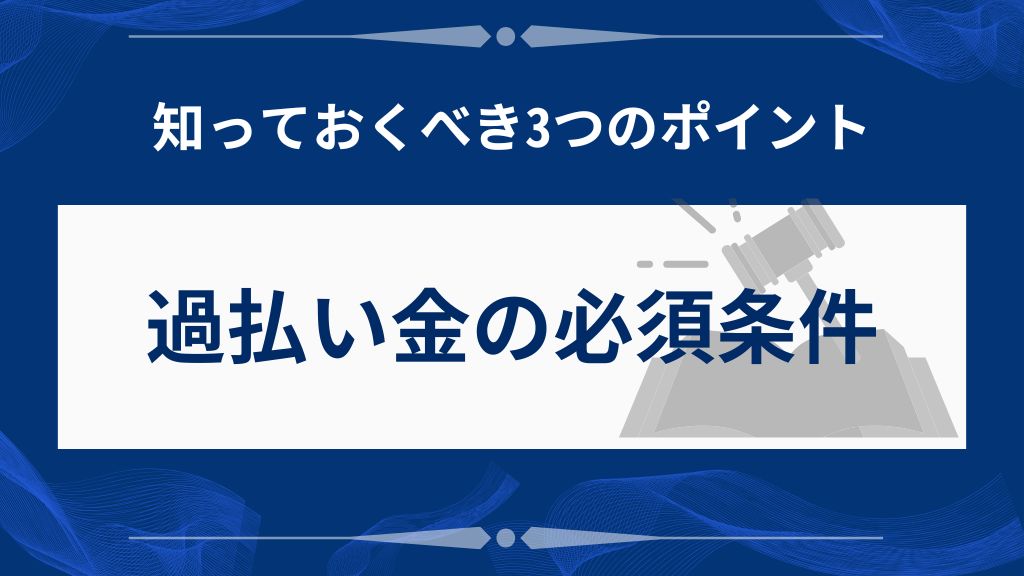
過払い金は、誰もが発生するわけではありません。法律で定められた条件を満たした場合にだけ、返還を求められる権利です。
ここでは、その3つの必須条件について具体的に見ていきましょう。
条件1:利息制限法の上限を超える高金利で借りていた場合
過払い金が発生する上で最も大切な条件は、過去に利息制限法で定められた上限を超える高金利で借り入れをしていたかどうかです。
具体的には、2010年6月以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用し、借入額に応じた利息制限法の上限金利(例:10万円以上100万円未満なら年利18%)を超える金利で返済をしていた場合に、過払い金が発生している可能性があります。
2010年以降に新たに借り入れを始めた方は、すでに法改正後の適正な金利が適用されているため、基本的に過払い金は発生しません。また、銀行カードローンも、もともと利息制限法内の金利設定がほとんどのため、過払い金が発生するケースはほぼないでしょう。
条件2:すでに完済している、または大幅に残高を減らしている
過払い金請求を考えるなら、対象となる借り入れをすでに完済しているか、もしくは残高をかなり減らしている状態であれば、より有利に進められます。
完済済みであれば、過払い金がそのまま現金として手元に戻ってくる可能性があります。しかし、まだ借り入れ残高が多く残っている状況では、過払い金と現在の債務が相殺される形になることがほとんどです。そのため、手元に戻る金額が限られたり、場合によってはゼロになるケースもあります。
また、現在返済中の借り入れについて過払い金請求をする場合、その金融機関とは今後取引ができなくなる可能性が高いことも、知っておくべき点です。完済後であれば、こうした制約を気にすることなく、請求手続きを進めやすくなります。
条件3:最後の取引から10年以内(時効完成前)である
過払い金返還請求の権利には、民法で定められた「時効」が適用されます。最後の取引(完済または最終の借り入れ・返済)から10年が経過すると、時効によって請求できる権利が消滅してしまう可能性があるため、注意が必要です。
この「最後の取引」の解釈が非常に重要なポイントです。一度完済した後に、再び同じ業者から借り入れをした場合、法律上は「継続的な取引関係」と見なされることがよくあります。その場合、時効のカウントがスタートする日(起算点)は、最後に完済した日になるのです。
ただし、一度完済してからある程度の期間が空いて再契約した場合は、別々の取引と見なされ、最初の完済から10年で時効が成立する可能性もあります。この判断は取引の状況によって変わるため、専門家による詳細な調査が欠かせません。
時効が迫っていたり、取引関係が複雑だったりする場合は、早めに弁護士や司法書士に相談するのが得策です。
過払い金請求の条件に当てはまるかをチェックしよう
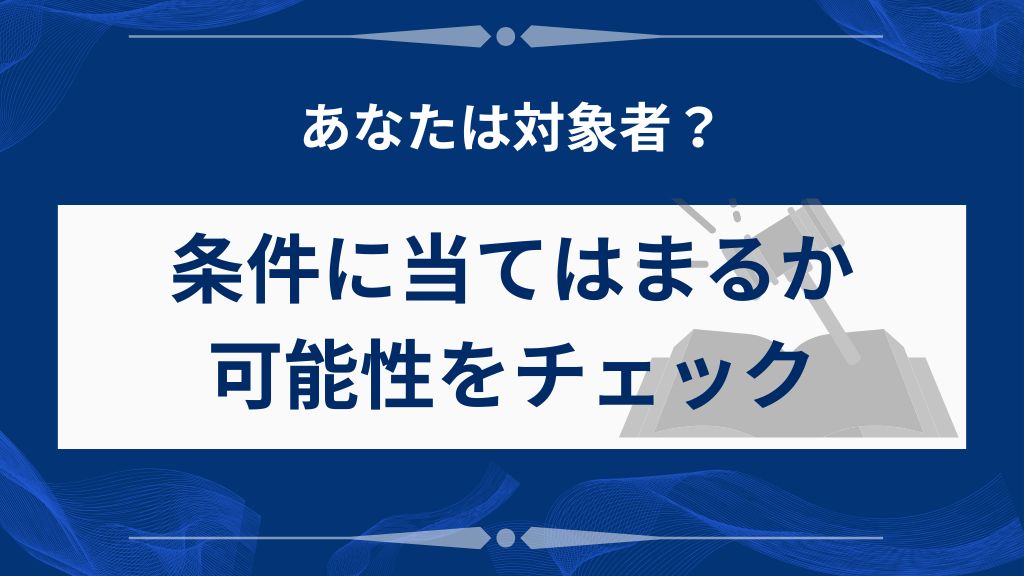
ご自身に過払い金が発生しているか、気になっている方も多いでしょう。
ここでは、過払い金請求の対象となりやすい方の具体的な特徴と、残念ながら請求が難しいケースを詳しく解説します。さらに、過払い金発生の可能性をチェックする方法もご紹介しますので、ぜひご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。
過払い金請求の対象となりやすい人の特徴
過払い金請求の対象になる可能性が高い方の特徴は、主に以下の通りです。
2010年6月以前から借り入れを始めた方
この時期より前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していたなら、グレーゾーン金利で契約していた可能性が高いです。
長期間、返済を続けていた方
特に5年以上、同じ業者との間で借り入れと返済を繰り返していた場合、過払い金が累積している可能性が高まります。
月々きちんと返済していたのに元本がなかなか減らなかった経験がある方は要注意です。
複数の消費者金融から借り入れをしていた方
各社で個別に過払い金が発生している可能性があり、合計すると大きな金額になることもあります。
完済から10年以内の方
過払い金請求には時効があり、完済から10年を過ぎると、原則として請求できません。完済時期を確認してみることをおすすめします。
過払い金請求が難しい人によくあるパターン
残念ながら、過払い金請求が難しい方もいらっしゃいます。よくあるパターンは以下の通りです。
2010年6月以降に初めて借り入れをした方
この時期以降、ほとんどの業者が利息制限法内の利率に変更しているため、基本的に過払い金は発生しません。
銀行のカードローンのみを利用していた方
銀行は元々利息制限法内の利率で貸し付けを行っていたため、過払い金は基本的に発生しません。ただし、銀行が保証会社として消費者金融を利用していた場合は例外もあります。
すでに債務整理を行い、過払い金も処理済みの方
任意整理や個人再生の際に、弁護士や司法書士が過払い金の調査も一緒に行っているケースが多いため、重複請求となってしまいます。
業者が倒産・廃業している場合
特に中小の消費者金融の中には、過払い金請求の増加で経営が破綻し、事業を停止した会社もあります。この場合、実際に回収するのは非常に困難である可能性が高いです。
まずは自分で!過払い金の可能性をチェックする方法
ご自身で過払い金の可能性をチェックするための方法をいくつかご紹介します。
古い契約書類や明細書を確認する
引き出しや書類整理ボックスに眠っている契約書、利用明細、返済予定表などを探してみてください。特に、金利が年率18%を超える記載があれば、過払い金があるかもしれません。
記憶による借り入れ履歴を整理する
いつ頃から借り入れを始めたのか、どの業者を利用していたのか、そしていつ完済したのかを、時系列で書き出してみましょう。おおよその時期でも十分な手掛かりになります。
信用情報機関への開示請求をする
CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターの3つの機関で、過去の借り入れ履歴を確認できます。手数料はかかりますが、契約内容や完済日を正確に把握できるため有効です。
これらの方法で「もしかして過払い金があるかも」と感じた場合は、一人で判断せず専門家に相談することをおすすめします。

【過払い金請求】返還手続きのメリット・デメリットも徹底解説!
過払い金を請求したいけど自分が請求できるのかもわからず、手続きを進められない人も...
過払い金の有無を確認する方法
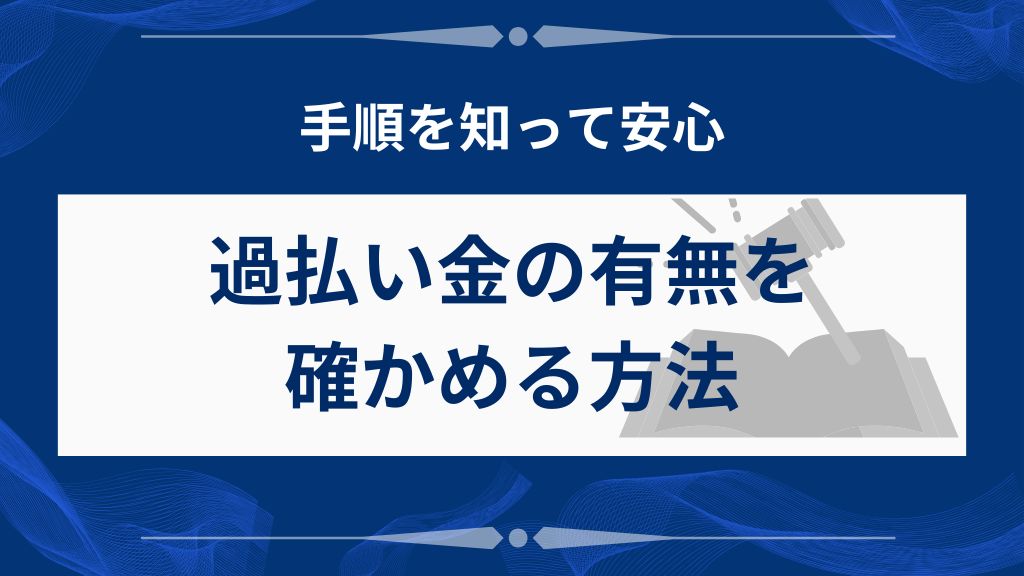
過払い金があるか正確に確認するには、段階的に進めることが大切です。
ここでは、まず貸金業者から取引履歴を取り寄せ、その情報に基づいて過払い金の引き直し計算を行い、最終的に過払い金の有無と返還見込み額を判定する具体的な方法を解説します。
この確認作業は専門的な知識も必要になるため、最終的な判断や手続きについては専門家のサポートを受けることをおすすめします。
取引履歴を取り寄せて借入条件を確認する
過払い金を確認する上で最も重要なのが、貸金業者から「取引履歴」を取り寄せることです。取引履歴とは、これまでの借り入れや返済の詳しい記録が記された書類で、過払い金の計算には欠かせない資料となります。
取引履歴は、現在利用中の業者だけでなく、過去に完済した業者に対しても請求できます。請求方法は業者によって異なりますが、電話での依頼や専用の申請書を使った郵送が一般的です。取得までには2週間から1ヶ月程度かかることもあります。
取引履歴が届いたら、記載されている内容を詳しく確認していきましょう。特に注意して確認したいのはは、借り入れ時期、借り入れ金額、適用金利、返済金額、返済日などです。2010年以前の取引で年18%を超える金利が適用されているなら、過払い金が発生している可能性が高いと言えます。
過払い金の計算方法(利息の引き直し計算)
過払い金の計算は、「利息の引き直し計算」という方法で行われます。これは、過去に法定金利を超えて支払ってしまった利息を、正しい金利でもう一度計算し直すことで、過払い金がいくらになるのかを割り出す方法です。まず法定金利を確認しましょう。利息制限法では、元本10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%が上限と決められています。
取引履歴にある金利がこの上限を超えている期間について、正しい金利で再計算を進めるのです。この計算は非常に複雑になることが多く、借り入れと返済を繰り返している場合は、さらに複雑さが増します。表計算ソフトや専用の計算ツールを使うのが一般的です。
さらに、過払い金には利息も付くのです。過払い金が発生した時点から年5%の利息が加算されますから、長期間にわたって過払い状態が続いていた場合、元の過払い金額よりもかなり大きな金額になる可能性があります。
過払い金の有無と返還見込み額を判定する
引き直し計算が終わったら、過払い金があるかどうか、そしてどのくらいの金額が返還されるのかを判定しましょう。計算結果がプラスなら過払い金が発生していることになりますし、マイナスならまだ借金が残っている状態だと分かります。
過払い金が確認できたとしても、実際に戻ってくる金額は計算上の金額と異なるケースもあります。貸金業者の経営状況や交渉の進め方によって、満額回収できることもあれば、提示された割合で和解になることもあるからです。専門家に相談することで、より確実で有利な条件での回収が期待できます。
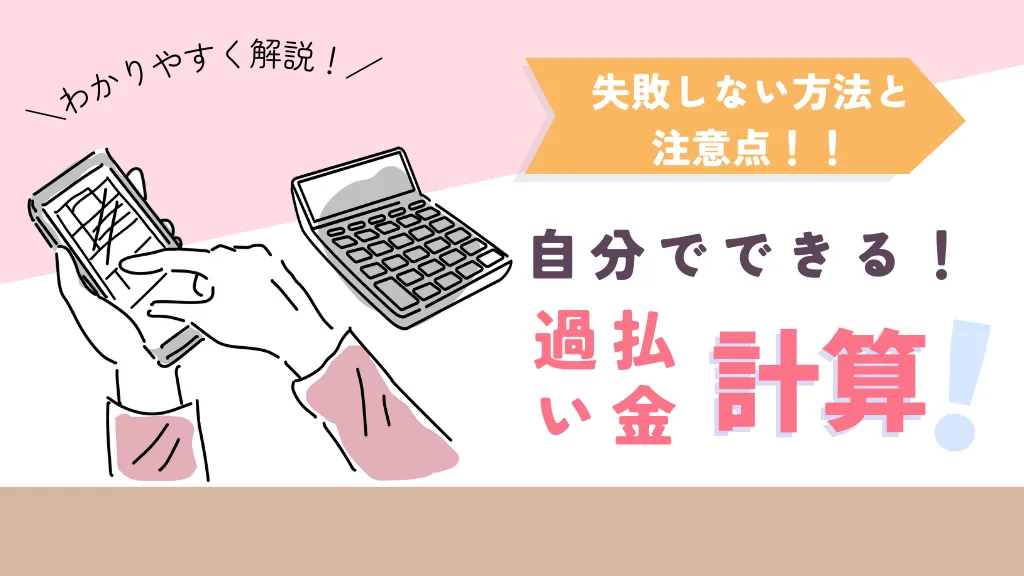
過払い金計算を自分でするには?10秒でシミュレーションの方法がわかる簡単解説
過払い金を計算して、もしかしたら戻ってくるお金があるかもしれない、そんな期待を持...
過払い金請求の時効について知っておくべきこと
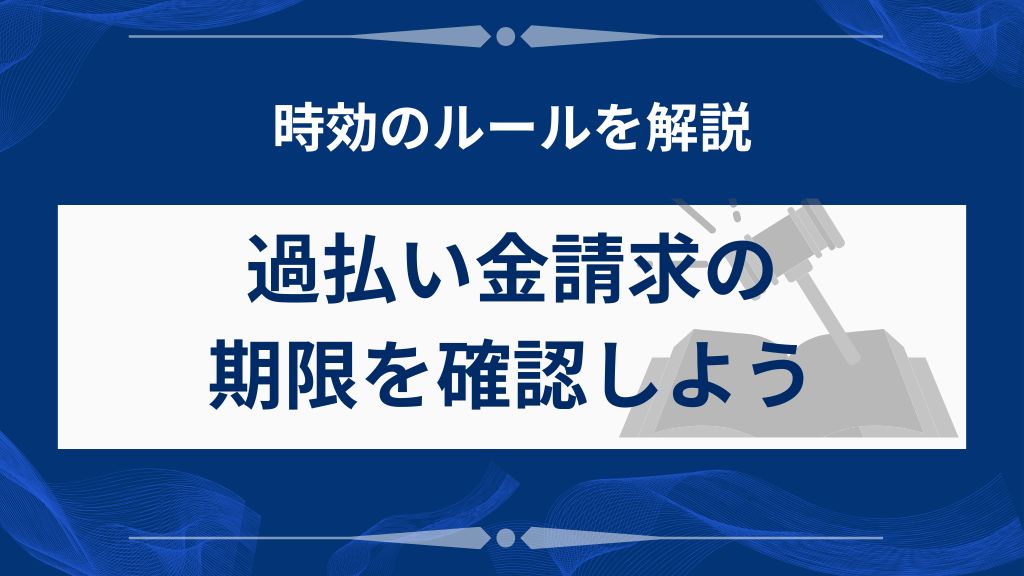
過払い金請求には、「時効」の期間が定められており、期限を過ぎると請求権が失われてしまいます。ここでは、「完済から10年」という基本的なルールに加え、「知ってから5年」というもう一つの時効、さらには時効を過ぎていても請求できる可能性のある特別なケースについて、詳しく解説します。
完済から10年で権利がなくなる基本ルール
過払い金請求の最も基本的な時効ルールは「完済から10年」です。これは民法で定められた「債権の消滅時効」によるもので、借金を完全に返済し終えた日から10年が経つと、過払い金の返還請求権が消滅してしまいます。
例えば、2016年3月に借金を完済した場合、2026年3月までが過払い金請求の期限です。この期限を過ぎると、法律上は過払い金を請求する権利が消滅します。
ただし、「完済」の定義については注意が必要です。最後の借金を返し終えた日が完済日となりますが、クレジットカードの場合、ショッピング枠とキャッシング枠で完済日が異なることがあります。過払い金の対象となるのはキャッシング枠の部分だけですから、キャッシング枠を完済した日から10年が、時効のカウントがスタートする日(起算点)になります。
また、同じ業者と複数回取引がある場合の完済日の考え方も、重要なポイントです。最初の完済から10年ではなく、最後の完済から10年が時効期間となることが一般的だと言えます。
知ってから5年でも時効になるケース
2020年の民法改正で、過払い金請求には新たな時効ルールが加わりました。それが「知ってから5年」という規定です。「過払い金があることを知った時から5年」で時効になるというもので、完済から10年よりも短い期間で権利が消滅する可能性が出てきました。
この「知った時」の判断は、非常にデリケートで複雑です。いつ過払い金の存在を認識したかによって、時効のカウントがスタートする日(起算点)が変わってくる場合があります。
この新しい時効ルールが適用されるのは、2020年4月1日以降に過払い金の存在を知った場合です。それ以前から知っていた方には、従来の「完済から10年」のルールが適用されます。多くの場合、「完済から10年」と「知ってから5年」のうち、より早く到来する方の時効が適用される可能性が高いとされています。
そのため、過払い金について少しでも心当たりがある方は、できるだけ早く専門家に相談することが非常に重要です。
時効を過ぎていても請求できる特別なケース(繰り返し借入・業者の違法行為など)
一般的な時効ルールを過ぎていたとしても、特別な事情があれば過払い金請求ができるケースがあります。
最も多いのが、「一連の取引」として認められるケースです。同じ業者と長期間にわたって借り入れと返済を繰り返していた場合、個々の取引ではなく、全体を一つの継続的な取引として判断されることがあります。最初の完済から10年が過ぎていても、最終完済から10年以内であれば、全期間の過払い金を請求できる可能性があるのです。
「一連の取引」と認められるには、以下3つの条件が重要な判断基準になります
- 完済から再借り入れまでの期間が短いこと
- 同一の基本契約に基づく取引であること
- 継続的な取引関係があったこと
などが重要な判断基準になります。
また、貸金業者側に違法行為や不当な行為があった場合も、時効の起算点が変更されたり、進行が猶予される・更新される場合があります。例えば、
- 利息制限法違反を隠していた、
- 取引履歴の開示を不当に拒んでいた
などの行為があった場合です。
時効が迫っている時の緊急対処法
時効が迫っている、あるいはすでに過ぎているかもしれない……そんな場合でも、諦める前にできる対処法があります。迅速な行動が過払い金回収の可能性を大きく左右します。
まず最も重要なのが「時効の完成猶予・更新」です。過払い金返還請求を正式に行うことで、時効の進行を一時的に止める、あるいはリセットする効果が期待できます。具体的には、内容証明郵便による請求書の送付(時効の完成猶予)、調停の申し立て、訴訟の提起(時効の更新)といった方法があります。特に内容証明郵便を送付した場合、そこから6ヶ月間は時効の完成が猶予され、その間に訴訟などを起こせば時効期間が新たにリセットされます。ただし、時効の完成猶予や更新の手続きは法的な要件を満たす必要があります。専門知識がない状態で進めると、かえって権利を失うリスクもあります。
次に大切なのが「取引履歴の速やかな取得」です。過払い金があるかどうか、そしてその金額を正確に把握するには、貸金業者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算を行う必要があります。
緊急性が高いと感じたら、弁護士や司法書士などの専門家にすぐに相談することをおすすめします。専門家であれば、時効の判断、完成猶予・更新手続きの実行、業者との交渉まで迅速に対応できます。時効は一度完成してしまうと取り返しがつきません。ですから、少しでも心当たりがある方は、早めに専門家に状況を確認してもらうことが大切です。
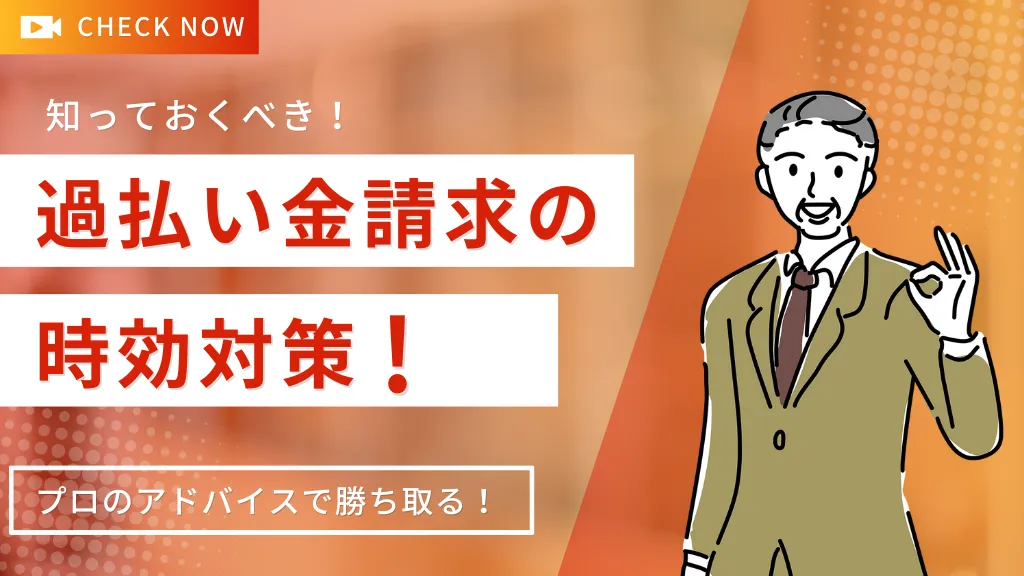
過払い金請求の時効は5年?民法改正後に10年以上過ぎた時の方法を解説
過払い金請求が可能かどうかを判断するためには、時効に関する知識が不可欠です。この...
過払い金請求の手続きの流れ
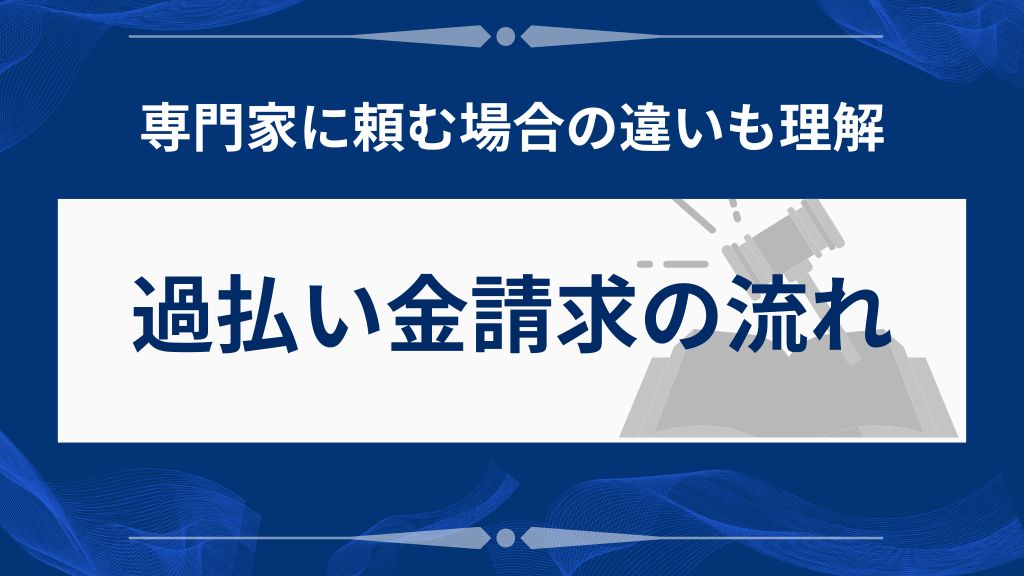
過払い金請求の手続きは、ご自身で行う場合と専門家に依頼する場合とで流れが異なります。ここでは、それぞれの特徴や具体的な流れを比較しながら見ていきましょう。どちらを選ぶかによって、必要な時間や労力、そして最終的に回収できる金額も変わってくる可能性があります。
自分で手続きする場合
ご自身で過払い金請求を進める場合、以下の手順で行います。
- 取引履歴の開示請求:貸金業者に過去の借り入れと返済の記録を請求します。
- 過払い金の計算:利息制限法に基づいた正しい金利で再計算し、過払い金を算出します。
- 過払い金返還請求書の送付:内容証明郵便を利用し、業者へ請求書を送付します。
- 業者との交渉:業者側は減額案を提示してくることが多いため、交渉が必要です。
- 訴訟の提起(交渉がまとまらない場合):裁判所に過払い金返還請求訴訟を起こします。
専門家に依頼した場合
弁護士や司法書士に依頼すると、以下の手順で手続きが進みます。
- 受任通知の送付:専門家が業者に受任通知を送付。業者からの連絡は専門家を通して行われます。
- 取引履歴の開示請求:専門家が業者から取引履歴を取り寄せます。
- 過払い金の計算:専門家が過払い金の計算を正確に行います。
- 業者との交渉:専門家が法律のプロとして業者と交渉し、高い回収率を目指します。
- 訴訟手続き(交渉がまとまらない場合):専門家が訴訟手続きを代行し、依頼者の負担を軽減します。
- 過払い金の回収と支払い:回収された過払い金から専門家の報酬が差し引かれ、依頼者に支払われます。
「自分で手続きする場合」と「専門家に依頼した場合」の違い
自分で過払い金請求を行う方法と、専門家に依頼する方法、それぞれの基本的な流れはご理解いただけたでしょうか。どちらを選ぶべきか、迷う方も多いかもしれません。そこで、両者を分かりやすく比較してみましょう。
【過払い金請求:自分で手続きする場合・専門家に依頼する場合】
| 項目 | 自分で手続きする場合 | 専門家に依頼する場合 |
| 手間・時間 | 全て自分で対応するため、多大な時間と労力を要する。 | 専門家が全て代行するため、自身の負担は最小限に抑えられる。 |
| 回収額の期待値 | 交渉経験や法律知識が不足している場合、回収額が減額される可能性が高まる。 | 専門家が交渉を行うため、高い回収率が期待できる。 |
| 精神的負担 | 業者との直接交渉や複雑な手続きにより、精神的なストレスを感じやすくなる。 | 業者とのやり取りは専門家が担当するため、精神的な負担は少なくなる。 |
| 費用 | 基本的に書類取得費などの実費のみが発生する。ただし、時間や労力も考慮に入れる必要がある。 | 多くの場合、成功報酬制が採用されており、回収額に応じて費用が発生する。 |
このように、自分で手続きする場合は費用を抑えられる反面、時間や労力、専門知識が求められます。一方、専門家に依頼すれば費用はかかりますが、手間なく確実に、より多くの過払い金回収が期待できます。ご自身の状況や優先順位に合わせて、最適な方法を選ぶことが大切です。もし少しでも不安を感じるようであれば、まずは専門家への無料相談を検討してみるのが良いでしょう。

過払い金請求を自分で行う方法|手順・メリット・デメリットをわかりやすく解説
「返済しても元金が全然減らない……もしかして払いすぎてるかも?」「この状況を何と...
過払い金請求を成功に導くための専門家の活用法
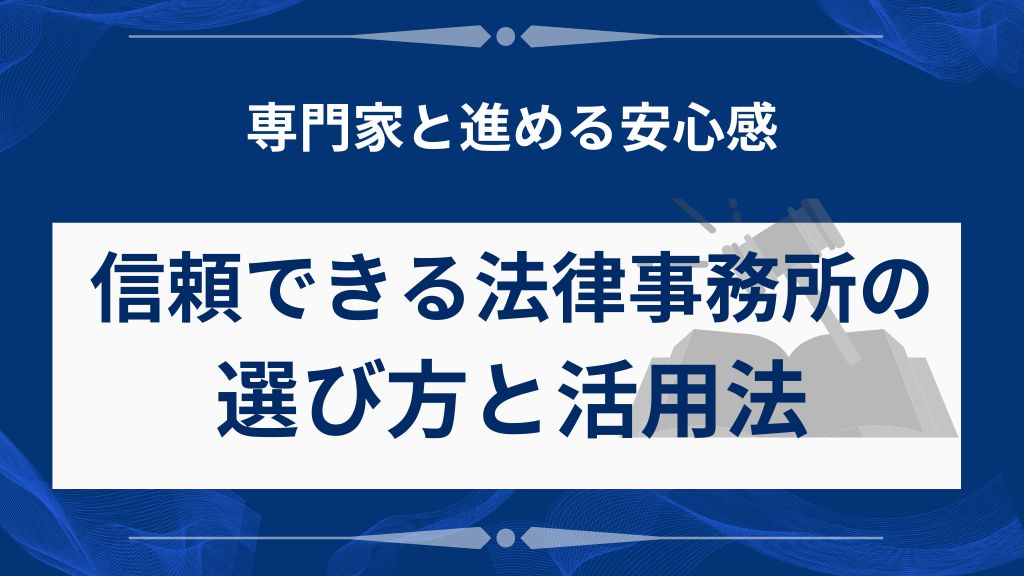
過払い金請求は法的な手続きが複雑で、ご自身で行うには多くの時間と専門知識が必要です。しかし、適切な専門家に依頼すれば、手続きの負担を大幅に減らせるだけでなく、より多くの過払い金を回収できる可能性も高まります。
専門家に依頼する最大のメリットは、貸金業者との交渉力にあります。経験豊富な弁護士や司法書士が代理人となれば、業者側も真剣に交渉に応じる傾向があります。過払い金の正確な計算や必要書類の準備、裁判手続きといった専門的な作業も全て任せられますから、あなたの負担は最小限に抑えられるはずです。
多くの法律事務所は成功報酬制を採用しています。これは、過払い金が回収できた場合にのみ費用が発生する仕組みです。つまり、回収できなければ費用はかからないため、リスクを抑えて請求手続きを進められます。
続いて、信頼できる法律事務所の選び方と無料相談活用のポイント、さらには相談前に準備しておくべき書類と情報について解説し、専門家とのスムーズな連携を支援します。
信頼できる法律事務所の選び方と無料相談活用のポイント
過払い金請求を依頼する法律事務所選びは、回収結果を左右する重要な判断になります。具体的には、以下のポイントに注目して選ぶと良いでしょう。
実績の確認
債務整理や過払い金請求の実績が豊富かどうか確認しましょう。ホームページで解決事例数や設立年数を確認し、この分野での経験が十分にあるかを確かめてみてください。
料金体系の明確さ
相談料、着手金、成功報酬の内訳を分かりやすく提示しているか確認しましょう。特に成功報酬については、回収額の何パーセントが報酬になるのか、裁判になった場合とそうでない場合で料金が変わるのかなど、詳細な説明を求めるようにしましょう。曖昧な説明しかしない事務所は避けるのが賢明です。
無料相談の活用
複数の事務所で相談を受けてみましょう。事務所によって回収見込み額や手続きの進め方が異なる場合があるため、比較検討することで、ご自身に合った選択ができます。
担当者の対応
質問に分かりやすく説明してくれるか、不安や疑問に真摯に向き合ってくれるかを確認してください。
相談前に準備しておくべき書類と情報
スムーズに相談を進めるには、事前の準備が大切です。具体的には、以下の書類や情報を準備しておくと効果的です。
借り入れ先の情報
どの会社からいつ頃借り入れを始めたのか、完済した時期はいつか、借り入れ時の金利は何パーセントだったかなど、覚えている範囲でメモにまとめておきましょう。
契約書や取引履歴
古い契約書などは紛失しているケースも多いため、なくても相談は可能です。専門家があなたの代理人として、貸金業者から取引履歴を取り寄せることができます。
身分証明書
運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認ができる書類が必要です。
現在の借入状況(返済中の場合)
最新の明細書や残高証明書があると、より正確な状況把握に役立ちます。
相談では、お金に関する不安や悩みを率直に伝えることが大切です。一人で抱え込まず、専門家のアドバイスを受けることで、ご自身の状況に最も適した解決方法を見つけやすくなります。
![非公開: 過払い金請求を自分でする方法は?請求の流れや成功への注意点を解説[bk]](https://saimu931.jp/wp-content/uploads/2024/07/4c2dd0dd9f5d56df11fb8fa0ee26d3dc.webp)
非公開: 過払い金請求を自分でする方法は?請求の流れや成功への注意点を解説[bk]
この記事では、借金の返済をしていたい人が過払い金と呼ばれる払いすぎた利息を自分で...
まとめ
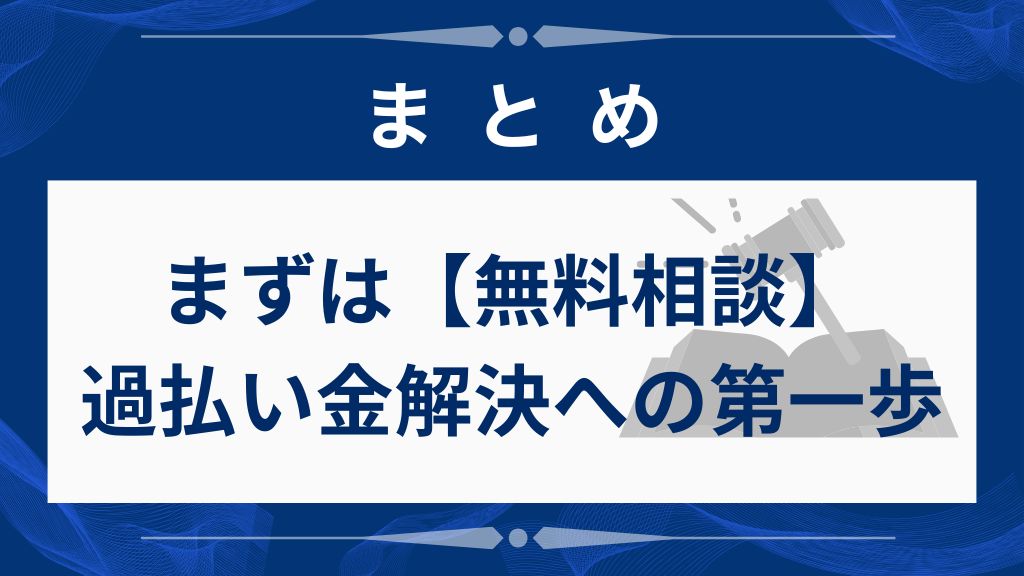
本記事では、過払い金とは何か、なぜ発生するのか、そしてご自身に過払い金があるかどうかを判断するための条件や、過払い金の請求方法、時効の注意点などを解説しました。
過払い金発生の主な条件は以下のとおりです。
- 2010年6月以前に、利息制限法の上限を超える金利(グレーゾーン金利)で借入をしていた。
- すでに完済しているか、大幅に残高を減らしている。
- 最後の取引から10年以内である(時効完成前)。
もし、これらの条件に心当たりがあるなら、一歩踏み出して調べてみることが大切です。過払い金請求には時効というタイムリミットがありますので、早めの行動が有利になります。
まずは無料相談を利用して、弁護士や司法書士といった専門家に自分の状況を話してみることから始めましょう。専門家はあなたの状況に応じた最適な解決策を提案してくれるはずです。
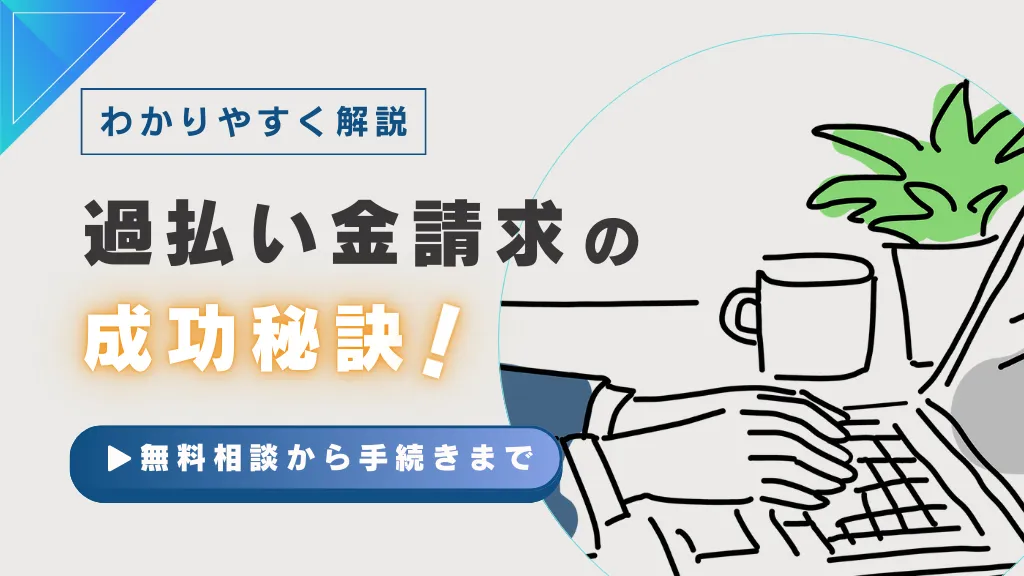
過払い金請求について無料で相談できる事務所の選び方を解説
この記事では、無料で相談ができる過払い金請求の事務所やサービスを探し、信頼できる...
この記事の監修者
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。 当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
この記事に関係するよくある質問
- 過払い金請求のCMが多いのはなぜですか?
- 過払い金のCMが多いのは、司法書士や弁護士事務所が過払い金請求案件の獲得を競い合っているためです。過払い金は、かつて金融機関が利息制限法の上限を超える金利で貸し付けていたことにより発生し、返還の対象となります。平成18年(2006年)の最高裁判決をきっかけに請求が認められるようになり、多くの法律事務所が広告費をかけて集客するようになったのが背景です。
- クレジットカードの過払い金を調べる方法は?
- クレジットカードの過払い金を確認するには、まずカード会社に「取引履歴」を請求し、その内容を基に「引き直し計算」を行うのが基本です。あわせて過払い金チェッカーを使って簡易的に診断したり、弁護士や司法書士などの専門家に調査を依頼したりする方法もあります。
- 過払い金請求のデメリットは?
- 過払い金返還請求の主なデメリットとして、請求先の業者から再び借り入れができなくなること、信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録される可能性があること、家族に借金が知られるおそれがあること、そして専門家への相談・依頼費用がかかることが挙げられます。特に返済中に請求し、過払い金で完済できない場合はブラックリストに載るリスクが高まります。
- 過払い金請求するとローンが組めなくなりますか?
- 完済済みの借金に対する過払い金請求であれば、基本的にローン審査に影響はありません。しかし、返済中に請求すると「債務整理」とみなされ、信用情報機関に事故情報が登録されてローンが組めなくなる可能性があります。特に住宅ローンなど大きな借り入れを予定している場合は、まず完済してから過払い金請求を行うのが安全です。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。