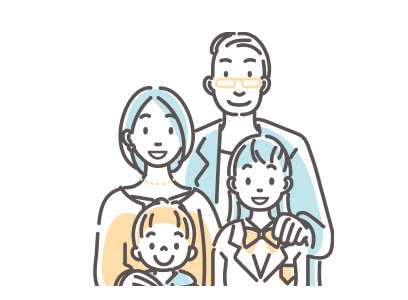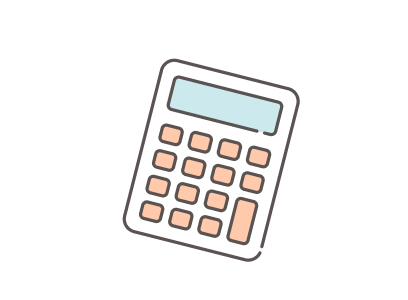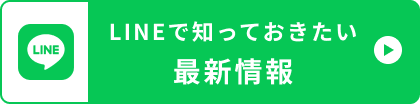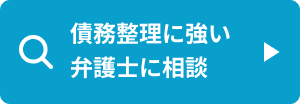個人再生で家を守ることができる?住宅ローン特則の活用法を解説
個人再生(民事再生)
2024.06.04 ー 2025.12.10 更新
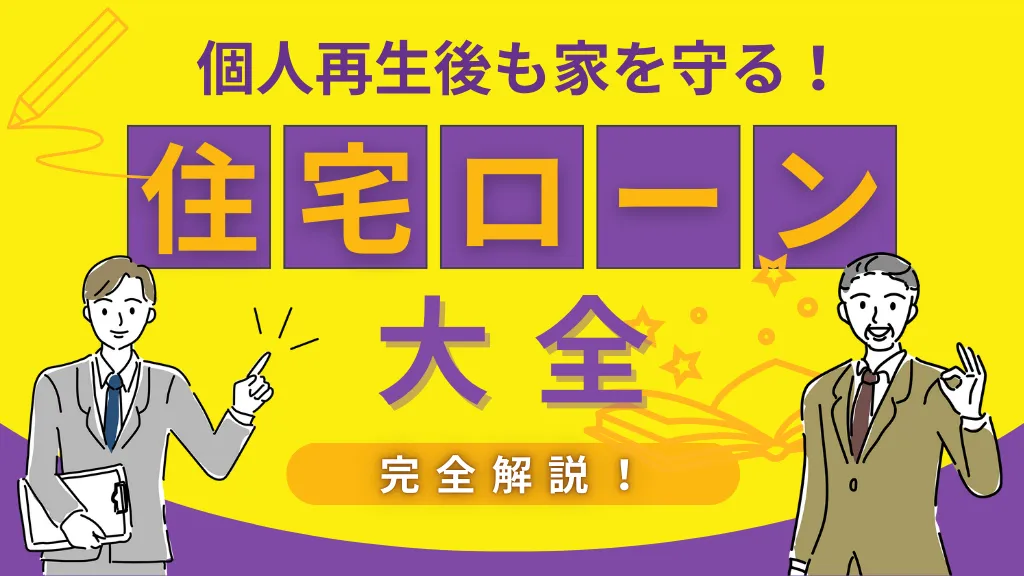
個人再生することで、借金の返済を無理なく行いながら、家を守ることができます。
この記事では、住宅ローン特則や条件、リフォームローンがある場合の対策など、様々なケースに応じた対策を詳しく解説します。これを読めば、あなたも家を守りながら借金問題を解決できるヒントを見つけることができるでしょう。
また、個人再生手続きの流れや必要書類、弁護士選びのポイントなど、実践的な情報もお伝えします。是非、参考にして前向きな気持ちで債務整理に向き合いましょう。
こんな人におすすめの記事です。
- 住宅ローンを抱えているが、借金の返済が厳しいと感じている方
- 自宅を手放さずに借金問題を解決したいと考えている方
- 個人再生手続きに関心があり、具体的な手続きや専門家のサポートについて知りたい方
記事をナナメ読み
- 個人再生は住宅ローン特則を活用することで、家を手放さずに借金問題を解決できる方法
- 専門家のサポートを受けて、適切な返済計画を立てることが成功の鍵
- 信用情報への影響を前向きに捉え、計画的な生活費管理を行うことで、安定した生活を送ることが可能
個人再生で家を残せる理由|住宅ローン特則とは

個人再生は、借金問題を抱える人々が経済的に立ち直るための法律手続きです。特に住宅ローン特則を活用することで、家を手放さずに済むという大きなメリットがあります。
この特則は、借金の返済が困難な状況でも、自宅を守るために設けられた制度です。個人再生の手続きを進める際に住宅ローン特則を適用することで、返済計画を現実的なものにし、家族と共に安心して住み続けることが可能になります。
以下では、住宅ローン特則がある理由やその効果、具体的な利用方法について詳しく説明します。
個人再生で家が残せるのは住宅ローン特則があるから
個人再生で家を残すことができるのは、住宅ローン特則という制度があるからです。この特則は、住宅ローンを抱えている人が個人再生手続きを行う際に、自宅を手放さずに済むように設けられたものです。
住宅ローン特則が適用されると、住宅ローンの元本や利息の返済条件が緩和される場合があります。例えば、返済期間を延長することで月々の返済額を減らし、無理のない返済計画を立てることが可能です。
住宅ローン特則の適用には、以下のような要件があります。まず、申立人が住宅ローンを含むすべての債務について正確に申告し、その居住用不動産が主たる住居であることを示さなければなりません。また、特則を適用するためには、裁判所や債権者の同意が必要です。
これにより、債務者は家族と共に安心して住み続けることができます。
住宅ローン特則の効果
住宅ローン特則の効果は非常に大きく、個人再生手続きを行う人々にとって重要な救済手段となります。
まず、特則が適用されることで、住宅ローンの返済負担が軽減されます。返済期間の延長や利息の減額が可能となり、これによって月々の返済額が低く抑えられます。
さらに、住宅ローン特則を利用することで、債務者は自宅を手放さずに済むため、家族の生活の安定が保たれます。
この特則は、個人再生の手続きの一環として、裁判所により正式に認可される必要があります。認可を受けるためには、再生計画案の提出が求められます。この計画案には、住宅ローンの返済スケジュールや具体的な返済方法が詳細に記載されている必要があります。
特則の効果を最大限に引き出すためには、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けながら手続きを進めることが推奨されます。専門家のアドバイスを受けることで、特則の適用をスムーズに進めることができ、最終的には経済的な再建を図ることができます。
住宅ローン特則を利用する方法
住宅ローン特則を利用するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。
まず、個人再生手続きを開始する前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家の助けを借りて、債務者の財務状況を正確に把握し、住宅ローン特則の適用が可能かどうかを判断しましょう。
その後、再生計画案を作成します。この計画案には、住宅ローンの返済条件や新たな返済スケジュールが詳細に記載されます。再生計画案は、裁判所に提出し、裁判所の審査を受けます。
裁判所が再生計画案を認可すると、特則の適用が正式に決定されます。特則が適用されると、住宅ローンの返済条件が変更され、債務者は新たな条件に基づいて返済を進めることになります。
重要なのは、特則の適用を受けた後も、計画通りに返済を続けることです。返済計画に従わなかった場合、特則の効果が失われ、再び返済困難に陥る可能性があります。
そのため、返済計画を守り、計画的に返済を進めることが必要です。住宅ローン特則を使うことで、債務者は経済的な負担を軽減しながら、自宅を守り、家族と共に安心して生活を続けることができます。
住宅ローンが残っている家を個人再生で残す4つの条件

住宅ローンが残っている家を個人再生で守りたいという方も多いでしょう。住宅ローンが残ったままで家を残すための4つの条件をご紹介します。
- 申立人が所有権を持っていること
- 住居目的の家であること
- 住宅ローン以外で担保にされていないこと
- 個人再生の計画が認められること
これらの条件を満たすことで、お住まいを守りながら、借金の問題を解決することができます。頑張って前向きに取り組んでいきましょう。
所有権が申立人にあり、住居目的の家である
個人再生で家を残すためには、まず所有権が申立人にあることが重要です。これは、購入した家が申立人名義であり、住居目的で使用されていることを意味します。
賃貸物件や事業用の不動産は対象外となります。住居目的の家であれば、再生手続きで住宅ローンの返済計画を立て直すことが可能です。契約時に所有権を確認し、申立人がそのまま住み続けることができるように手続きを進めることが重要です。
住居目的の家であることを示すために、住民票や公共料金の請求書などの書類が必要になります。
家が住宅ローン以外の担保になっていない
個人再生で家を守るためのもう一つの条件は、家が住宅ローン以外の担保になっていないことです。もし家が他の借金の担保に使われている場合、個人再生の手続きで家を残すことは難しくなります。
住宅ローンだけを担保としている場合、再生手続きで住宅ローンの返済計画を見直すことが可能です。他の担保が設定されていると、再生計画の実行が複雑化し、時間がかかることがデメリットとなります。
そのため、再生手続きを始める前に、家がどのような担保に使われているかを詳細に確認し、必要ならば専門家と対処法を相談することがよいでしょう。
保証会社の代位弁済から6ヶ月以内
保証会社の代位弁済から6ヶ月以内に対応することが大切です。その理由は、債務者が滞納を繰り返すと、保証会社が債権者に代わって借金を弁済する代位弁済が行われます。しかし、その後に返済計画を立てることが可能で、無料の相談窓口や専門の事務所を活用することがおすすめです。
具体例として、債務整理を行うことで、返済期間の延長や金利の減額ができる場合もあります。また、裁判所に個人再生手続きを申し立てる方法や、任意整理で債務を減額する方法もあります。ただし、これらの手続きは専門知識が必要ですので、弁護士や司法書士に相談しましょう。
まとめとして、保証会社の代位弁済から6ヶ月以内に適切な対応をすることで、借金問題を解決し、家族や自分の生活を守ることができます。頼れる専門家に相談し、前向きな気持ちで立ち向かいましょう。
家に保証会社の抵当権が設定されている
家に保証会社の抵当権が設定されている場合、注意が必要です。というのも、債務の返済が滞ると、家が競売にかけられる可能性があるからです。しかし、安心してください。対策はあります。
まず、債務整理を行い家を守る方法があります。個人再生手続きや任意整理など、返済計画を見直すことで、競売を回避することが可能です。ただし、専門家のアドバイスが必要ですので、弁護士や司法書士に相談しましょう。
また、家族や親族が連帯保証人となっている場合、連帯保証人も債務の返済を行わなければなりません。家族の負担を減らすためにも、早めの対処が大切です。
最後に、前向きな気持ちと正しい知識が大切です。借金問題を解決する道は必ずありますので、希望を持ち続けましょう。
住宅ローンがない家は個人再生で残せる?
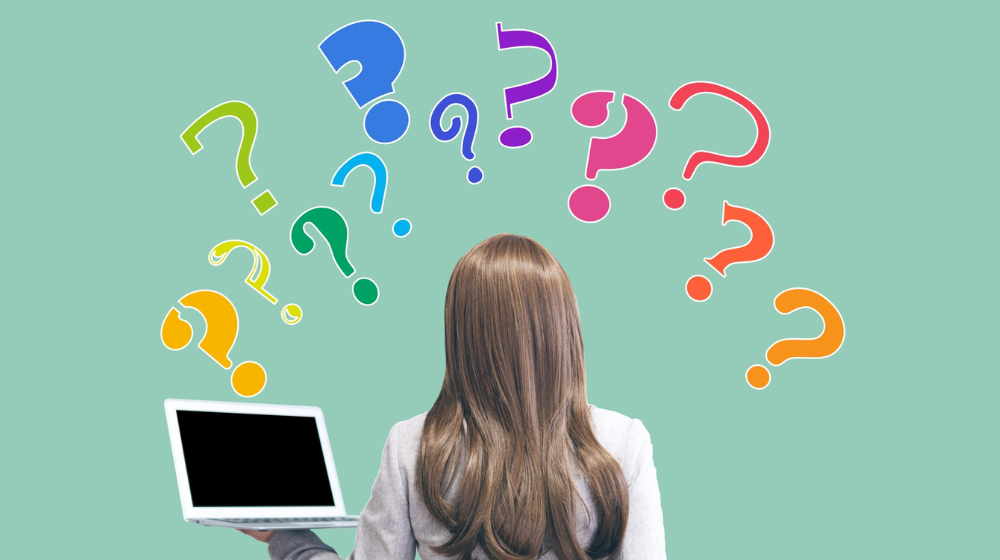
住宅ローンがない家は個人再生で残すことができます。個人再生手続きは、借金の返済計画を立て直すことで、家や車などの財産を守ることができる法律手続きです。
住宅ローンがない場合、家を担保にしていないため、競売の対象にならないケースがほとんどです。ただし、他の債務によって家に抵当権が設定されている場合は注意が必要です。
結論として、住宅ローンがない家は個人再生手続きで残せることが一般的ですが、他の債務状況や抵当権の有無によって異なる場合があります。専門家に相談し、最適な解決方法を見つけましょう。
家の資産価値が最低弁済額より少なければ残せる場合がある
家の資産価値が最低弁済額より少ない場合、残せる可能性があります。その理由として、債権者側が回収を諦めることが挙げられます。家を手放すことなく、債務の圧縮ができるので、前向きな気持ちになれます。
具体例として、任意整理や個人再生といった方法があります。任意整理は、債務を減額し、返済計画を立てることができます。個人再生は、裁判所を通じて債務を減額し、返済計画を立てることができます。どちらの方法でも、家族の理解と協力が大切です。
ただし、以下の条件が必要です。
- 債務の一部を放棄してもらえること
- 家族や保証人が支援してくれること
- 家の資産価値が最低弁済額より低いこと
以上の条件が揃えば、家を残すことができます。専門家と相談し、適切な方法を選ぶことが大切です。
住宅ローンを完済した家を残せるケース
住宅ローンを完済した家を残せるケースもあります。その理由は、住宅ローンが完済されているため、担保が消滅しているからです。家が債権者に取られる心配はなく、安心して生活できます。
具体例としては、個人再生や破産の手続きが挙げられます。個人再生では、他の債務が減額され、返済計画が立てられます。破産手続きでは、他の債務が免除されます。
ただし、以下の条件が必要です。
- 住宅ローンの完済
- 他の債務が適切に整理されること
これらの条件が揃えば、家を残しながら、前向きな人生を送ることができます。適切な方法を選ぶことが大切なので、専門家に相談しましょう。
家の資産価値が最低弁済額より高い場合は経済的に困難な可能性がある
家の資産価値が最低弁済額より高い場合、経済的に困難な状況に陥るかもしれません。その理由は、家の価値が高いため、債権者が家を売却して回収しようとするからです。
具体例として、競売があります。競売では、裁判所が財産を売却して債務を弁済します。しかし、家族全員が同じ状況にある場合は、家を残すことができる可能性があります。
条件は以下の通りです。
- 家族が連帯保証人でないこと
- 家族が債務を引き受けることができないこと
これらの条件が揃えば、家を残すチャンスがあります。まずは専門家に相談し、最善の方法を選びましょう。
家のリフォームローンがある人の個人再生

個人再生を検討している方の中には、家のリフォームローンがある場合も多いです。しかし心配ご無用、個人再生を通じて、借金の整理が可能であり、より軽い返済計画に移行できます。
リフォームローンについても、法律の専門家である弁護士や司法書士と相談することで、適切な手続きを行い、家族との暮らしを守ることができるでしょう。
ただし、リフォームローンには担保がある場合と無担保の場合があり、個人再生の手続きが異なる点に注意が必要です。抵当権がある場合は、債務整理を進める前に、担保の状態や金融機関との交渉が重要になります。
無担保の場合も、返済計画の再整備が求められるでしょう。どちらのケースでも、専門家と相談して適切な対応を進めることが、前向きな気持ちで借金問題に取り組むための大切なポイントです。
家のリフォームローンに抵当権がついている場合
家のリフォームローンに抵当権がついている場合、個人再生手続きにはいくつかの注意点があります。まず、担保である家に対する金融機関との交渉が重要になります。これにより、競売を回避できる可能性が高まり、家族との暮らしも守れるでしょう。
また、リフォームローンの返済額や利息を減額し、家の維持費や家族の生活費を確保することが大切です。これが可能であれば、滞納しなくても良い状態になり、家族の暮らしを維持できます。
ただし、抵当権がある場合でも、家の価値やローン残高によっては、個人再生が難しいケースもあり得ます。専門家と相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
家のリフォームローンが無担保の場合
家のリフォームローンが無担保の場合、個人再生手続きは比較的簡単です。まず、法律の専門家と相談し、返済計画の再整備を行いましょう。これにより、返済額や利息が減額され、家族の生活費を確保できるようになります。
また、無担保なので、家を失うリスクが低いため、家族との暮らしを守ることができます。ただし、元々の借金の状態や金利によっては、再生計画の達成が難しい場合もあります。
そのため、専門家と相談しながら、材料費や労務費などのリフォームに関する費用の計画を見直し、無理のない返済計画にすることが大切です。
個人再生の手続きの流れと必要書類
個人再生は、住宅ローンを抱える人が借金問題を解決するための効果的な手続きです。まず、専門家に相談し、債権や居住状況などの情報を元に再生計画を立てます。
この計画には元本の減額や返済期間の延長などが含まれ、裁判所に申立てを行い受付を済ませます。裁判所は再生計画を審査し、適正であると判断した場合、再生計画が認可されます。
認可後は計画に沿って返済を進め、最終的に借金の解消を目指します。手続き全体は通常3〜5年かかり、それぞれのステップで慎重な対応が求められます。必要書類には収入証明書、資産状況を示す書類、債権者との契約書、居住状況を証明する書類などがあり、これらを揃えることで手続きがスムーズに進みます。
手続きの概要と流れ
個人再生の手続きは複雑ですが、手順を理解することでスムーズに進めることができます。まず、専門家に相談し、債権や居住状況などの情報を元に、再生計画を立てます。この計画には元本の減額や返済期間の延長などが含まれます。
計画がまとまったら、裁判所に申立てを行い、受付を済ませます。裁判所は再生計画を審査し、適正であると判断した場合、再生計画が認可されます。
認可後は、計画に沿って返済を進め、最終的に借金の解消を目指します。手続き全体は通常3〜5年かかり、それぞれのステップで慎重な対応が求められます。
必要な書類と準備方法
個人再生の手続きには、いくつかの必要書類があります。
まず、収入証明書や資産状況を示す書類が必要です。これには給与明細や銀行の預金通帳、所有する不動産の登記簿謄本などが含まれます。
また、債権者との契約書や借入明細書も重要な書類です。これらの書類は、再生計画の妥当性を判断するために必要です。
さらに、居住状況を証明するための書類として、住民票や公共料金の請求書も求められます。準備する際は、書類が揃っているか確認し、不足がないように注意しましょう。
これにより、手続きがスムーズに進みます。個人再生はお金の問題を解決する強力な対処法ですが、準備と計画が成功の鍵となります。
個人再生による生活再建のポイント

個人再生は、多重債務に苦しむ人々が再スタートを切るための重要な手続きです。借金の一部を減額し、残りを長期間にわたって無理のない返済計画で返済することができます。
特に、住宅ローンを抱えている場合でも、自宅を手放さずに再建を図ることが可能です。個人再生を成功させるためには、手続きの正しい理解と計画的な実行が不可欠です。
また、家計の見直しや生活費の管理、支援を受けることも大切です。以下に、具体的なポイントについて詳しく説明します。
住宅ローンの取り扱い方法
住宅ローンがある場合、個人再生の手続きでは「住宅資金特別条項」を活用することで、自宅を手放さずに済むことが可能です。この条項を適用するためには、一定の条件を満たす必要があります。
まず、住宅ローンが対象となる債務であること、そして再生計画において住宅ローンの返済を続ける意思があることを示さなければなりません。具体的には、返済計画の中で住宅ローンの優先順位を確保し、他の債務と分けて計画を立てます。
住宅ローン債権者との交渉も重要で、再生計画の内容に同意を得る必要があります。また、返済計画の実行においても、毎月の収支を厳格に管理し、計画通りの返済を続けることが求められます。これにより、家族と共に住み続けられる安心を確保しながら、経済的な再建を図ることができます。
個人再生後の生活費管理
個人再生が認可されると、新たな生活費管理が求められます。まず、毎月の収入と支出を見直し、無駄な出費を削減することが重要です。家計簿をつけることで、収支のバランスを把握し、必要な支出と不要な支出を明確にすることができます。
特に、食費や光熱費、通信費などの固定費を見直し、節約できる部分を探します。次に、予算計画を立て、それに基づいて生活することが求められます。予期せぬ出費にも備えるために、緊急用の貯金も少しずつ積み立てることが大切です。
また、返済計画に基づいた定期的な返済を続けることで、信用を回復し、将来的な経済的安定を目指します。支出を管理し、計画的な生活を送ることで、再生後の生活を安定させ、安心して暮らすことができるようになります。
生活再建に向けた支援とアドバイス
生活再建を成功させるためには、様々な支援とアドバイスを活用することが重要です。まず、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることで、手続きのスムーズな進行と適切なアドバイスを得ることができます。
次に、家族や友人の協力も大切です。再建に向けた計画を共有し、協力をお願いすることで、精神的な支えとなります。また、コミュニティや支援団体の活用も検討してみましょう。地域の支援団体やカウンセリングサービスなどは、経済的な問題だけでなく、心理的なサポートも提供しています。
さらに、生活再建のための情報を積極的に収集し、自分自身の知識を深めることも重要です。インターネットや図書館などで情報を調べることで、自分に合った支援策やアドバイスを見つけることができます。生活再建は一人で抱え込まず、周囲のサポートを受けながら進めることが成功への鍵です。
弁護士への相談方法と選び方

借金の問題を解決するために弁護士に相談する方法は、まず弁護士会やインターネットのサイトで検索し、無料で相談できる事務所を見つけることです。次に、相談前に返済状況や借金額、金融機関などの情報を整理し、具体的な質問を考えておきましょう。
また、弁護士の選び方としては、借金の専門家であること、実績が豊富であること、アフターケアも充実していることが重要です。口コミや評判も参考にし、信頼できる人物を選ぶことが大切です。
弁護士に相談するメリット
弁護士に相談するメリットは、専門的な知識と経験を持っているため、最適な解決策を提案してくれます。具体的には、任意整理や自己破産といった手続きを適切に進めてくれるだけでなく、過払い金請求などの権利を守り、負担を軽減する方法も教えてくれます。
また、弁護士は債権者と交渉する力があり、返済の減額や猶予期間の延長を可能にします。さらに、弁護士に相談することで、家族や友人には相談しにくい個人的な悩みも打ち明けることができ、心の支えとなります。
適切な弁護士の選び方
適切な弁護士を選ぶためには、まず専門性を確認しましょう。借金問題に詳しい弁護士は、効果的なアドバイスや適切な手続きが期待できます。また、事務所の雰囲気や対応をチェックし、安心して相談できるかどうかを見極めることも大切です。
次に、実績や評判を調べます。インターネットや口コミで情報を集め、信頼できる弁護士を探しましょう。最後に、費用やアフターサポートも考慮し、自分の状況に合った弁護士を選ぶことが成功への鍵となります。
個人再生後の生活再建のポイント

個人再生手続きが完了した後、生活を再建するためのポイントを押さえることが重要です。個人再生によって借金が減額され、無理のない返済計画が立てられますが、再建には計画的な生活費の管理や信用情報の回復、専門家のサポートが不可欠です。
また、家族やコミュニティからの支援も大きな助けとなります。以下では、新たな生活費管理の方法や信用情報の回復手段、専門家のサポートとアフターケア、家族やコミュニティの支援の重要性について詳しく説明します。
新たな生活費管理の方法
個人再生後には、生活費の管理が再建の鍵となります。まず、毎月の収入と支出を見直し、無駄な出費を削減することが重要です。
家計簿をつけることで、どこにお金が流れているのかを把握し、必要な支出と不要な支出を明確に分けることができます。特に、食費や光熱費、通信費などの固定費を見直し、節約できる部分を探すことが大切です。
次に、予算計画を立て、それに基づいて生活することを心掛けましょう。予期せぬ出費にも備えるために、緊急用の貯金を少しずつ積み立てることも忘れずに。
また、返済計画に基づいた定期的な返済を続けることで、信用を回復し、将来的な経済的安定を目指すことができます。計画的な生活を送ることで、再生後の生活を安定させ、安心して暮らすことができるようになります。
信用情報の回復手段
個人再生手続き後、信用情報に与える影響を理解し、信用を回復するための具体的な手段を講じることが重要です。
まず、個人再生によるブラックリスト登録期間は5~7年です。この間は新たなローンやクレジットカードの利用が制限されますが、返済を滞りなく続けることで、徐々に信用が回復します。
次に、クレジットスコアの改善に努めましょう。小額のローンや携帯電話の分割払いなど、信用情報にプラスとなる行動を積み重ねることが有効です。
また、信用情報機関に定期的に問い合わせ、自分の信用状況を確認することも大切です。必要に応じて、信用情報の訂正を依頼することも可能です。さらに、借金完済後には、信用情報機関に完済証明を提出し、情報の更新を促しましょう。
信用回復には時間がかかりますが、計画的な行動と継続的な努力で、再び信用を築き上げることができます。
専門家のサポートとアフターケア
個人再生後の生活再建には、専門家のサポートとアフターケアが欠かせません。弁護士や司法書士は、再生手続きだけでなく、その後の生活再建に向けたアドバイスやサポートも提供します。
例えば、返済計画の見直しや家計管理の方法、再度の債務整理が必要な場合の対応策など、専門的な知識と経験を活かしたアドバイスが得られます。また、定期的な相談やチェックインを通じて、生活再建が順調に進んでいるかを確認し、必要に応じて適切な対応を取ることができます。
専門家のサポートを受けることで、個人再生後の不安や悩みを軽減し、確実に生活再建を進めることができます。さらに、アフターケアとして、必要に応じて心理的な支援やカウンセリングも活用することで、心の健康を保ちながら、前向きに生活を再建することができます。
家族やコミュニティの支援の重要性
個人再生後の生活再建には、家族やコミュニティからの支援が重要です。まず、家族の理解と協力が不可欠です。
再生計画を共有し、家族全員で協力して家計管理や生活費の節約に取り組むことで、再建のプロセスがスムーズに進みます。また、家族の精神的な支えが、再生後の生活の安定にも繋がります。
次に、地域社会やコミュニティの支援も大きな助けとなります。地域の支援団体やカウンセリングサービスを利用することで、経済的な問題だけでなく、心理的なサポートも得ることができます。
さらに、同じような経験を持つ人々との交流を通じて、情報やアドバイスを共有し合うことも有益です。家族やコミュニティの支援を積極的に活用し、一人で抱え込まずに支え合いながら生活再建を進めることで、成功への確率が高まります。
まとめ:個人再生で住宅ローンを抱える家を守る方法

個人再生は、借金の総額が多くても自宅を手放さずに生活を再建するための手続きです。特に、住宅ローン特則を活用することで、家を守ることができます。この特則は、一定の要件を満たすことで適用され、住宅ローンの返済が滞納していないこと、家族が同居していること、住宅を担保にしたローンがあることなどが含まれます。
個人再生の申立てを行う前に、専門家に依頼して債権者との交渉や手続きの進行をサポートしてもらうことが重要です。弁護士や司法書士は、借金の総額や返済能力を考慮し、最適な返済計画を立案します。この計画には、通常の返済額よりも大幅に減額された金額が含まれることがあり、債権者の同意を得ることが求められます。
個人再生手続きでは、収入証明書や資産状況の証明、債務状況の証明などの書類を揃える必要があります。銀行からの借金や税金の滞納なども含めて全額を見直し、現実的な返済計画を組むことが大切です。これにより、住宅ローンの返済期限を延長したり、金利を減額したりすることが可能になります。
また、個人再生手続きが開始されると、本人の信用情報にブラックリストとして登録されることがあります。このため、新たなローンやクレジットカードの利用が制限されることがありますが、この制約を前向きに捉え、無駄な出費を削減することで、安定した生活を送ることができます。
個人再生の手続きを通じて、家族と共に新しい生活を始めるためには、専門家のサポートを受けながら、返済計画を確実に実行することが重要です。債権者との交渉や裁判所での手続きをスムーズに進めるために、適切な対処法を学び、計画的に取り組みましょう。
この記事の監修者
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。 当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
この記事に関係するよくある質問
- 個人再生後何年でローンを組める?
- 個人再生後にローンを組めるようになるのは、任意整理であれば約5年程度です。自己破産や個人再生の場合は、信用情報機関に8年程度登録されるため、ローンが組めるのは最短で5年後、最長で7年後となります。なお、任意整理の場合は、信用情報機関や契約内容により異なりますが、完済してから5年間とされることが多いです。
- 個人再生で借金はどれくらい減る?
- 個人再生では、借金を5分の1から10分の1程度に減額し、残りを3〜5年程度で返済する計画を立てます。この減額後の返済しなければならない額を「最低弁済額」といいます。そのため、個人再生を申し立てる前に「最低弁済額」がいくらになるのかを想定しておくことが重要です。
- 個人再生は何年で消える?
- 個人再生でブラックリストに登録される期間は5~7年です。この期間中は、新しく借金をしたりクレジットカードを作ったりすることができません。ただし、順調に返済を続けていれば、完済・解約から5~7年でブラックリストから外されます。
- 個人再生が通らなかったらどうなるの?
- 個人再生の再生計画が通らなかった場合、不認可となった時点でこれまで進めてきた個人再生の手続きは終了します。再生計画案で示した借金の減額は認められません。ただし、一度不認可になった場合でも、再度個人再生の申し立てを行うことは可能です。
- 個人再生は妻に影響しますか?
- 個人再生手続きを行っても結婚相手に影響することはありません。これは既に結婚している場合も同じです。個人再生手続きをするためには、配偶者の収入状況などの情報が必要になりますが、それによって配偶者や婚約者が個人再生手続きをするわけではありません。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。