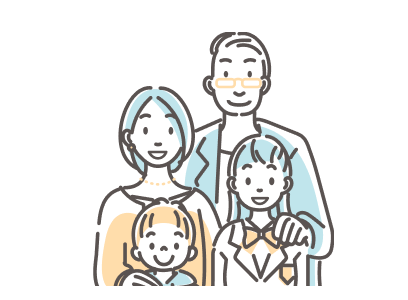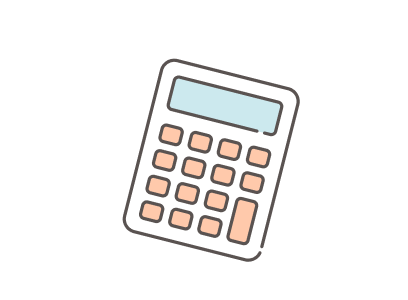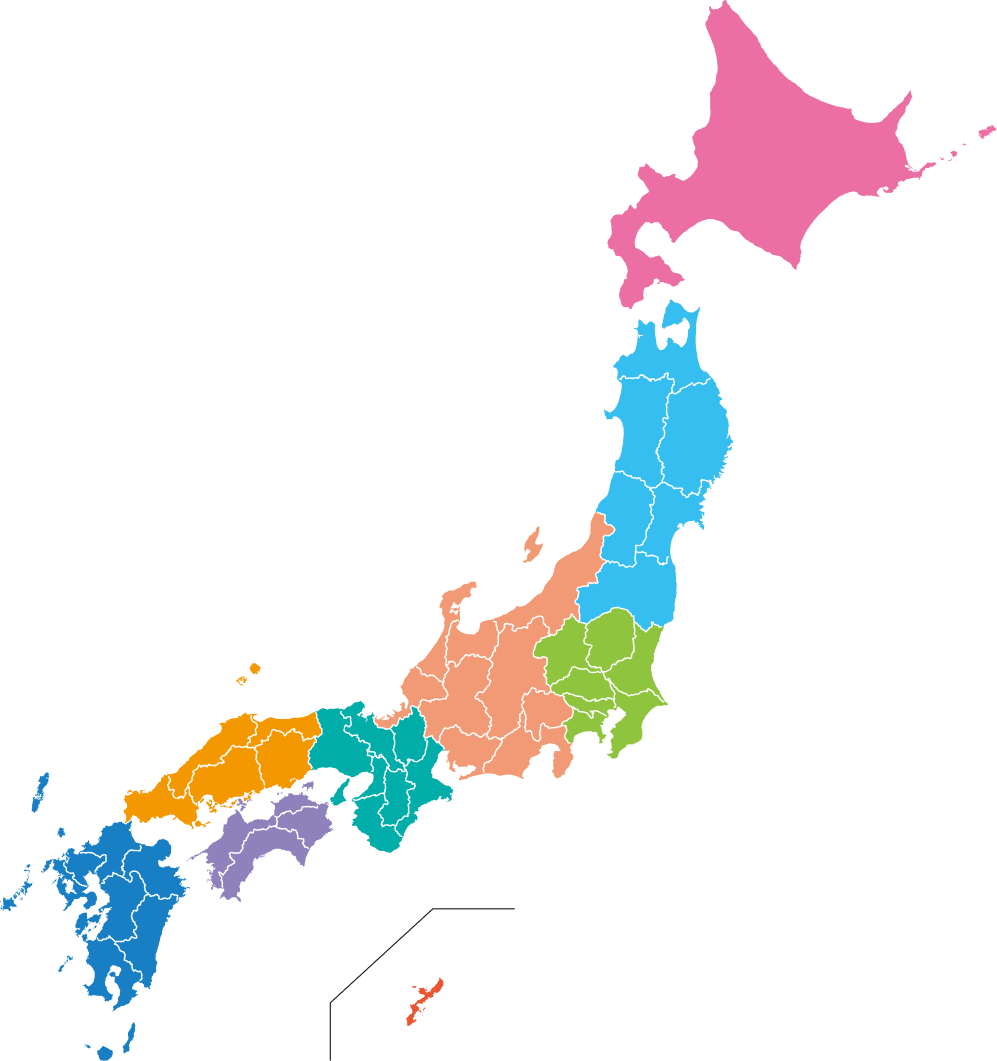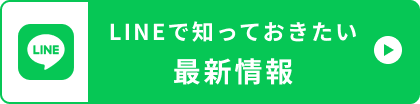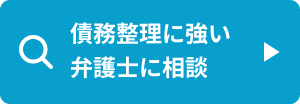個人再生の手続きを解説!個人事業主が相談する前に知るべきこととは?
個人再生(民事再生)
2025.04.16 ー 2025.04.15 更新
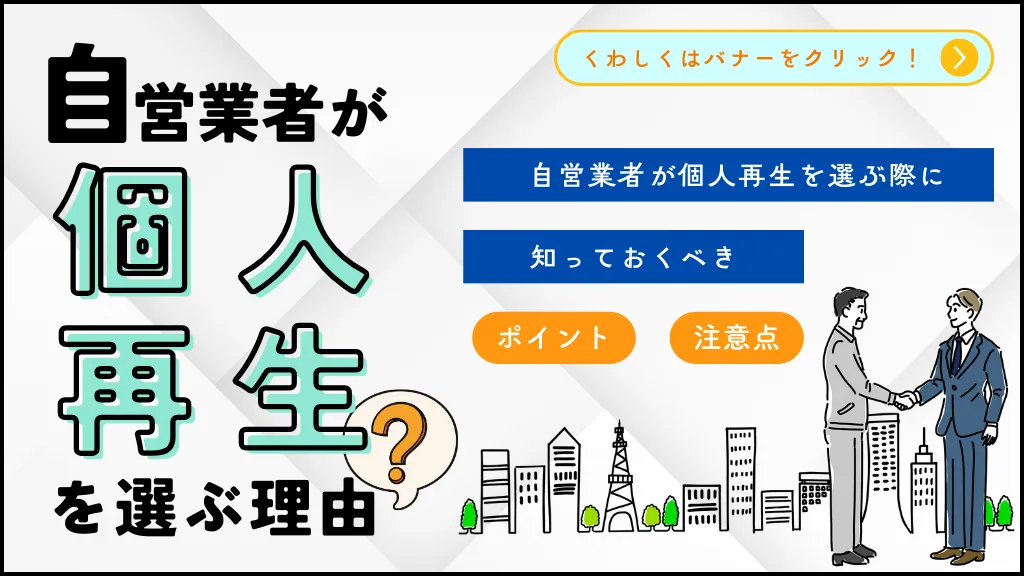
借金問題に悩む個人事業主の方へ、本記事では自己破産以外の選択肢として「個人再生」について解説します。個人再生は、借金を大幅に減額し、最低限の支払で生活や事業の再建を目指せる制度です。住宅や自動車を手放さずに済む場合が多いため、特に事業や家庭を守りたい人には有効な手段です。自己破産では全ての財産を失うリスクがある一方、個人再生なら住宅ローン特則等を利用することで家や車を維持できます。何より、免責によって借金から解放される安心感があります。
以下の内容では、個人再生の条件や注意点、他の債務整理方法との違いなどを詳しく紹介します。事前に専門家に予約を取り、相談することで最適な解決策を見つける一歩を踏み出しましょう。本記事が、借金問題解決の一助となれば幸いです。
こんな人におすすめの記事です。
- 借金問題を抱えている個人事業主で、事業を継続しながら負担を減らしたいと考えている方
- 住宅や自動車を手放さずに借金を整理する方法を探している方
- 自己破産以外の選択肢を知りたい、または免責や返済条件について具体的な情報を求めている方
記事をナナメ読み
- 個人再生は、借金を大幅に減額しながら事業や生活を継続することができる有効な方法
- 住宅や自動車を守れる可能性が高く、自己破産と比較して財産を手放すリスクが少ない
- 専門家に相談することで、自分に適した解決策を見つけ、安心して借金問題に取り組むことが重要
自営業者が個人再生を選ぶ理由とは?

自営業者が個人再生を選択する理由は、事業を継続しながら債務の整理ができる点にあります。個人再生は、借金の一部を免除してもらいながら、残りを分割で返済していく制度です。自営業者にとって、この制度は事業を続けながら借金問題を解決できる有効な手段となります。
個人再生を選ぶ自営業者の多くは、経営不振や予期せぬ出費により債務が膨らんでしまった状況にあります。しかし、事業自体には将来性があり、継続する価値があると判断している場合が多いのです。個人再生を利用することで、過大な債務から解放され、事業に専念できる環境を整えることができます。
また、個人再生は自己破産と比べて社会的な信用への影響が小さいという利点もあります。取引先や顧客との関係を維持しやすく、事業の継続性を確保しやすいのです。このように、自営業者が個人再生を選ぶ背景には、事業継続と債務整理の両立を図りたいという強い意志があります。
自営業者が抱える典型的な借金問題
自営業者が抱える借金問題は、事業の性質上、一般のサラリーマンとは異なる特徴を持っています。多くの場合、事業資金の調達や運転資金の確保のために借入を行うことが多く、その結果として債務が膨らみやすい傾向にあります。特に、景気の変動や競合他社との競争激化により売上が減少した場合、返済が困難になるケースが少なくありません。
また、自営業者は個人保証を求められることが多く、事業の失敗が個人の借金問題に直結しやすい構造があります。さらに、取引先への支払いや従業員の給与など、事業を継続するために必要な支出が優先されるため、個人的な借金の返済が後回しになりがちです。
加えて、自営業者は収入が不安定であることも借金問題を複雑にする要因となっています。季節変動や景気の影響を受けやすく、安定した返済計画を立てることが難しい場合があります。このような状況下で、税金や社会保険料の滞納も重なると、さらに深刻な債務問題に発展することがあります。
これらの要因が重なり、自営業者の借金問題は複雑化・長期化しやすく、個人再生などの法的手続きを検討せざるを得ない状況に陥ることがあります。
個人再生が自営業者に適している理由
個人再生は、自営業者にとって適した債務整理の方法として注目されています。その理由の一つは、事業を継続しながら借金を整理できる点です。通常の破産手続きでは事業の継続が困難になる可能性がありますが、個人再生では事業資産を保持したまま債務の返済計画を立てることができます。
また、個人再生は将来の収入を見込んで返済計画を立てるため、事業の成長性がある自営業者にとって有利です。収入の変動が大きい自営業の特性に合わせて、柔軟な返済計画を立てることが可能です。
さらに、個人再生では債権者との個別交渉が不要なため、自営業者の時間と労力を節約できます。裁判所の関与のもと、公平な返済計画が立てられるため、債権者との関係悪化を避けられる点も魅力です。
加えて、個人再生では住宅ローンなどの担保付き債務の取り扱いが柔軟です。自宅兼事務所を持つ自営業者にとって、この点は特に重要です。債務の一部免除を受けながらも、事業に必要な資産を守ることができるのです。
個人再生を行うメリットとデメリット

個人再生は自営業者にとって重要な選択肢の一つですが、メリットとデメリットを慎重に検討する必要があります。メリットとしては、事業を継続しながら債務を整理できる点が挙げられます。返済額が軽減され、最長5年で債務から解放される可能性があるため、経営の立て直しに集中できます。また、一部の財産を手元に残せるため、事業に必要な資産を確保できます。
一方、デメリットとしては、信用情報に記録が残り、新規の借入れが困難になる可能性があります。また、手続きが複雑で時間がかかることや、裁判所の管理下に置かれるため、事業の自由度が制限されることも考慮すべき点です。さらに、再生計画が認められなければ破産手続きに移行するリスクもあります。
個人再生は自営業者にとって有効な選択肢ですが、専門家のアドバイスを受けながら、自身の状況に適しているか十分に検討することが重要です。
自営業者にとっての個人再生のメリット
自営業者にとって個人再生は、事業を継続しながら債務を整理できる有効な選択肢です。最大のメリットは、事業用資産を手放すことなく返済計画を立てられる点です。通常の破産手続きでは事業継続が困難になりますが、個人再生なら営業を続けながら債務整理が可能です。
また、個人再生では債務の一部が免除されるため、返済負担が軽減されます。これにより、事業に集中できる環境が整います。さらに、個人再生中は債権者からの取り立てが停止されるため、精神的な負担も軽減されます。
個人再生は、将来の収入で返済を行う制度です。自営業者の場合、収入の変動が大きいことがありますが、個人再生では収入に応じた柔軟な返済計画を立てられます。これにより、無理のない返済が可能になり、事業の安定化にもつながります。
加えて、個人再生では信用情報の回復が比較的早いという利点もあります。これは、取引先との関係維持や新規取引の開拓において重要な要素となります。自営業者にとって、信用の回復は事業の発展に直結する重要な要素です。
個人再生が抱える一般的なデメリット
個人再生には、債務者にとっていくつかの一般的なデメリットが存在します。まず、個人再生手続きを行うと、その事実が信用情報機関に最長10年間登録されます。これにより、新規のローンやクレジットカードの作成が困難になる可能性があります。また、個人再生中は裁判所の管理下に置かれるため、一定の自由が制限されます。例えば、高額な買い物や新たな借入れには裁判所の許可が必要となります。
さらに、個人再生では債務の一部免除を受けられますが、その分返済期間が最長5年間と長期にわたります。この間、毎月の返済を継続する必要があり、生活に一定の制約がかかることは避けられません。加えて、個人再生の申立てには弁護士や司法書士への依頼が一般的で、その費用負担も考慮しなければなりません。
最後に、個人再生は債務整理の一種であるため、取引先や関係者に知られると信用低下につながる可能性があります。特に自営業者の場合、この点は事業継続に影響を与える可能性があるため、慎重に検討する必要があります。
自営業者の個人再生、手続きの流れを解説

自営業者が個人再生を選択する場合、手続きの流れを理解することが重要です。まず、債務者は弁護士や司法書士に相談し、個人再生の申立てを行います。裁判所は申立てを受理すると、債権者への通知や債権調査を行います。その後、債務者は再生計画案を作成し、裁判所に提出します。この計画案には、返済額や期間などが含まれます。裁判所は計画案を審査し、認可決定を下します。
認可後は、債務者は計画に沿って返済を行い、通常3年から5年で手続きが完了します。自営業者の場合、事業継続を前提とした計画立案が求められ、売掛金や在庫の扱いにも注意が必要です。手続き中も事業を継続できるため、収入を確保しながら債務整理を進められる点が大きな特徴です。
個人再生の申立てから完了までの手順
個人再生の申立てから完了までの手順は、通常6つの段階を経て進められます。まず、裁判所に個人再生の申立てを行います。この際、債務者の資産状況や収入、負債の詳細な情報を記載した書類を提出する必要があります。次に、裁判所は申立ての内容を審査し、手続開始決定を行います。
この決定後、債権者への通知が行われ、債権の届出期間が設けられます。同時に、債務者は再生計画案を作成し、裁判所に提出します。この計画案には、今後の返済方法や生活再建の見通しなどが含まれます。
その後、債権者集会が開かれ、再生計画案について協議が行われます。債権者の同意が得られれば、裁判所は再生計画を認可します。認可後は、再生計画に基づいて返済を行い、通常3年から5年の返済期間を経て個人再生手続きが完了します。
この過程では、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることが重要です。彼らは複雑な手続きの補助や、再生計画案の作成支援など、円滑な手続きの進行をサポートしてくれます。
必要な書類と注意点
個人再生を申し立てる際には、適切な書類の準備が不可欠です。まず、収入証明書や確定申告書など、収入を証明する書類が必要となります。自営業者の場合、過去3年分の確定申告書や帳簿などが求められることが一般的です。また、債務の状況を示す借入れ一覧表や債権者からの残高証明書も重要な書類です。
資産状況を明らかにするため、不動産登記簿謄本や預金通帳のコピーなども提出が必要です。事業用の資産がある場合は、それらの評価額を示す資料も求められる可能性があります。
注意点としては、提出書類の正確性と網羅性が挙げられます。特に自営業者の場合、事業に関する収支や資産状況を明確に示すことが重要です。不正確な情報や隠蔽は、手続きの遅延や却下につながる可能性があります。
また、個人再生中も事業を継続する場合、事業計画書の提出が求められることがあります。この計画書には、今後の収支見込みや事業継続の見通しを具体的に記載する必要があります。裁判所や債権者を納得させられる内容であることが重要です。
個人再生中も事業を継続するためのポイント

個人再生を選択した自営業者にとって、事業の継続は重要な課題です。まず、事業の収支を明確にし、再生計画に組み込むことが必要です。その際、将来の収益予測を慎重に行い、無理のない返済計画を立てることが重要です。また、取引先との関係維持にも注意を払う必要があります。個人再生中であっても、適切な説明と誠実な対応により、信頼関係を保つことが可能です。
さらに、事業に必要な資産や設備のリース契約については、裁判所の許可を得て継続することができます。これにより、事業の基盤を維持しながら再建を進めることが可能となります。加えて、売掛金の回収や新規の受注にも積極的に取り組み、事業の安定化を図ることが大切です。
最後に、専門家のサポートを有効活用することも重要なポイントです。弁護士や税理士などの助言を得ながら、法的手続きと事業運営の両立を図ることで、個人再生を成功に導くことができるでしょう。
事業を続けながら借金整理を行う方法
自営業者が個人再生を選択する際、事業を継続しながら借金整理を行うことが可能です。この方法では、事業資産を保持しつつ、債務の一部を免除してもらえるため、経営の立て直しに有効です。具体的には、売掛金の回収や既存のリース契約の継続が認められるため、事業の運営に支障をきたすことなく再建を進められます。
ただし、注意すべき点もあります。買掛金の取り扱いには慎重さが求められ、仕入先との関係維持が重要になります。また、個人再生中は新規の与信取引が制限される可能性があるため、事前に取引先との調整が必要です。
事業を継続しながら借金整理を行うためには、適切な再生計画の立案が不可欠です。将来の収支予測を慎重に行い、返済可能な金額を設定することが重要です。また、専門家のアドバイスを受けながら、事業の収益性向上や経費削減などの経営改善策を並行して実施することで、再生の成功率を高めることができます。
売掛金やリース契約の取り扱い
個人再生を行う自営業者にとって、売掛金やリース契約の取り扱いは重要な問題です。売掛金は事業継続に不可欠な資金源であり、適切に管理することが求められます。個人再生手続き中も、通常通り売掛金の回収を行うことができますが、回収した資金は事業の運転資金として使用することが認められています。
一方、リース契約については、個人再生手続きの開始によって自動的に解除されることはありません。ただし、リース料の支払いが困難な場合は、リース会社との交渉により契約の見直しや解約を検討する必要があります。リース契約を継続する場合は、再生計画にその旨を記載し、裁判所の認可を得ることが重要です。
また、個人再生中に新たなリース契約を結ぶ際は、裁判所の許可が必要となる場合があります。これは、過度な債務を負わないようにするための措置です。自営業者は、これらの点に注意しながら、事業の継続と債務の整理のバランスを取ることが求められます。適切な対応により、事業を継続しながら個人再生を成功させることが可能となります。
個人再生で注意すべき「買掛金」や「信用情報」への影響

個人再生を行う際、自営業者は買掛金や信用情報への影響に特に注意を払う必要があります。買掛金は事業継続に不可欠な取引先との関係に直結するため、その取り扱いには慎重さが求められます。個人再生手続きでは、買掛金を優先的に返済することで、取引先との関係維持を図ることが可能です。
一方、信用情報への影響も避けられません。個人再生の申立てにより、信用情報機関に記録が残り、一定期間融資を受けにくくなる可能性があります。この期間は通常5年程度ですが、事業の継続や再建に影響を与える可能性があるため、十分な検討が必要です。適切な対応策を講じることで、これらの影響を最小限に抑えつつ、事業の再生を図ることが重要です。
買掛金が与える手続き上の課題
個人再生において、買掛金は自営業者にとって重要な課題となります。通常の債務とは異なり、買掛金は事業継続に直結する重要な要素であるため、手続き上で特別な配慮が必要です。多くの場合、買掛金は事業に不可欠な仕入先との関係を維持するために優先的に返済する必要があります。
個人再生の手続きでは、買掛金の取り扱いについて慎重に検討する必要があります。裁判所に提出する再生計画案では、買掛金の返済方法や期間を明確に示す必要があります。仕入先との交渉も重要で、個人再生を行うことを説明し、取引継続への理解を求めることが求められます。
また、買掛金の返済が滞ると、仕入先との関係悪化や信用低下につながり、事業継続に支障をきたす可能性があります。そのため、再生計画では買掛金の返済を優先的に組み込み、確実に履行できる内容にすることが重要です。
個人再生中も事業を継続するためには、新規の買掛金を発生させないよう、キャッシュフロー管理を徹底することが不可欠です。これにより、再生計画の実行可能性を高め、事業の存続と債務の整理を両立させることができます。
信用情報への登録とその期間
個人再生を行うと、その情報は信用情報機関に登録されます。この登録は、借り入れや契約に影響を与える可能性があるため、自営業者にとって重要な考慮事項となります。信用情報への登録期間は、個人再生の開始決定から5年間です。この期間中、新規の借り入れや各種契約が困難になる可能性があります。
ただし、個人再生中でも事業継続は可能であり、既存の取引先との関係維持に努めることが重要です。信用情報機関への登録は、あくまで金融機関や大手企業との新規取引に影響を与えるものであり、既存の顧客や小規模な取引先との関係には直接的な影響はありません。
自営業者は、この5年間の信用情報登録期間を、事業の立て直しと財務体質の改善の機会と捉えることが大切です。計画的な返済と堅実な経営を続けることで、信用を回復し、将来的な事業拡大の基盤を築くことができます。個人再生後の信用回復には時間がかかりますが、着実な努力により、再び健全な事業運営が可能となります。
個人再生を成功させるための専門家の選び方

個人再生を成功させるためには、適切な専門家を選ぶことが重要です。自営業者の場合、事業継続と債務整理の両立が求められるため、経験豊富な弁護士や司法書士のサポートが不可欠です。専門家選びの際は、自営業に詳しく、個人再生の実績が豊富な人物を選ぶことがポイントです。また、初回相談時の対応や説明の丁寧さ、費用の透明性なども重要な判断基準となります。さらに、依頼後のフォロー体制や、裁判所との交渉力なども考慮に入れましょう。信頼できる専門家と二人三脚で進めることで、個人再生の成功率は大きく向上します。自営業者特有の課題に対応できる専門家を選ぶことで、事業を継続しながら債務整理を進められる可能性が高まります。
弁護士と司法書士、どちらを選ぶべきか?
個人再生を検討する自営業者にとって、弁護士と司法書士のどちらを選ぶべきかは重要な決断です。両者には専門性や取り扱える業務範囲に違いがあるため、自身の状況に応じて適切な専門家を選ぶことが大切です。
弁護士は法律のエキスパートとして、複雑な案件や訴訟が必要な場合に強みを発揮します。個人再生の申立てから裁判所での手続き、債権者との交渉まで一貫して対応できるため、難しい事案や大型の債務を抱える場合に適しています。
一方、司法書士は主に書類作成や手続き面でのサポートに長けています。比較的シンプルな案件や、債務額が少ない場合には、司法書士でも十分対応可能です。また、弁護士と比べて費用が抑えられる傾向にあります。
選択の際は、自身の債務状況や事業の複雑さ、必要なサポートの範囲を考慮しましょう。また、個人再生の経験が豊富な専門家を選ぶことも重要です。事前の無料相談を活用し、相性や信頼関係を確認した上で依頼先を決めることをおすすめします。
専門家に依頼する際のポイント
個人再生を成功させるためには、適切な専門家のサポートが不可欠です。専門家を選ぶ際は、まず自営業者の個人再生に精通した経験豊富な弁護士や司法書士を探すことが重要です。過去の成功事例や口コミ評価を参考にしつつ、無料相談を活用して相性を確認しましょう。
依頼する際は、自身の財務状況や事業の将来性を正直に伝え、専門家との信頼関係を構築することが大切です。また、個人再生の手続きや影響について丁寧な説明を求め、疑問点は遠慮なく質問することで、より適切なアドバイスを得られます。
費用面では、着手金や報酬額の内訳を明確に確認し、分割払いなどの柔軟な対応が可能かどうかも事前に相談しておくとよいでしょう。さらに、個人再生中や完了後の事業継続に関するサポート体制も重要なポイントです。専門家のアドバイスを受けながら、再建計画を綿密に立てることで、個人再生を成功に導く可能性が高まります。
個人再生後の生活再建に向けたアドバイス

個人再生後の生活再建には、適切な収支管理と前向きな姿勢が不可欠です。まず、収入と支出を細かく把握し、無駄な出費を削減することが重要です。固定費の見直しや節約習慣の確立により、安定した家計を維持しましょう。また、貯蓄の習慣を身につけ、将来の不測の事態に備えることも大切です。
同時に、過去の経験を教訓として、健全な財務管理の重要性を再認識することが求められます。債務の返済を確実に行いながら、事業の成長や新たな収入源の開拓にも目を向けましょう。
さらに、心理面でのケアも忘れずに。失敗を恐れず、前向きな姿勢で新たな挑戦に臨むことが、持続可能な生活再建につながります。家族や周囲の支援者との良好な関係を築き、精神的な支えを得ることも大切です。これらの取り組みを通じて、着実に生活を立て直し、より安定した将来を築いていくことができるでしょう。
債務整理後の収入と支出の管理
個人再生を成功させた後は、収入と支出の適切な管理が生活再建の鍵となります。まず、収入面では事業の安定化と拡大に注力し、計画的な売上目標を設定することが重要です。一方で、支出については優先順位を明確にし、不要な経費を削減する努力が求められます。特に自営業者の場合、事業費と生活費の区別を明確にし、それぞれの予算管理を徹底することが大切です。
また、再発防止のため、緊急時の備えとして貯蓄習慣を身につけることも重要です。月々の収支を細かく記録し、定期的に見直すことで、無駄な出費を抑え、安定した資金繰りを維持できます。さらに、クレジットカードの使用を控え、現金主義の生活を心がけることで、過剰な借入れを避けることができます。
これらの取り組みを通じて、健全な財務状況を維持し、事業と生活の両立を図ることが可能となります。個人再生後の生活再建は、単なる借金返済にとどまらず、長期的な視点での経済的自立を目指す過程であることを忘れてはいけません。
生活再建のためのマインドセット
個人再生を経験した自営業者にとって、生活再建は新たな出発点となります。この過程で重要なのは、適切なマインドセットを持つことです。まず、過去の失敗を反省しつつも、それに囚われすぎないことが大切です。むしろ、この経験を貴重な学びの機会と捉え、今後の事業運営に活かす姿勢が求められます。
同時に、計画性と規律を持って財務管理に取り組む必要があります。収支のバランスを常に意識し、無理のない範囲で事業を展開することが重要です。また、緊急時に備えた資金の確保や、将来の投資に向けた計画的な貯蓄も心がけましょう。
さらに、自己啓発や業界動向の把握にも注力し、自身のスキルや知識を常にアップデートすることが大切です。これにより、ビジネスチャンスを逃さず、安定した収入を確保する可能性が高まります。
最後に、周囲のサポートを大切にし、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることも重要です。一人で抱え込まず、適切な支援を受けながら、着実に生活再建を進めていくことが成功への近道となるでしょう。
まとめ:個人再生が個人事業主に適している理由とその利点

個人事業主が抱える借金問題は、会社員や法人とは異なる特徴があります。特に、事業資金や生活費が一体化しているため、返済が難しくなるケースが多いです。このような場合、個人再生は借金を大幅に減額し、事業を継続しながら弁済計画を立てることが可能な有効な手段です。
個人再生では、借金総額の一部を免除してもらいながら、残った金額を返済する仕組みです。過払い金が発生している場合は、それを請求して返済額をさらに減額できる可能性もあります。個人事業主にとって、事業用資産を手放さずに済む点が特に大きなメリットです。これにより、事業再建と借金整理を同時に進めることができます。
また、個人再生では自己破産とは異なり、住宅ローン特則を利用すれば、自宅や車を失わずに済む場合もあります。さらに、任意整理と比較しても、返済額が減額される割合が大きく、総額の負担を軽減できる可能性が高いです。
ただし、個人再生には一定の条件があります。たとえば、最低限の収入が必要であり、給与所得が安定していることが望ましいです。また、弁済計画が認められなければ破産手続きに移行するリスクもあります。そのため、事前に専門家に相談し、個人再生が自分に適しているかどうかを判断することが重要です。
個人再生を行うことで、ブラックリストに登録される期間はありますが、取引先との関係が維持しやすい点や、事業に専念できる環境を整えられる点が魅力です。今、借金問題を抱えているなら、気軽に専門家へ相談し、自身にとって良い選択肢を見つけることが重要です。
この記事の監修者
株式会社WEBYの債務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に債務整理の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
この記事に関係するよくある質問
- 個人再生は不公平なのでしょうか?
- 個人再生は、債務を最大で5分の1まで減額できる手続きです。ただし、場合によっては必ずしも5分の1になるわけではありません。清算価値保障原則というルールにより、所有している財産の価値以上を返済する必要があります。このルールは、自己破産を回避して個人再生を選ぶことが「不公平」と見なされないために設けられています。
- 個人再生で失うものは何ですか?
- 個人再生を利用しても、原則として財産を失うことはありません。ただし、借金を大幅に減らすことができる一方で、自分が所有している全財産の価値より多く減額することはできません。そのため、最低でも財産の総額に相当する金額を、3~5年の期間をかけて返済する必要があります。
- 個人再生の成功率は?
- 個人再生を考える方の多くは、司法書士や弁護士に依頼して手続きを進めます。そのため、「手続きが失敗して費用が無駄になるのではないか」と不安になることもあるでしょう。しかし、ご安心ください。個人再生の成功率は約93%と非常に高く、多くの方がこの手続きを成功させています。専門家のサポートを受けることで、さらに安心して進めることが可能です。
- 個人再生は何年で消えますか?
- 個人再生の手続きにかかる期間は、1年から1年半ほどです。その後、再生計画の認可決定に従い、原則3年間で返済を完了します。さらに、手続き開始から5〜10年で信用情報機関の事故情報が削除され、生活への影響がほとんどなくなります。万が一、個人再生後に返済が難しくなった場合でも、適切な対処法を取ることで解決の道を探ることが可能です。
- 個人再生が失敗したらどうなる?
- 個人再生に失敗すると、借金の減額はされず、遅延損害金が加算された金額を一括で請求される可能性があります。その額を支払えない場合、債権者から裁判を起こされるリスクがあります。さらに、裁判の結果として給与や財産の差押えを受ける可能性もあるため、個人再生の手続きは慎重に進める必要があります。専門家のサポートを受けることで失敗のリスクを減らせます。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。