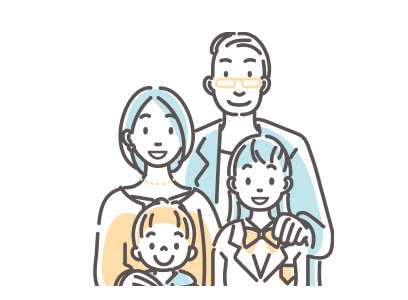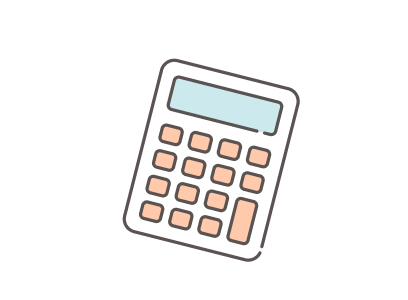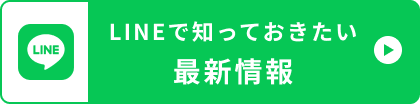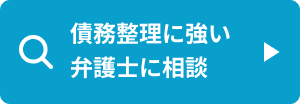休眠会社のメリット・デメリットを解説!?手続きや注意点も完全網羅
代表破産・倒産
2025.04.17 ー 2025.12.10 更新
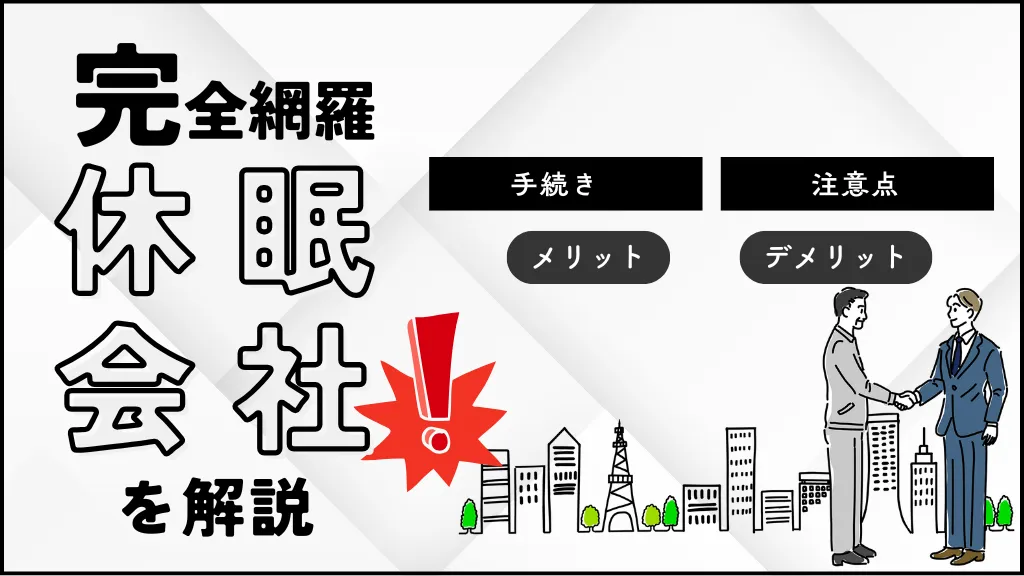
事業活動を一時的に停止しながら法人格を維持する「休眠会社」は、経営者にとって柔軟な選択肢の一つです。本記事では、休眠会社の概要や手続きの流れについて詳しく紹介します。休眠会社は将来的な事業再開や事業譲渡を視野に入れた経営判断として注目される一方、法的な義務や費用負担が伴います。
以下に、その具体的な仕組みや注意点を解説し、休眠会社を活用する際のポイントを明確にします。この記事を通じて、休眠会社の実態と利点を把握し、適切な経営戦略を見つけましょう。
こんな人におすすめの記事です。
- 事業活動を一時停止しつつ、法人格を維持したい中小企業の経営者
- 将来的な事業再開や事業譲渡を視野に入れている企業オーナー
- 休眠会社の手続きや法的義務について正確な情報を知りたい個人や法人
記事をナナメ読み
- 休眠会社は法人格を維持しながら将来的な事業再開や譲渡の可能性を残せる有効な経営戦略
- 手続きや法的義務を正確に理解し、適切に管理することで、リスクを抑えつつ会社の価値を維持できる
- 専門家の助言を活用することで、効率的かつ確実に手続きを進めることが可能
休眠会社とは?その定義と背景

休眠会社とは、事業活動を一時的に停止している法人のことを指します。通常の会社と異なり、営業や収益活動を行っていませんが、法人格は維持されている状態です。この状態は、経済情勢の変化や事業戦略の見直しなど、様々な理由で生じることがあります。
休眠会社が生まれる背景には、事業の一時的な中断や将来の再開を見据えた戦略的な判断があります。例えば、市場環境の悪化により一時的に事業を停止する場合や、新規事業への参入準備期間として会社を休眠状態にすることがあります。
また、企業グループ内での組織再編や、事業承継の準備期間として休眠状態を選択することもあります。休眠会社は、完全な廃業とは異なり、将来的な事業再開の可能性を残しつつ、一時的に活動を停止する選択肢として活用されています。
休眠会社の定義
休眠会社とは、法人格を維持しながら実質的な事業活動を停止している会社のことを指します。具体的には、営業や製造などの事業を行わず、収益を上げる活動を一時的に休止している状態を指します。ただし、完全に解散や清算をしているわけではなく、法人としての登記は存続しています。
休眠会社は、事業の縮小や一時的な停止、将来の再開を見据えた待機状態など、様々な理由で生まれます。この状態では、役員や株主は存在し続けますが、従業員は通常解雇されています。また、事務所や工場などの実体を持たないケースが多く、登記上の本店所在地のみが存在する形態をとることが一般的です。休眠会社は法的には通常の会社と同様に扱われるため、最低限の維持管理や税務申告などの義務は継続して果たす必要があります。
休眠会社が生まれる背景
休眠会社が生まれる背景には、経済環境の変化や事業戦略の転換が大きく関わっています。景気の低迷や業界の構造変化により、一時的に事業活動を停止せざるを得ない状況に陥ることがあります。また、新規事業への参入や海外展開を検討する際、将来的な再開の可能性を残すために会社を休眠状態にすることもあります。
企業の合併や買収に伴い、不要となった子会社や関連会社を休眠させるケースも少なくありません。これは、将来的な事業再編や資産管理の観点から戦略的に選択されることがあります。
さらに、創業者の高齢化や後継者不在といった問題に直面した中小企業が、廃業を避けて休眠状態を選択するケースも増えています。これにより、将来的な事業承継や再開の可能性を残すことができます。
税制面での優遇措置を活用するために、意図的に休眠状態を選択する企業もあります。特定の条件下では、休眠会社に対する課税が軽減されることがあるため、節税対策の一環として利用されることがあります。
休眠会社のメリット5選

休眠会社には、事業再開時の利点や経済的なメリットがいくつか存在します。まず、事業活動を再開する際に手続きが比較的容易であり、新規設立と比べて時間と労力を節約できます。また、既存の許認可を維持できるため、再取得の手間が省けます。
さらに、一定の条件を満たせば法人税や消費税の課税対象外となる可能性があり、税負担を軽減できます。廃業と比較しても、休眠会社化は費用や時間を抑えられるため、将来の事業再開の選択肢を残せます。加えて、適切な管理を行えば節税効果が得られる可能性もあります。これらのメリットにより、企業は将来の事業展開の柔軟性を保ちつつ、経済的な負担を軽減することができます。
事業活動を再開しやすい
休眠会社の大きな利点の一つは、事業活動を再開しやすいことです。一度休眠状態に入っても、適切な手続きを踏めば比較的容易に事業を再開できます。これは、会社の法人格が維持されているためです。休眠期間中も登記上は存続しているため、新たに会社を設立する手間が省けます。また、取引先との関係や信用も継続されやすく、再開時のスムーズな事業展開が期待できます。
さらに、休眠前に取得していた許認可や契約関係も多くの場合そのまま利用可能です。これにより、再開時の手続きや準備にかかる時間とコストを大幅に削減できます。ただし、休眠期間が長期に及ぶ場合は、法令や市場環境の変化に注意が必要です。再開時には、最新の規制や業界動向を確認し、必要に応じて体制を整えることが重要です。このように、休眠会社は将来の事業再開の選択肢を残しつつ、一時的に活動を停止できる柔軟な仕組みといえます。
許認可の再取得が不要
休眠会社の大きなメリットの一つは、許認可の再取得が不要な点です。事業を一時的に休止しても、会社の法人格が維持されるため、以前に取得した許認可や資格を失効せずに保持できます。これは特に建設業や不動産業、飲食業など、事業再開時に新たな許認可取得が必要となる業種において非常に有利です。例えば、建設業許可や宅地建物取引業免許などは、取得に時間とコストがかかりますが、休眠状態でもこれらを維持できるのです。また、取引先との契約や銀行口座なども、そのまま引き継ぐことができるため、事業再開時のスムーズな立ち上げが可能となります。
さらに、業界によっては長年の実績や信用が重要視される場合もあり、休眠状態を経ても設立年数を維持できることは大きな利点となります。このように、許認可の再取得が不要であることは、将来的な事業再開の可能性を残しつつ、柔軟な経営判断を可能にする休眠会社の重要なメリットの一つと言えるでしょう。
法人税・消費税の課税が無い場合がある
休眠会社は、事業活動を停止していることから、一定の条件を満たせば法人税や消費税の課税が免除される場合があります。法人税については、所得がない場合や欠損金の繰越控除により課税所得が生じない場合、納税義務が発生しません。消費税に関しても、課税売上高が1000万円以下の事業者は免税事業者となるため、休眠状態で売上がなければ課税対象外となります。
ただし、固定資産を保有している場合は固定資産税が課税される可能性があるため注意が必要です。また、休眠期間中も法人格は存続しているため、資本金に応じた最低税額の納付が必要な場合もあります。
休眠会社の税務上のメリットを活用するには、適切な会計処理と税務申告が不可欠です。所得がないことや資産状況を正確に把握し、必要な書類を提出することで、税負担を軽減できる可能性があります。ただし、税法は複雑で頻繁に改正されるため、専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。
廃業より費用や時間を抑えられる
休眠会社を選択する大きな利点の一つは、廃業と比較して費用と時間を大幅に抑えられることです。廃業手続きには多くの書類作成や清算手続きが必要となり、時間と労力がかかります。また、弁護士や税理士などの専門家に依頼する場合、高額な費用が発生することもあります。一方、休眠会社化では、事業活動の停止を届け出るだけで済むため、手続きが比較的簡単です。
さらに、将来的に事業を再開する可能性がある場合、休眠会社を選択することで再起業にかかる時間と費用を節約できます。新たに会社を設立する場合と比べ、既存の法人格を利用できるため、各種許認可の再取得や取引先との関係構築などにかかる手間を省くことができます。
また、休眠期間中も法人格が維持されるため、ブランド価値や信用力を保持できるメリットもあります。これは、将来的な事業再開や会社売却を考えている場合に特に重要となります。
以上のように、休眠会社化は廃業と比較して、時間的・金銭的コストを抑えつつ、将来の選択肢を残せる柔軟な対応策といえます。
節税につながる可能性がある
休眠会社は、節税の観点からも注目されています。事業活動を停止していても法人格を維持することで、将来的な税務上のメリットを得られる可能性があるのです。例えば、過去の欠損金を繰り越して、将来の事業再開時に課税所得から控除できる場合があります。これにより、再開後の法人税負担を軽減できる可能性が生まれます。
また、休眠期間中は収益がないため、法人税や消費税の課税対象とならないケースが多く、税負担を抑えられます。さらに、休眠状態を維持することで、将来的に有利な税制改正や優遇措置が導入された際に、迅速に対応できるという利点もあります。
ただし、休眠会社の節税効果を最大限に活用するには、適切な税務申告と会計処理が不可欠です。税理士や会計士などの専門家に相談し、法令遵守を徹底しながら、最適な税務戦略を立てることが重要です。休眠会社の活用は、将来の事業展開を見据えた長期的な視点での節税対策として有効な選択肢となり得るでしょう。
休眠会社のデメリット5選

休眠会社には、事業再開の容易さや許認可の維持といったメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。まず、毎年の税務申告が必要となり、事業活動がなくても手続きの手間がかかります。また、休眠状態を維持するための費用が発生し、会社の財務を圧迫する可能性があります。
役員に変更があった場合は、登記手続きが必要となり、追加の費用と時間がかかります。さらに、長期間活動を行わない場合、みなし解散のリスクが高まり、法人格を失う可能性があります。最後に、保有する固定資産に対して課税される場合があり、予期せぬ税負担が生じる可能性があります。これらのデメリットを十分に理解し、休眠会社の維持が本当に最適な選択肢なのか慎重に検討する必要があります。
毎年税務申告が必要
休眠会社であっても、法人格は存続しているため、毎年の税務申告は欠かせません。具体的には、法人税、地方法人税、法人住民税、事業税などの申告が必要となります。たとえ収益がなくても、これらの申告を怠ると、加算税や延滞税が課される可能性があります。また、消費税の課税事業者である場合は、消費税の申告も必要です。
税務申告を行う際は、休眠状態であることを明確に示すため、収益事業開始届出書を提出し、休眠中であることを税務署に伝えることが重要です。これにより、税務調査のリスクを軽減できる可能性があります。
さらに、法人税の確定申告書には、休眠中である旨を記載することが望ましいです。これにより、税務署側も休眠状態を理解し、適切な対応をとることができます。
休眠会社の税務申告は、専門知識が必要な場合が多いため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。適切な税務申告を行うことで、将来的な事業再開時のトラブルを防ぐことができます。
休眠維持費用がかかる
休眠会社を維持するには、一定の費用が発生します。まず、法人登記を維持するための年間登録免許税が必要です。また、税務申告を行うための税理士費用も考慮しなければなりません。さらに、法人口座の維持費や、最低限の事務所経費なども発生する可能性があります。
休眠状態であっても、会社の存続には役員が必要です。役員報酬を支払わない場合でも、役員の社会保険料の負担が生じることがあります。また、会社所有の資産がある場合は、固定資産税などの税金も継続して支払う必要があります。
これらの費用は、会社の規模や状況によって異なりますが、年間数万円から数十万円程度かかることが一般的です。休眠会社を維持するメリットと比較して、これらの費用が見合うかどうかを慎重に検討する必要があります。長期的な視点で、将来の事業再開の可能性や、許認可の維持の重要性などを考慮し、休眠維持の是非を判断することが重要です。
役員変更登記の必要性
休眠会社においても、役員変更登記は法律で定められた重要な手続きです。会社法上、役員の任期満了や辞任、新たな役員の選任があった場合、2週間以内に登記する必要があります。これは、休眠状態であっても変わりません。役員変更登記を怠ると、過料の対象となる可能性があるため注意が必要です。
また、役員変更登記は会社の信用維持にも関わります。取引先や金融機関、行政機関などが会社の状況を確認する際、登記情報は重要な判断材料となります。適切に更新されていない登記は、会社の信頼性に疑問を投げかける可能性があります。
さらに、将来的に事業を再開する際にも、最新の役員情報が登記されていることは重要です。スムーズな事業再開のためにも、休眠期間中も役員変更登記を適切に行うことが推奨されます。
休眠会社の管理者は、これらの点を踏まえ、役員の変更があった際には速やかに登記手続きを行うよう心がけましょう。適切な登記管理は、休眠会社の健全性を維持する上で欠かせない要素です。
みなし解散のリスク
休眠会社を長期間放置すると、みなし解散のリスクが高まります。これは、法人登記簿に記載された本店所在地に会社が存在しない状態が継続した場合に適用される措置です。具体的には、登記所から通知を受けてから2か月以内に法人の所在を証明できない場合、会社は解散したものとみなされます。
このリスクを回避するためには、定期的に登記事項を確認し、必要に応じて変更手続きを行うことが重要です。また、法人税の確定申告書を3年以上提出していない場合も、みなし解散の対象となる可能性があります。休眠会社を維持する場合は、最低限の事務処理を継続し、法的義務を果たすことが不可欠です。みなし解散となると、会社の財産は国庫に帰属し、再開業が困難になるため、十分な注意が必要です。
固定資産税などが課税される場合がある
休眠会社であっても、固定資産を所有している場合は固定資産税が課税される可能性があります。これは、事業活動の有無に関わらず、資産の所有者に対して課される税金だからです。例えば、休眠状態にある会社が土地や建物を所有していれば、毎年固定資産税を納付する義務が生じます。また、自動車税や軽自動車税についても同様で、会社名義の車両を保有している場合は課税対象となります。
さらに、法人住民税の均等割についても、資本金や従業員数によっては課税される場合があります。これらの税金は、休眠状態であっても会社が存続している限り発生し続けるため、長期的な休眠状態を維持する場合は、これらの税負担を考慮に入れる必要があります。休眠会社の維持にかかるコストを最小限に抑えるためには、不要な資産の処分や、課税対象となる資産の見直しを検討することが重要です。
休眠会社化の手続きの流れ

休眠会社化の手続きは比較的シンプルで、主に事業活動の停止と必要な届出から成り立ちます。まず、会社の事業活動を実質的に停止し、従業員を解雇または転籍させます。次に、税務署や都道府県税事務所に休業届を提出します。この際、法人税や消費税の申告も忘れずに行います。
また、銀行口座や取引先との契約の整理も必要です。ただし、会社の登記は抹消せず、最低限の維持を続けます。役員変更や本店所在地の変更などの登記事項に変更がある場合は、法務局への変更登記も必要になります。
休眠会社化の手続きにかかる費用は、主に書類作成や提出にかかる手数料、場合によっては専門家への相談料などです。これらの手続きを適切に行うことで、将来の事業再開の可能性を残しつつ、会社を休眠状態に移行させることができます。
必要な書類と手続き内容
休眠会社化の手続きでは、まず目的を明確にし、商号や登録住所などの情報を確認します。その後、商業登記に必要な書類を準備します。事業内容の廃止や変更がある場合、それを反映させる作業も必要です。また、厚生年金保険や税務申告の登録情報も整理しておきます。
手続きは株主総会での決議を経て法務局へ届け出を行う形で進みます。この際、清算人の選任や任期の議決が求められることがあります。さらに、官報公告によって会社が休眠状態に入る旨を公表する必要があります。これにより、倒産や消滅とは異なる「休眠」という制度上の違いを明示できます。
手続きの経過で課題が発生した場合、司法書士などの専門家による支援が役立ちます。法律上の説明や実施方法の案内を受けることで、作業が効率化します。また、最長数年間の休眠期間中も必要に応じて手続きを実施する必要があり、いずれ再開を予定している場合は上記の支援が重要です。
手続きにかかる費用
休眠会社化の手続きにかかる費用は、主に登記費用と税理士への依頼費用が中心となります。登記費用は、休眠会社化に伴う変更登記の際に発生し、通常1万円から2万円程度です。ただし、登記内容の複雑さによって多少の変動があります。税理士への依頼費用は、休眠会社化の手続きや税務申告の代行を依頼する場合に必要となり、一般的に5万円から15万円程度です。この費用は税理士事務所によって異なるため、事前に複数の事務所に相談して見積もりを取ることをおすすめします。
また、休眠会社を維持するための年間費用も考慮する必要があります。これには、毎年の税務申告費用や登記費用が含まれ、通常5万円から10万円程度かかります。さらに、会社の状況によっては、最低限の経費や固定資産税などの諸税が発生する可能性もあります。
休眠会社化の費用は、通常の会社解散や清算手続きと比較すると低く抑えられますが、長期間維持する場合は累積的なコストを考慮することが重要です。会社の状況や将来的な事業再開の可能性を踏まえて、費用対効果を慎重に検討することが賢明です。
休眠から復活させる手続き

休眠会社を復活させる際には、まず株主総会を開催し、事業再開の決議を行う必要があります。その後、登記申請を行い、法務局に事業再開の旨を届け出ます。また、税務署や社会保険事務所にも再開の報告をしなければなりません。復活手続きの際には、定款や株主名簿の確認、役員の選任なども必要となるでしょう。
復活にかかる費用は、登記申請料や書類作成費用など、数万円から十数万円程度が一般的です。ただし、長期間休眠状態だった場合や、複雑な手続きが必要な場合は、さらに費用がかかる可能性があります。
税務面では、事業再開後の収益に応じて法人税や消費税の納税義務が発生します。また、休眠期間中の未払い税金がある場合は、それらの清算も必要となるでしょう。適切な手続きを踏むことで、スムーズな事業再開が可能となります。
復活手続きの流れ
休眠会社を復活させる手続きは、比較的シンプルな流れで進めることができます。まず、取締役会を開催し、事業再開の決議を行います。次に、法務局に対して代表取締役の就任登記を申請します。この際、就任承諾書や印鑑証明書などの必要書類を準備する必要があります。続いて、税務署や都道府県税事務所に対して、開業届や異動届などを提出します。これにより、税務上の手続きが完了します。
さらに、事業再開に伴い、必要に応じて各種許認可の再取得や更新を行います。例えば、建設業や不動産業などの場合、業界固有の許可が必要となることがあります。また、従業員を雇用する場合は、労働保険や社会保険の手続きも忘れずに行いましょう。
最後に、取引銀行に対して、休眠状態から復帰した旨を通知し、必要に応じて口座の再開や新規開設を行います。これらの手続きを適切に進めることで、休眠会社を円滑に復活させ、事業を再開することができます。
復活時に発生する費用
休眠会社を復活させる際には、いくつかの費用が発生します。まず、登記費用が必要となります。これには、法務局に提出する復活登記申請の手数料や、登録免許税が含まれます。また、定款の変更が必要な場合は、公証人役場での認証手数料も発生します。
次に、会計・税務関連の費用があります。休眠期間中の決算書や税務申告書の作成、滞納していた法人税や消費税の納付などが必要になる可能性があります。これらの処理には、税理士や会計士への報酬が発生することもあります。
さらに、事業再開に伴う諸経費も考慮する必要があります。例えば、オフィスの賃貸料、従業員の給与、必要な設備や備品の購入費用などです。また、事業によっては、許認可の更新料や保険料なども発生する可能性があります。
最後に、休眠期間中に発生した未払い費用の清算も必要です。例えば、未払いの社会保険料や年金保険料、固定資産税などがある場合は、これらを支払う必要があります。これらの費用は、休眠期間の長さや会社の状況によって大きく異なるため、事前に専門家に相談し、適切な見積もりを行うことが重要です。
税務申告における注意点

休眠会社であっても、毎年の税務申告は欠かせません。法人税や消費税の申告が必要となりますが、事業活動がない場合は「零申告」となることが多いでしょう。ただし、固定資産税や法人住民税などは課税される可能性があるため、注意が必要です。税務署への届け出では、休眠状態であることを明確に伝え、適切な処理を行うことが重要です。
また、休眠期間中に役員変更があった場合は、登記変更を忘れずに行いましょう。税務申告を怠ると、みなし解散のリスクが高まるだけでなく、将来的な事業再開時に問題が生じる可能性があります。休眠会社の税務管理は、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることをおすすめします。
毎年必要な税務申告とは
休眠会社であっても、毎年の税務申告は欠かせません。法人税や消費税の申告が主な対象となりますが、収益がない場合でも「零申告」を行う必要があります。法人税の場合、事業年度終了後2ヶ月以内に申告書を提出しなければなりません。消費税については、課税事業者であれば年1回の申告が求められます。これらの申告を怠ると、加算税や延滞税が課される可能性があるため注意が必要です。
また、休眠状態であっても法人住民税の均等割は課税されるため、自治体への申告も忘れてはいけません。さらに、源泉所得税の納付義務がある場合は、毎月または半年ごとの納付と年末調整も必要となります。これらの税務申告を適切に行うことで、休眠会社の法的義務を果たし、将来的な事業再開や清算の際のトラブルを回避することができます。
税務署への届け出のポイント
休眠会社の税務申告において、税務署への適切な届け出は非常に重要です。まず、法人税の確定申告書を毎年提出する必要があります。事業活動を行っていなくても、収益がゼロであることを報告しなければなりません。また、消費税の申告も必要となる場合があります。特に、休眠前に課税事業者だった場合は注意が必要です。
さらに、法人住民税の申告も忘れてはいけません。自治体によって手続きが異なる場合があるため、所在地の自治体に確認することをおすすめします。休眠状態であっても、固定資産を所有している場合は固定資産税の申告も必要です。
休眠会社の状態に変更した際には、異動届出書を税務署に提出することが大切です。これにより、税務署側で休眠状態であることを把握し、不要な調査や連絡を避けることができます。また、役員変更や本店所在地の変更があった場合も、速やかに届け出る必要があります。
最後に、休眠状態が長期化する場合は、定期的に税務署とコミュニケーションを取ることをおすすめします。これにより、法令の変更や新たな手続きの必要性などの情報を適時に入手できます。
休眠会社を放置した場合のリスク

休眠会社を放置すると、様々なリスクが生じる可能性があります。最も重大なのは、みなし解散となるリスクです。法人税の申告を12年間行わないと、税務署によって強制的に解散させられる可能性があります。また、法人登記の住所変更や役員変更などの手続きを怠ると、登記上の義務を果たしていないとみなされ、法的な問題に発展する恐れがあります。さらに、休眠状態が長期化すると、取引先や金融機関からの信用が低下し、将来的な事業再開や融資の際に支障をきたす可能性があります。これらのリスクを回避するためには、適切な管理と定期的な手続きが不可欠です。休眠会社を放置せず、適切に対応することで、将来の事業再開や円滑な会社運営につながります。
みなし解散となる可能性
休眠会社を長期間放置すると、みなし解散となるリスクが高まります。会社法の規定により、12年以上にわたり事業報告書等を提出していない場合、裁判所による解散命令の対象となります。この期間は、最後に登記した日から起算されます。みなし解散となると、会社の法人格が失われ、再開業が困難になります。
また、清算手続きが必要となり、予期せぬ費用や手間が発生する可能性があります。さらに、休眠状態が長期化すると、取引先や金融機関からの信用低下につながる恐れもあります。このため、休眠会社を維持する場合は、定期的な登記や税務申告を怠らず、法令遵守を心がけることが重要です。将来的な事業再開の可能性を残すためにも、みなし解散を回避する適切な対応が求められます。
社会的信用の低下
休眠会社は、事業活動を停止しているにもかかわらず法人格を維持しているため、社会的信用の低下を招く可能性があります。取引先や金融機関、投資家などのステークホルダーは、休眠状態の企業に対して不信感を抱きやすく、将来的な事業再開や新規事業展開の際に障害となることがあります。また、休眠期間が長期化すると、企業としての存在意義や社会的責任が問われる可能性も高まります。
さらに、休眠会社の存在は、経済の健全性や透明性を損なう要因となり得るため、行政機関や監督当局からの scrutiny が強まる可能性もあります。このような社会的信用の低下は、企業価値の毀損につながり、再起を図る際の大きな障壁となる可能性があるため、休眠会社の維持には慎重な判断が求められます。
まとめ:将来を見据えた休眠会社という経営戦略

休眠会社とは、事業活動を停止している株式会社でありながら、法人格を維持している状態を指します。このような会社は、法務局での登記が存続しているため、法務大臣の管理下で必要な公告を官報に出す義務があります。休眠会社化は、何らかの理由で事業活動を一時停止し、将来の再開や事業譲渡を見据えた経営判断として選択されることがあります。
手続きの流れとしては、まず取締役会で休眠状態に移行する決議を行い、その後、管轄の法務局に必要な資料を提出します。この際、株式や不動産の譲渡が含まれる場合は、それぞれの手続きが必要となります。また、決算や確定申告も継続して行う必要があり、経営者はこれらの法的義務を怠ると、罰則が課される可能性があります。
休眠状態以降も、最低限の維持費用がかかるため、会社の種類や状況に応じた管理が求められます。また、事業譲渡を目的としている場合は、登記上の事項を適切に更新し、取引先や一般からの信頼を損なわないよう注意が必要です。事務所の所在地や取締役の変更がある場合も、速やかに届け出を出すことが求められます。
休眠会社は、将来的な事業再開の可能性を残しつつ、コストを抑えられる無料または低コストの経営戦略の一環として活用できます。ただし、法律上の義務や手続きの漏れを防ぐため、専門家の助言を受けることが推奨されます。これにより、会社の価値を維持しつつ、柔軟な経営判断が可能となります。
この記事の監修者
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。 当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
この記事に関係するよくある質問
- 休眠会社にするとどうなりますか?
- 休眠会社(休業)とは、法人としての事業活動を一時的に停止することを指します。この場合、活動は停止しますが、会社自体は消滅せずに存続します。一方、事業活動を完全に停止し、会社が消滅する場合は「廃業」となります。
- 休眠会社は何年で消滅しますか?
- 最後の登記から12年を経過している株式会社(休眠会社)や、最後の登記から5年を経過している一般社団法人や一般財団法人(休眠一般法人)は、事業を継続している場合、「まだ事業を廃止していない」という旨の届出が必要です。届出が行われない場合、法律に基づき解散したものとみなされ、法人格を失うことになります。
- 休眠会社にする理由は何ですか?
- 休眠状態にすることで、運営コストを抑えたり、特定の税金が免除される場合があります。その結果、法人を存続させながら最小限のコストで維持することが可能です。これにより、経営を一時的に中断したい状況や将来の再開を見据えた場合に活用されることが多いです。
- 休眠会社を復活させるにはどうしたらいいですか?
- 事業を再開する際は、税務署や都道府県税事務所、本店所在地の自治体の役場に再開届(異動届出書)を提出するだけで、手続きは比較的簡単です。また、休眠会社は法人格が存続しているため、これまでの人脈やブランドを引き続き活用しやすいという利点があります。
- 休眠会社は確定申告をしなくていいですか?
- 休眠会社であっても、税務申告は義務付けられており、通常の株式会社と同様に決算期ごとに申告する必要があります。休眠会社は事業活動を停止しているものの、法人格が存続している会社を指します。そのため、法律に基づき必要な手続きを継続する義務があります。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。