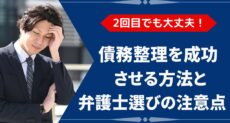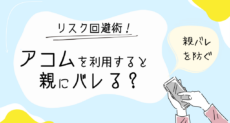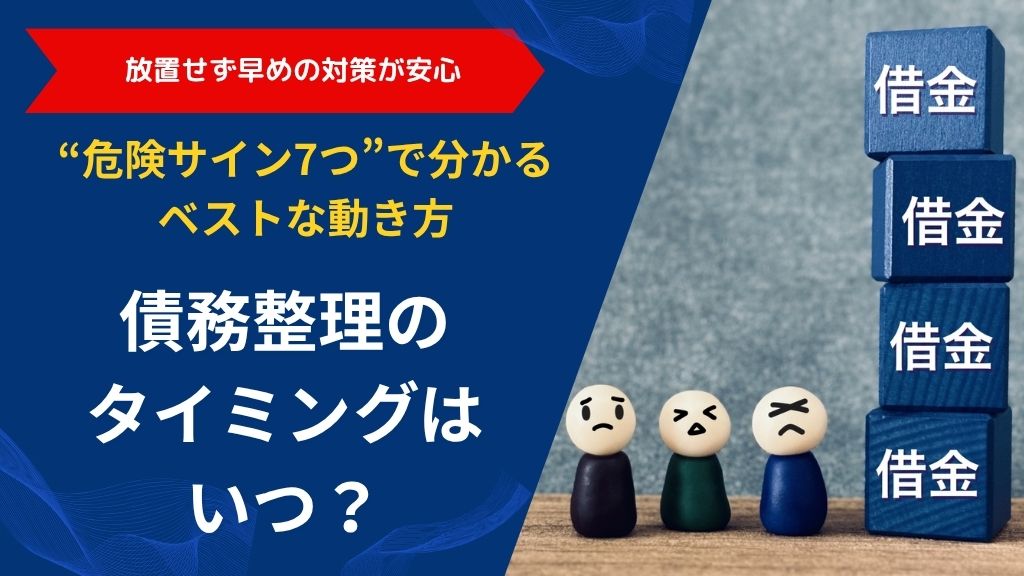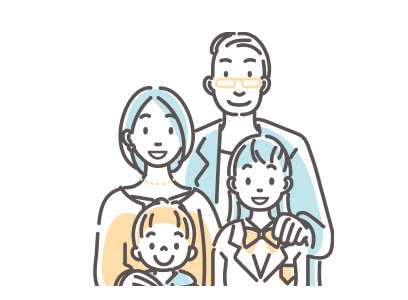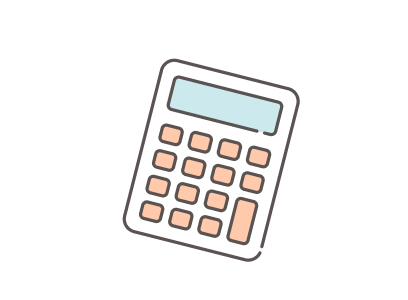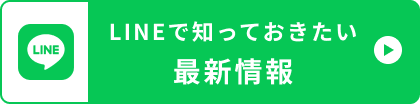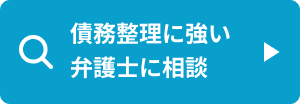自己破産の流れを9ステップで解説|手続きの仕組み・費用・注意点まで完全ガイド
自己破産
【実績多数!】くすの木総合法務事務所
2024.04.05 ー 2025.12.10 更新
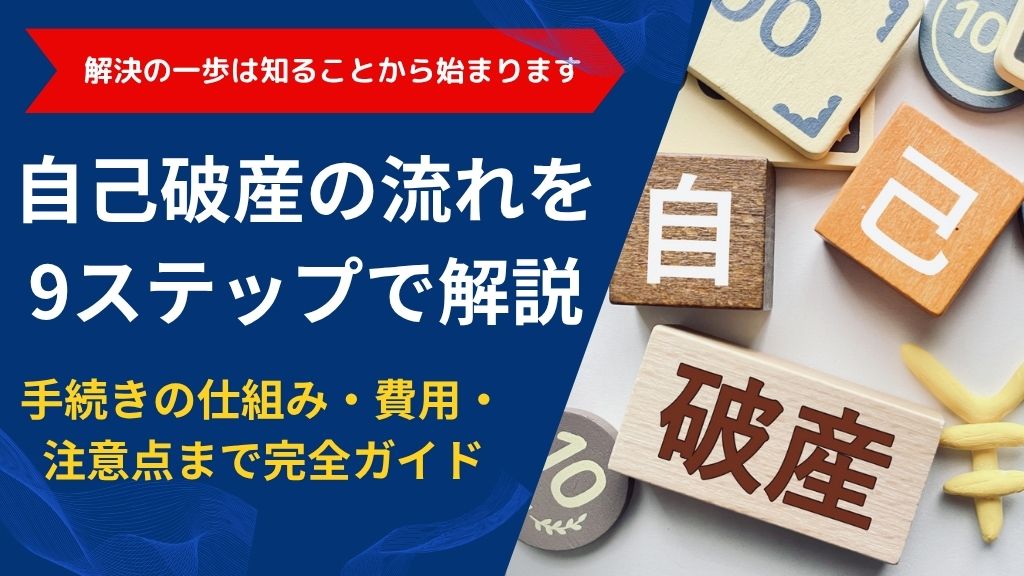
借金の返済に行き詰まり、自己破産を考えているけれど、「手続きがよくわからない……」と悩んでいませんか。自己破産は、経済的に困窮した方を救済し、生活を立て直すために法律で定められた制度です。
この記事では、自己破産の手続きの流れを1〜9のステップでわかりやすく解説します。さらに、手続きにかかる期間や費用の目安、手続き中に絶対に避けるべき行為についてもまとめています。
まずは自己破産とはどのような制度で、手続きがどのような流れで進んでいくのかを見ていきましょう。
こんな人におすすめの記事です。
- 毎月の返済に追われ、もう限界だと感じている方
- 自己破産を考えているけれど、手続きの流れがよくわからず、不安に感じている方
- 借金問題を弁護士に相談した方がいいのか迷っている方
記事をナナメ読み
- 自己破産の仕組みや種類、他の債務整理手続きとの違いをわかりやすく解説
- 自己破産手続きの具体的な流れを9ステップで確認できる
- 手続きの期間や費用の目安、注意すべき行動も紹介
- 専門家に依頼するメリットや選び方がわかる
自己破産とは?手続きの基本的な仕組みと特徴
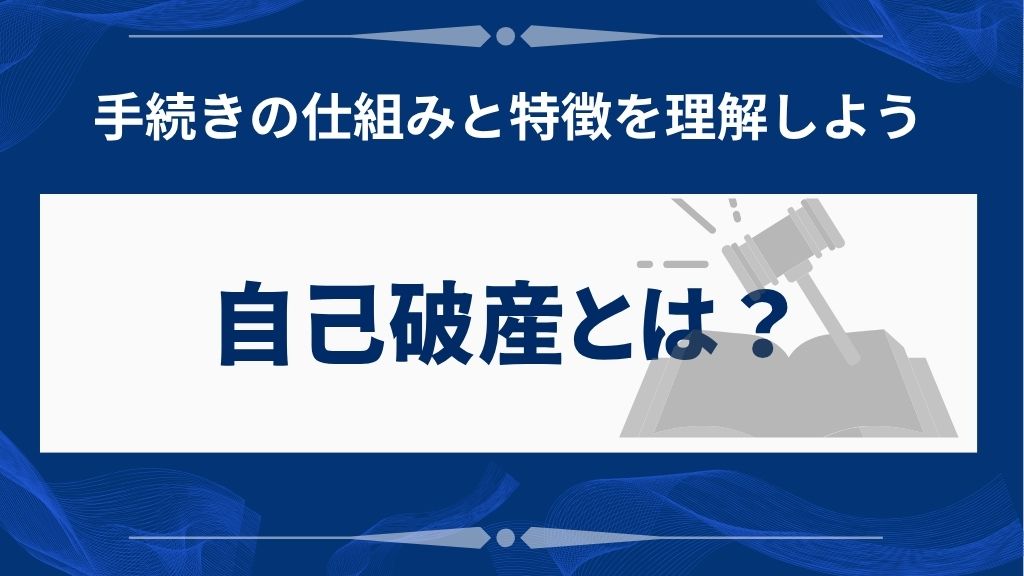
自己破産とは、債務者(借金を抱えている方)が借金を返済できない状態であることを裁判所に認められた場合に、財産を処分して債権者(お金を貸している相手/金融機関や貸金業者など)に配当した後、免責の決定によって残りの借金の支払い義務を免除してもらう法的な手続きです。
ここでは、自己破産の基本的な仕組みと手続きの種類、他の債務整理との違いについて解説します。
自己破産の基本的な仕組みと種類(同時廃止・管財事件)
自己破産の最大のメリットは、借金がゼロになる「免責」を得られることです。財産もすべてを失うわけではありません。生活に最低限必要な財産(自由財産)は手元に残せます。手続きは裁判所主導で進むため、債権者と直接交渉する必要はありません。申立てから免責までは3ヶ月~1年ほどかかりますが、この間、債権者からの取り立ては止まります。
自己破産の手続きには、主に「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があり、申立人の財産状況によって振り分けられます。
同時廃止事件(破産手続開始と同時に手続きが終了)は、お金に換えられる高価な財産(換価財産)がほとんどない場合に選ばれる、シンプルな手続きです。破産管財人が選任されないため、手続きが簡素化され、費用も比較的安く抑えられます。申立てから免責許可まで約3~4ヶ月程度で完了することが多く、個人の自己破産の約7割がこの形式です。
一方、管財事件(破産管財人が選任され、財産の調査・換価・配当が行われる)は一定以上の財産を保有している場合や、事業を営んでいた場合、ギャンブルなどが借金の原因となった場合に選ばれる手続きです。手続き期間は6ヶ月から1年程度と長くなり、破産管財人への報酬などとして、裁判所に最低20万円程度の費用(予納金)を納める必要があります。個人の管財事件向けに「少額管財」という簡易な手続きも導入されており、予納金を20万円程度に抑えつつ、期間も短縮されています。
他の債務整理との違い
自己破産は債務整理の一つですが、「任意整理」や「個人再生」といった選択肢もあります。それぞれの違いを以下の表で確認しましょう。
| 手続きの種類 | 主な特徴(借金がどうなるか) | メリット | デメリット・注意点 | 向いている人 |
| 任意整理 | ・裁判所を通さず、弁護士が債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続き ・将来利息をカットし、毎月の返済額を減額できる(元本を3~5年で分割返済) | ・裁判所を通さないため、手続きが比較的簡単 ・債権者を選んで整理できる ・財産を手放す必要がない ・官報に掲載されない ・資格・職業制限がない | ・元本は基本的に減額されず、全額返済が必要 ・債権者が交渉に応じない場合もある ・信用情報に登録される(約5年) | ・借金総額が比較的少ない人 ・毎月の返済の利息の負担を減らしたい人 ・安定した収入があり、元本の分割返済ができる人 ・自宅や車などの特定の財産を残したい人 |
| 個人再生 | ・裁判所を通じて借金を大幅に減額(通常5分の1程度)し、3〜5年で分割返済する手続き | ・借金を大幅に減額できる ・住宅ローン特則で自宅を維持できる可能性がある ・資格・職業制限がない | ・手続きが複雑で時間がかかる継続的な収入が必要 ・官報に掲載される ・信用情報に登録される(約5〜10年) | ・安定した収入があり、減額後の借金の分割返済ができる人 ・自宅を残したい人 |
| 自己破産 | ・財産を生産して、裁判所の免責決定により、原則すべての借金の支払い義務を免除してもらう手続き | ・すべての借金の支払い義務から完全に解放される ・生活を立て直すリスタートができる | ・一定の財産を手放す必要がある ・一部の職業・資格に制限がある(手続き中のみ) ・官報に掲載される ・信用情報に登録される(約5〜10年) | ・借金の返済が不可能と判断される人財産が少ない人 ・収入が少なく、生活再建を優先したい人 |
どの手続きを選ぶかは、収入状況、財産の有無、今後の生活設計などを総合的に考える必要があります。「自己破産しかない」と思い込まず、まずは弁護士や司法書士に相談して、自分の状況に最も適した方法を確認するのが安心です。
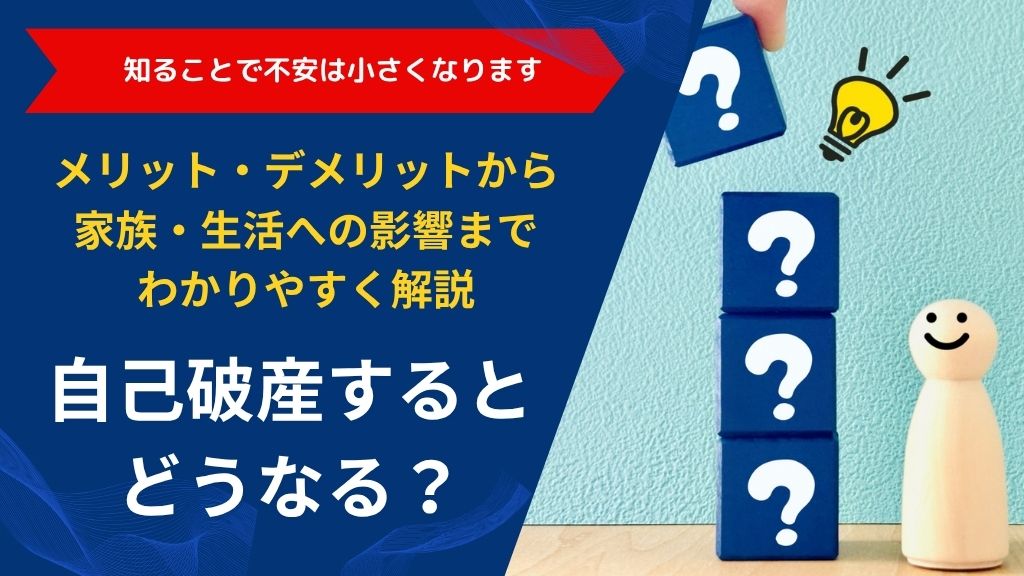
自己破産するとどうなる?メリット・デメリットから家族・生活への影響までわかりやすく解説
自己破産をすると、借金がなくなる一方で「どんなデメリットがあるのか」「仕事や家族...
自己破産手続きの流れ【9ステップで確認】
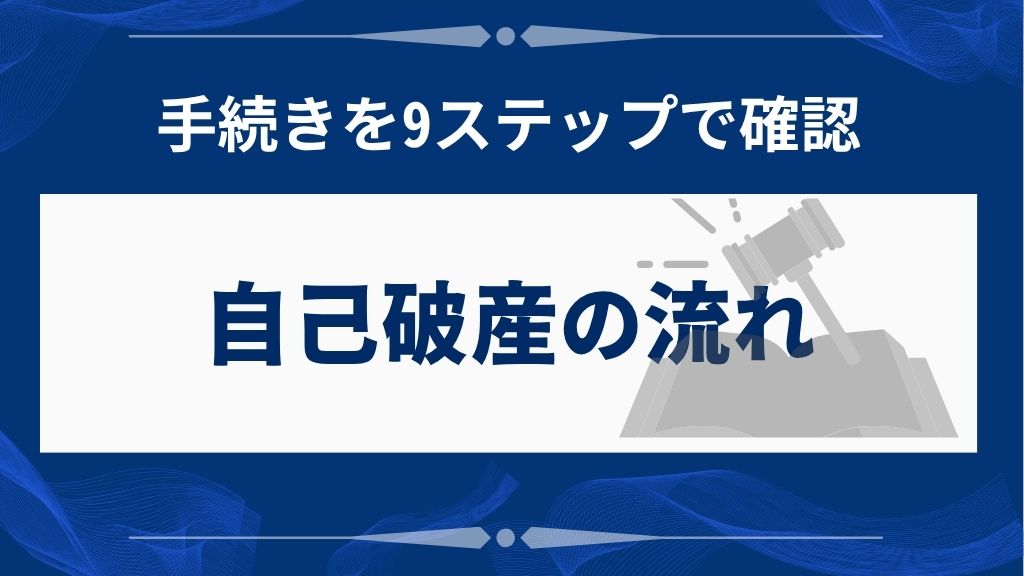
手続きの流れを理解することで、心の準備ができて、スムーズな解決への道筋が見えてきます。ここでは、自己破産手続きの一般的な流れを9ステップで解説します。
1.弁護士への相談・依頼(受任契約)
自己破産手続きの第一歩は、債務整理に精通した弁護士への相談です。多くの法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、借金の総額、収入状況、資産の有無などをヒアリングし、自己破産が最適な解決方法かを判断してくれます。
相談時には、請求書や給与明細、預金通帳、不動産の登記事項証明書などの資料を持参すると、より具体的なアドバイスを受けられるでしょう。弁護士に依頼すると、受任契約を締結し、この段階で弁護士費用の支払い方法も相談できます。契約後は、債権者からの連絡は弁護士が窓口となるため安心です。
2.債権者への受任通知送付で督促ストップ
弁護士が受任契約を締結すると、速やかにすべての債権者へ「受任通知書」を送付します。これにより、貸金業法に基づき債権者はあなたへの直接的な取り立てや督促を停止しなければなりません。
督促が止まることで、精神的なプレッシャーから解放されます。また、返済も一時的に停止されるため、生活費の確保や手続き費用の準備に専念できます。
3.申立て書類の準備・作成
自己破産の申立てには膨大な書類の準備が必要です。主な必要書類には、破産手続開始申立書、陳述書、債権者一覧表、財産目録、家計収支表、住民票、給与明細書、源泉徴収票、預金通帳のコピーなどがあります。不動産があれば登記事項証明書や固定資産税評価証明書、自動車があれば車検証や鑑定書(見積書)の提出が必要です。
財産目録には、不動産、自動車、預貯金、保険の解約返戻金、退職金見込額など、所有するすべての財産を詳細に記載しなければなりません。家計収支表は破産に至った経緯や現在の生活状況を示す重要な書類です。過去数ヶ月分の詳細な収支を記録します。弁護士は書類作成をサポートしながら、不備がないよう確認します。
4.裁判所への破産申立て
必要書類が揃うと、弁護士が管轄(申立人の住所地)の地方裁判所に破産手続開始の申立てを行います。申立てと同時に所定の費用(予納金)を納める必要があり、同時廃止事件では2万円程度、管財事件では最低20万円程度が必要です。
申立て後、裁判所は提出書類を審査し、破産手続きを開始するかを判断します。書類に不備があれば補正を求められます。
5.破産手続開始の決定/同時廃止・管財事件の判定
裁判所が申立て内容を審査し、支払不能状態(現在の財産や将来の収入をもってしても、継続的に返済することが不可能な状態)の要件を満たしていると判断すると、破産手続開始の決定が出されます。同時に、事件の種類が「同時廃止事件」か「管財事件」かが決定されます。
同時廃止事件は、換価財産がほとんどなく、免責不許可事由もない場合に適用される簡易な手続きです。手続き期間が短く、費用も安く済みます。
一方、管財事件は一定以上の財産を保有している場合や、免責不許可事由がある場合などに選択されます。破産管財人が選任され、財産の調査・換価(処分してお金に換えること)や免責に関する調査が行われるため、手続き期間が長く、予納金も高額になります。
6.債権者の意見申述期間(同時廃止事件)
同時廃止事件の場合、破産手続開始決定後に債権者の意見申述期間が設けられます。これは債権者が債務者の免責に対して意見や異議を述べることができる期間で、通常1ヶ月程度です。
債権者からの意見は比較的少なく、多くの場合、平穏に期間が経過します。この期間中、債務者が特別な手続きを行う必要はありませんが、弁護士と密に連絡を取ることが大切です。
7.破産管財人による財産調査・処分(管財事件)
管財事件では、裁判所によって選任された破産管財人が中心となって手続きが進行します。破産管財人は、通常、弁護士が選任され、債務者の財産の調査、管理、換価処分を行う専門家です。
破産管財人は債務者と面談し、財産状況や負債の原因などを詳しく聞き取り、申告された財産の実在性や評価額を調査します。お金に換えられる財産が発見された場合、破産管財人はこれを現金化し、債権者への配当原資を確保します。ただし、債務者の生活に必要な最低限の財産は「自由財産」として手元に残せます。この処分には数ヶ月を要することが多いです。
8.債権者集会(管財事件)
管財事件では、破産管財人の調査が一定程度進んだ段階で債権者集会が開催されます。これは破産管財人が調査結果を債権者に報告し、今後の手続きの方針を説明する場です。債務者も出席が義務付けられています。
債権者集会では、破産管財人から財産状況の報告や配当の見込みなどが説明されます。これに対し、債権者は質問や意見を述べることができますが、出席することは少なく、破産管財人と債務者、代理人弁護士のみで進行することが多いです。財産の換価処分が完了してない場合などは次回期日が指定され、複数回開催されることもあります。配当手続きが完了すると破産手続きは終結となり、その後は免責手続きに移行します。
9.免責審尋・免責許可決定
破産手続きが終了すると、最終段階として免責手続きが行われます。免責審尋は裁判官が債務者と面談し、免責を許可するかを判断するための手続きです。借金に至った経緯、反省の状況、今後の生活再建への意欲などについて質問されます。
正直に答えることが重要であり、虚偽の発言は免責不許可の原因となる可能性があります。代理人弁護士が同席してサポートします。
免責審尋で問題がないと判断されると、通常1週間から1ヶ月程度で免責許可決定が下されます。この決定により、借金の支払い義務から法的に解放され、新たな生活をスタートできるのです。
自己破産の手続きは、一人で進めるには複雑です。まずは債務整理に強い弁護士に相談し、最適な解決策を見つけましょう。
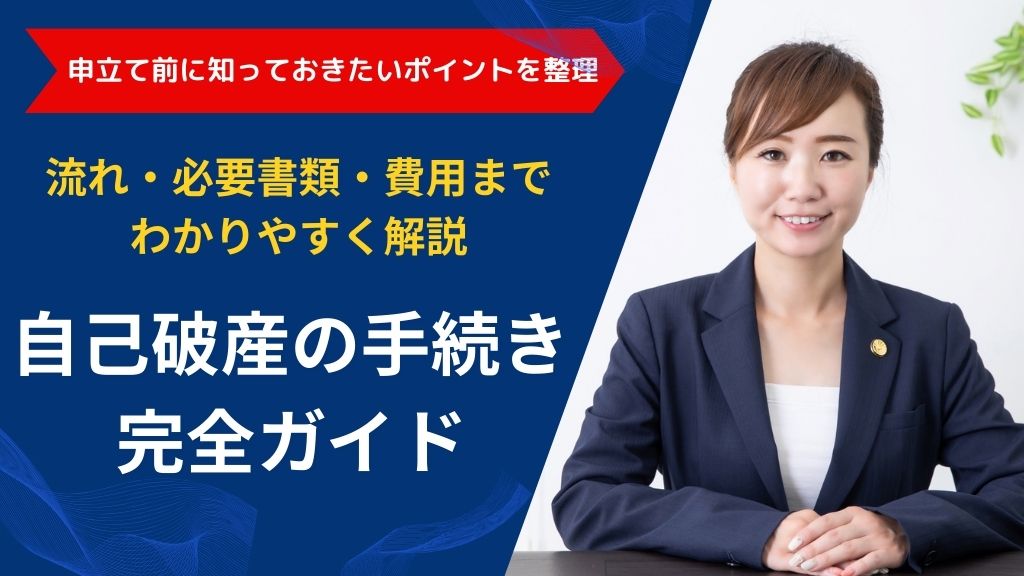
自己破産の手続き完全ガイド|流れ・必要書類・費用までわかりやすく解説
毎月の返済が苦しくて、もうどうしていいか分からない。そんな状況でも、自己破産とい...
自己破産手続きにかかる期間と費用の目安
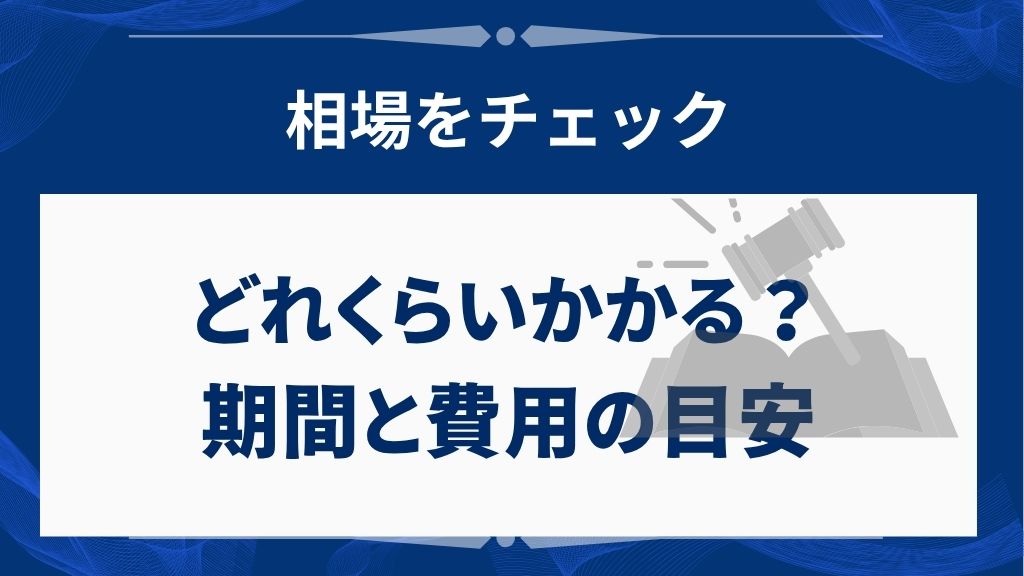
自己破産の手続きは、財産状況や借金の複雑さによって「同時廃止事件」と「管財事件」に分かれ、期間も費用も大幅に変わります。詳しく見ていきましょう。
手続きにかかる期間(同時廃止・管財事件別)
必要書類の準備期間なども考慮すると、弁護士との相談から実際の申立てまでに2~3ヶ月程度かかることが一般的です。つまり、自己破産を決意してから免責が確定するまでには、最短でも半年程度、場合によっては1年半以上の期間を見込んでおく必要があります。
手続きの種類ごとの期間と費用の目安を以下の表で確認しましょう。
| 手続きの種類 | 期間の目安 | 裁判所費用(内訳含む) | 弁護士費用の相場 |
| 同時廃止事件 | 約3~6ヶ月 | 約2万円(収入印紙代1,500円、予納郵券3,000~15,000円、官報公告費10,584円) | 20~40万円程度 |
| 管財事件 | 6ヶ月~1年程度(複雑な事案では1年以上) | 最低50万円以上(予納金として) | 30~60万円程度 |
| 少額管財 | 3~6ヶ月程度 | 約20万円(予納金として) | 30~60万円程度 |
裁判所費用の内訳
裁判所に納める費用は、手続きの種類によって大きく異なります。同時廃止事件の場合は、収入印紙代1,500円、予納郵券が3,000~15,000円程度、官報公告費が10,584円で、合計約2万円前後が目安です。
管財事件では、上記の基本費用に加えて「予納金」が必要です。通常の管財事件では最低50万円以上、事案によっては100万円を超えることもあります。この予納金は破産管財人の報酬や事務処理費用に使われます。
少額管財の場合は予納金が20万円程度に抑えられ、弁護士が申立代理人となっている場合に利用できます。経済的に困窮している場合は、予納金の分割納付や減額、法テラスの民事法律扶助制度が利用できることもあります。
弁護士費用の相場と支払い方法
自己破産の弁護士費用は事務所によって幅がありますが、同時廃止事件で20~40万円程度、管財事件で30~60万円程度が相場です。
多くの弁護士事務所では分割払いに対応しており、月額2~5万円程度の分割払いが一般的です。弁護士に依頼して受任通知を送付してもらうことで、債権者からの取り立てが止まり、その間に弁護士費用を積み立てることができます。
法テラスの民事法律扶助制度を利用できる場合は、弁護士費用の立替えを受けられ、月額5,000円~10,000円程度の分割返済となります。収入や資産が一定基準以下の場合に利用できますが、対応できる弁護士が限定されることや、手続きに時間がかかることもあるため、事前に確認しておくことが大切です。
自己破産は人生の再スタートを切るための重要な手続きです。費用や期間に関する不安も、債務整理に詳しい弁護士に相談し、具体的な見通しを確認しておきましょう。
自己破産手続き中に絶対避けるべき行為とは?
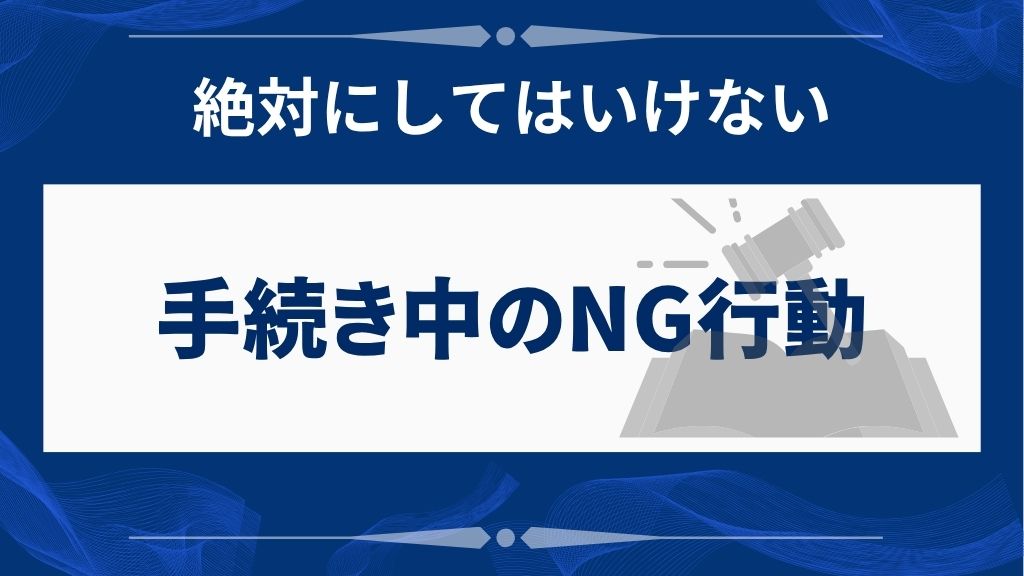
自己破産手続きが開始されると、破産者には様々な義務や制約が課されます。これに違反すると「免責不許可事由」に該当し、借金の免除(免責)が受けられなくなる重大なリスクを負うことになります。
禁止される行為は、主に債権者の利益を守り、公平な財産分配を実現するために設けられているのです。「知らなかった」では済まされません。
ここでは、手続き中に絶対にやってはいけない行為を具体的に解説します。
財産の処分や隠匿は絶対にNG
自己破産手続き中の最も重大な禁止事項の一つが、財産の無断処分や隠匿です。債務者の財産は「破産財団」として管理され、債権者への配当(借金返済の元手)となるため、勝手に処分することは許されません。
具体例としては、以下のような行為が該当します。
- 不動産や自動車の売却
- 預金の引き出しや移動
- 家族や知人への財産の贈与・名義変更
これらの行為は財産の隠匿・処分として扱われ、免責不許可の対象となります。
特に、家族のために財産を移転する行為は、明らかな財産隠匿とみなされ、最悪の場合、詐欺破産罪として刑事処罰の対象となる可能性もあります。
やむを得ず財産を処分する必要がある場合は、必ず事前に破産管財人や裁判所の承認を得てください。
新たな借入れやクレジットカード利用の禁止
破産手続き開始後、新たな借入れやクレジットカードの利用は厳格に禁止されています。これは、既存の債権者への公平性を保つとともに、債務者の経済状況をこれ以上悪化させないための制約です。
具体的には以下の行為が含まれます。
- 銀行や消費者金融からの新規借入れ
- 友人・知人からの借金
- クレジットカードでのショッピングやキャッシング
- 携帯電話の分割払い契約
- 保証人になること
既存のクレジットカードも利用停止となるのが一般的です。
生活に必要な費用であっても、原則として新たな借入れは認められません。必要な場合は、生活保護などの公的制度の利用や親族からの援助(贈与として明確にする)を受けることを検討しましょう。
転居・長期旅行時は裁判所の許可が必要
破産手続き中は、転居(住所変更)や長期間の旅行を行う際に、事前に裁判所の許可を得ることが義務付けられています。これは、破産管財人や裁判所が債務者と連絡を取れる状態を維持し、手続きを円滑に進めるためのルールです。
- 転居:同じ市区町村内でも届出が必要
- 旅行:一般的に1週間以上の旅行や県外宿泊を伴う場合は事前許可が必要
- 海外旅行:原則として許可されない
ただし、仕事上の出張や親族の冠婚葬祭、医療上必要な入院などの合理的な理由があれば許可が下りることがほとんどです。いずれの場合も、事前に正直に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。
虚偽の申告や書類を偽造すること
破産手続きにおいて、虚偽の申告や書類の偽造は最も重大な違反行為です。これらは免責不許可事由に該当し、発覚した場合は免責が認められないだけでなく、詐欺破産罪や文書偽造罪などで刑事責任を問われる可能性があります。
- 虚偽申告の例
- 債権者一覧表や財産目録への財産の記載漏れ
- 収入や支出の過少・過大申告
- 破産に至った経緯の虚偽説明
- などがあります。隠したい借金や借入理由があっても、正直に申告すべきです。破産管財人は徹底的な財産調査を行いますので、隠蔽は必ず発覚します。
- 書類の偽造の例
- 給与明細書の改ざん
- 架空の請求書の作成
- 銀行口座の取引履歴の改ざん
隠したい借金や借入理由があっても、正直に申告すべきです。破産管財人は徹底的な財産調査を行いますので、隠蔽は必ず発覚します。また、家族や知人に、存在しない貸金について証言を依頼したり、財産の隠匿を手伝ってもらう行為は、関係者をも犯罪に巻き込む可能性があります。
自己破産手続きは複雑ですが、ルールを守ることで公正な債務整理が実現できます。違反行為のリスクを冒すより、弁護士や司法書士に正直に相談し、適切な手続きを進めることが、新しいスタートを切るための最も確実な方法です。

自己破産中の注意点と手続きのNG行動一覧
自己破産をご検討中の皆さん、この記事はあなたの知りたい情報をお届けします。自己破...
自己破産を弁護士に依頼すべき理由と選び方
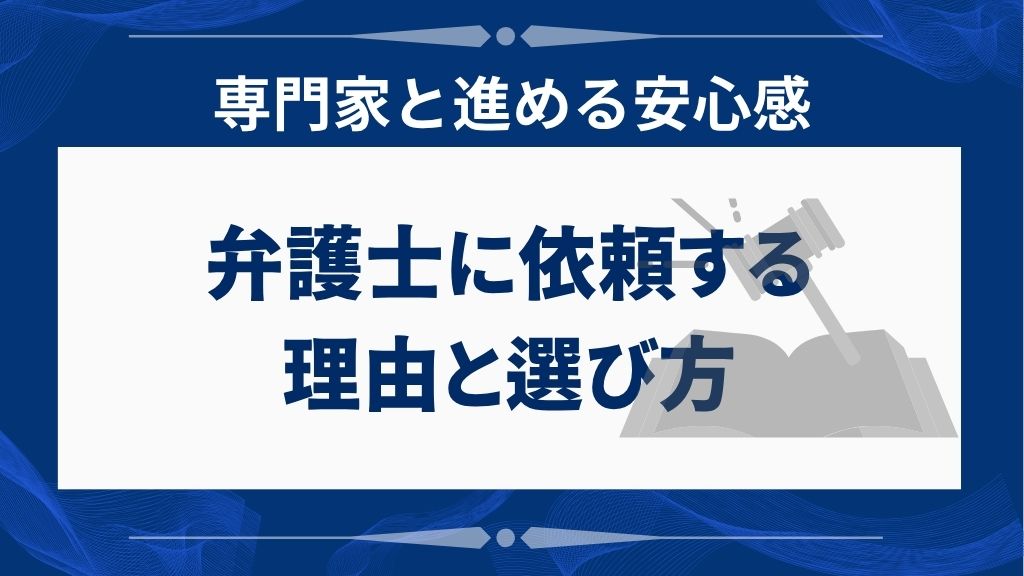
自己破産の手続きは、裁判所への申立書作成から債権者との交渉、裁判官との面談まで、法的知識と実務経験が必要な場面が数多くあります。弁護士に依頼することで、精神的な負担を大幅に軽減し、手続きをスムーズに進めることが可能になります。ここでは、弁護士に依頼する3つのメリットと、自己破産に強い弁護士の選び方を解説します。
弁護士に依頼する3つのメリット
- 債権者からの取り立てが即座に停止する
弁護士に依頼すると、すべての債権者に「受任通知」が送付され、法律上、債権者は直接債務者に連絡を取れなくなります。これにより、毎日の督促に怯える生活から即座に解放され、精神的な安定を取り戻せます。 - 複雑な手続きを全て代行してもらえる
自己破産の申立書は多岐にわたり、正確な作成が必要です。弁護士に依頼すれば、必要書類の収集から作成、裁判所への提出まで全て代行してもらえます。裁判所での面談にも同席してもらえるので、手続き期間の短縮や確実性の向上が期待できます。 - 将来の生活再建までサポートしてもらえる
自己破産は新たな生活の始まりです。経験豊富な弁護士は、破産後の生活設計についても具体的なアドバイスを提供してくれます。住宅を借りる際の注意点や、クレジットカードが作れるようになる時期など、実生活に即したサポートを受けられます。
自己破産に強い弁護士の選び方(相談タイミング含む)
- 債務整理の実績が豊富な弁護士を選ぶ
自己破産を含む債務整理は、実務経験の差が結果に大きく影響します。年間に扱う債務整理案件数が多く、自己破産についても十分な実績がある弁護士を選びましょう。初回相談時に、過去の案件数や手続き期間の目安、想定される問題点とその対策について具体的に説明してくれる弁護士は信頼できます。 - 相談しやすい環境が整っているかを確認する
精神的に追い詰められた状況で相談するため、初回相談が無料であること、土日や夜間の相談に対応してくれる、分割払いに柔軟に応じてくれるなど、依頼者の立場に配慮した対応をしてくれる弁護士を選びましょう。 - 相談の最適なタイミング
返済が困難になり始めた時点で相談することが重要です。自己破産以外の選択肢も含めて検討できます。給料の差し押さえ予告通知が届いた場合は緊急度が高いため、即座に相談することをお勧めします。早めの相談が、財産の保全や手続き期間の短縮につながります。
借金問題は一人で抱え込む必要はありません。専門家に相談することで、最適な解決方法を見つけ、新たな生活への一歩を踏み出すことができます。
「債務急済」なら、居住エリアや相談内容に合わせて最適な専門家を検索できて、無料相談への予約もスムーズです。
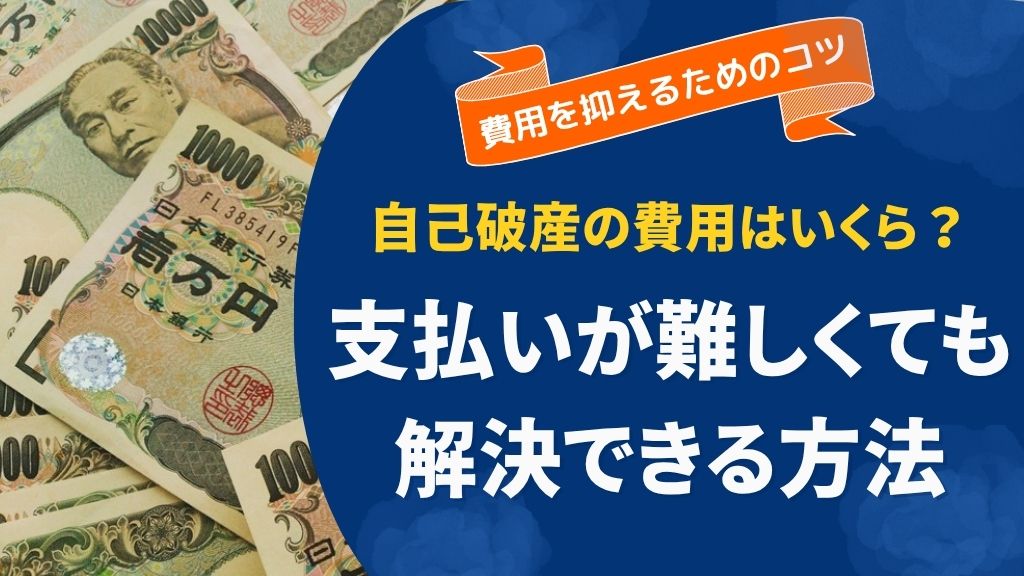
自己破産の費用はいくら?支払いが難しい人でも解決できる方法を徹底解説
「自己破産を検討しているけれど、費用がいくらかかるのか不安」「支払いが難しい状況...
まとめ
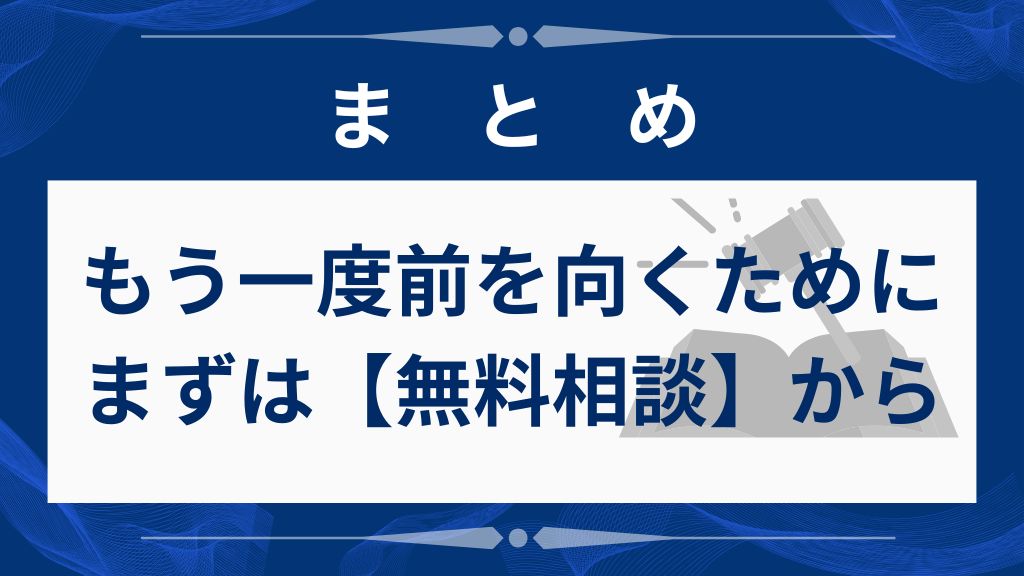
自己破産は、借金問題で苦しむ方にとって新しいスタートを切るための重要な選択肢です。ただし、手続きは複雑で、個人の状況によって最適な解決方法は異なります。収入や資産、借金の総額などを整理し、自己破産以外の債務整理(任意整理や個人再生)も含めて検討することが大切です。
手続きの過程では、裁判所への申立てから免責許可決定まで、多くの書類準備や法的な手続きが必要となり、専門知識が求められます。特に、財産の処分や債権者対応、免責不許可事由の判断は難しく、専門家のサポートが不可欠です。
できるだけ早く弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談されることをお勧めします。多くの事務所では初回無料相談を受け付けていますので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。専門家は、あなたの状況に応じた解決方法を提案してくれるはずです。
一人で抱え込まず、適切なサポートを受けながら解決に向けて歩むことで、明るい未来への道筋が見えてきます。勇気を持って第一歩を踏み出しましょう。
この記事の監修者
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。 当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
この記事に関係するよくある質問
- 自己破産すると毎月の給料はどうなるの?
- 自己破産の手続きを行う前に支払われた給料は、破産財団に組み込まれる可能性があります。 一方で、破産手続開始決定後に受け取る給料やボーナスは「新得財産」とされ、原則として差し押さえの対象にはなりません。 これは、生活に必要な財産として「自由財産」に該当するためです。
- 自己破産すると銀行口座はどうなるの?
- 自己破産を申し立てると、債務のある銀行の口座は一時的に凍結されることがあります。 ただし、すべての銀行口座が凍結されるわけではなく、借入やローン契約のある金融機関に限られます。 また、信用金庫や信用組合などでも同様に、債務がある場合は口座が凍結の対象となります。
- 自己破産したら年金はどうなる?
- 年金の受給権は「差押禁止財産」にあたるため、自己破産をしても失われることはありません。 そのため、自己破産を理由に将来の年金が受け取れなくなったり、支給額が減額されたりすることはありません。 安心して受給を続けることができます。
- 自己破産すると携帯の契約はどうなるの?
- 携帯電話の料金を滞納しておらず、現在の契約が継続している場合は、自己破産をしても契約や機種変更などに制限はありません。 一方で、自己破産時に通信料金の未払いがある場合は、契約が解除されることがあります。 ただし、免責が確定した後であれば、他社で新たに契約することは可能です。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。