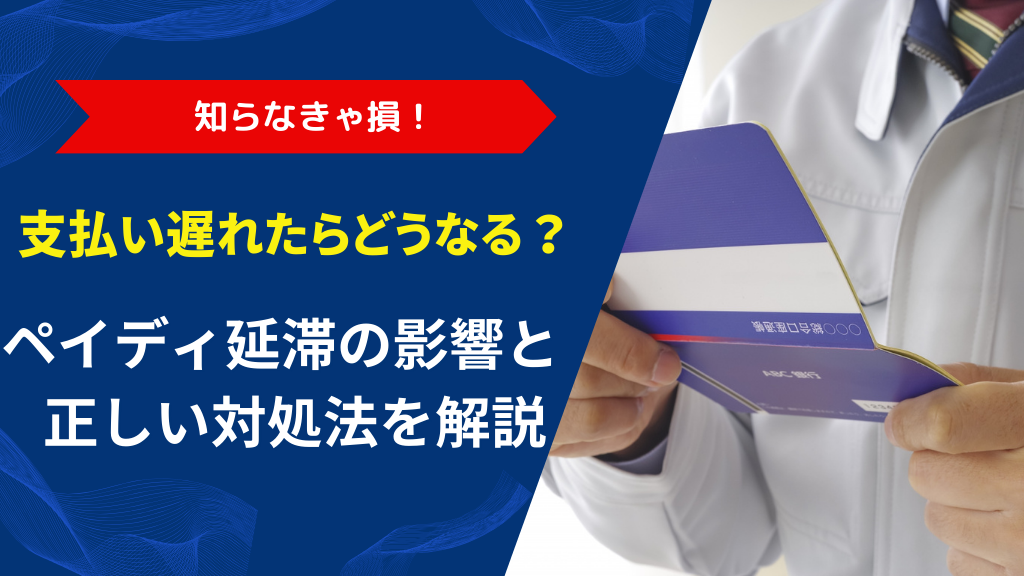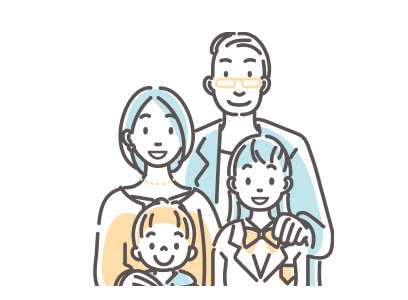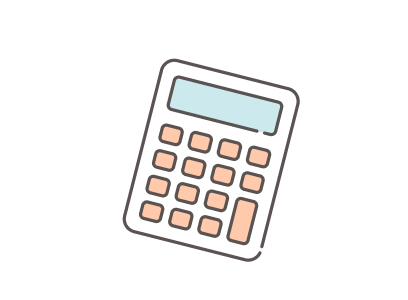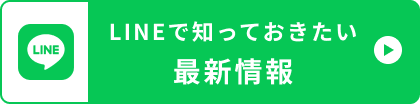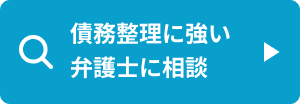個人再生の最低弁済額はいくら?あなたが払う金額の計算方法と具体例を徹底解説
個人再生(民事再生)
2024.02.04 ー 2025.12.10 更新
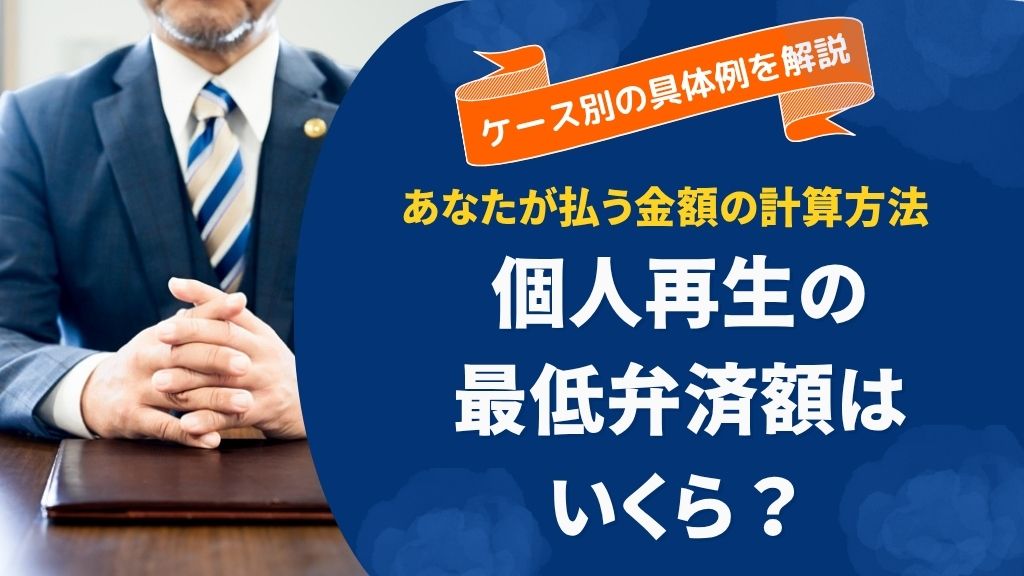
個人再生は、借金を大幅に減額しながら残った債務を3〜5年かけて分割で返済していく制度です。 しかし、どれだけ減額されても「最低弁済額」と呼ばれる、法律上必ず返済しなければならない金額が存在します。
この最低弁済額は、借金の総額、保有している財産の評価、毎月の手取り収入などをもとに計算され、 人によって返済額は大きく異なるものです。
この記事では、個人再生における最低弁済額の計算方法や具体的なシミュレーション、そして手続き後の返済イメージまでを詳細に解説し「自分の場合はいくら返すことになるのか?」の目安がわかります。ご自身の負担を把握し、無理のない再生計画を立てるためにも、ぜひ最後までご覧ください。
こんな人におすすめの記事です。
- 借金を減らしたいが「個人再生でどれだけ減るか」を知りたい方
- 最低弁済額の仕組みや計算方法をわかりやすく理解したい方
- 自己破産との違いを比較して最適な方法を選びたい方
- 将来の返済負担をシミュレーションして生活再建を考えたい方
記事をナナメ読み
- 最低弁済額は、個人再生で必ず返済すべき「法律で定められた最低額」
- 決定には「借金総額・清算価値・可処分所得」の3基準を比較して算出
- 返済期間は原則3年(特別事情で5年まで延長可能)で正確な計算が重要
- 弁護士に相談すれば、誤算を防ぎ無理のない返済計画を立てられる
個人再生の最低弁済額とは?あなたが払う金額の決まり方
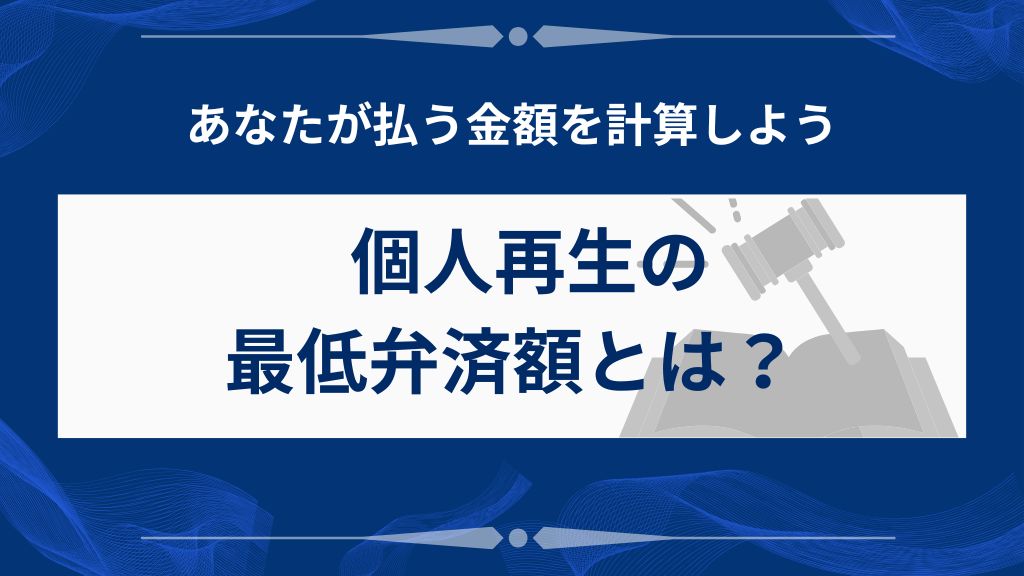
個人再生では法律で決められた「最低弁済額」をもとに返済額が決まります。「どれくらい返せばいいのか」は、多くの方にとって最大の関心事でしょう。ここでは最低弁済額の仕組みと、実際にいくら支払うことになるのかを解説します。
法律で決められた最低限の返済額の基準
個人再生は、裁判所を通じて借金を大きく減らし、残りを原則3年間で返済する制度です。この時、どれだけ減額されても一定額は必ず返済しなければなりません。その最低限の金額が「最低弁済額」として法律で定められています。
債務整理における最低弁済額の位置づけ
最低弁済額とは、個人再生に置いて債務者が返済すべき最低限の金額です。これは裁判所に提出する再生計画に盛り込まれ、法律に基づいて決まります。最低弁済額の目的は、債務者の生活再建を助けながらも、債権者にも一定の返済を保証することです。
なお、自己破産では借金がすべて免除されますが、財産は基本的に処分されます。一方個人再生では財産を維持しつつ借金を減額し、最低弁済額以上の返済を計画的に行う必要があります。このように、個人再生における最低弁済額は、制度の中核をなす重要な基準です。
裁判所が認可する返済計画の原則
個人再生では、再生計画が裁判所に認可されなければ手続きが進みません。その条件の一つが、弁済額が法律で規定された最低弁済額を下回らないことです。
裁判所は、提出された再生計画が公正で現実的かを厳格にチェックします。計画の内容や年債能力、債権者への配慮なども審査対象です。とくに最低弁済額の計算は、計画認可の前提となる重要なポイントです。そのため、正確な算定には専門的な知識と経験が求められます。
借金がどこまで減るか、限界ラインを知ろう
個人再生における借金の減額幅は、債務者の状況によって大きく異なります。減額の限界ラインを正確に把握することは、手続き後の生活設計を立てる上で非常に重要です。
自己破産との減額効果の違い
自己破産は原則として全ての借金が免除される手続きです。ただし、その代わりに一定の財産は処分されます。一方、個人再生では借金が大幅に減額されますが、全額は免除されません。しかし、住宅などの財産を手元に残したまま手続きができるのが大きな特徴です。
最低弁済額は、この「財産を守りながら返済する」という個人再生の特性を反映した金額です。債権者から見ても、自己破産で何も回収できないより個人再生で一部でも回収できるほうが有利です。
住宅ローン特則利用時の計算方法
個人再生では、「住宅ローン特則」という制度を使えば、自宅を手放さずに手続きできます。この特則を利用できるのは住宅ローンがある人に限られ、一定の条件を満たす必要があります。
住宅ローン特則を使うと、住宅ローンの残高は最低弁済額の計算から除外されます。つまり住宅ローン以外の借金だけをもとに最低弁済額が決まります。これは、住宅ローンの債権者だけが特別な扱いを受けるためです。そのため、対象となる借金が少なくなり最低弁済額も抑えられる可能性があります。
ただし住宅ローン特則の適用には厳格な条件があります。利用を考えている方は弁護士などの専門家に相談することが重要です。
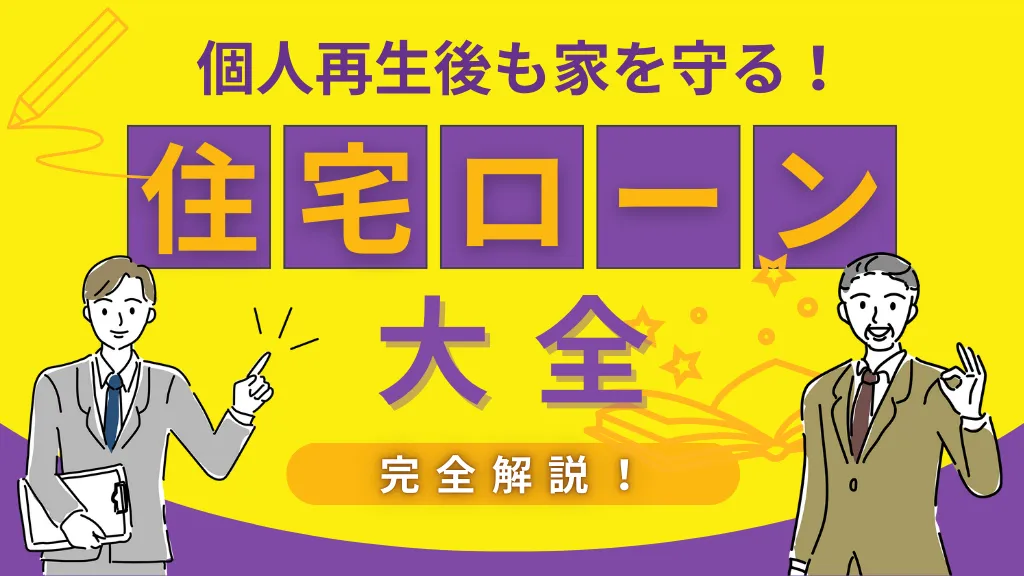
個人再生で家を守ることができる?住宅ローン特則の活用法を解説
個人再生することで、借金の返済を無理なく行いながら、家を守ることができます。 こ...
最低弁済額を決める3つの計算基準
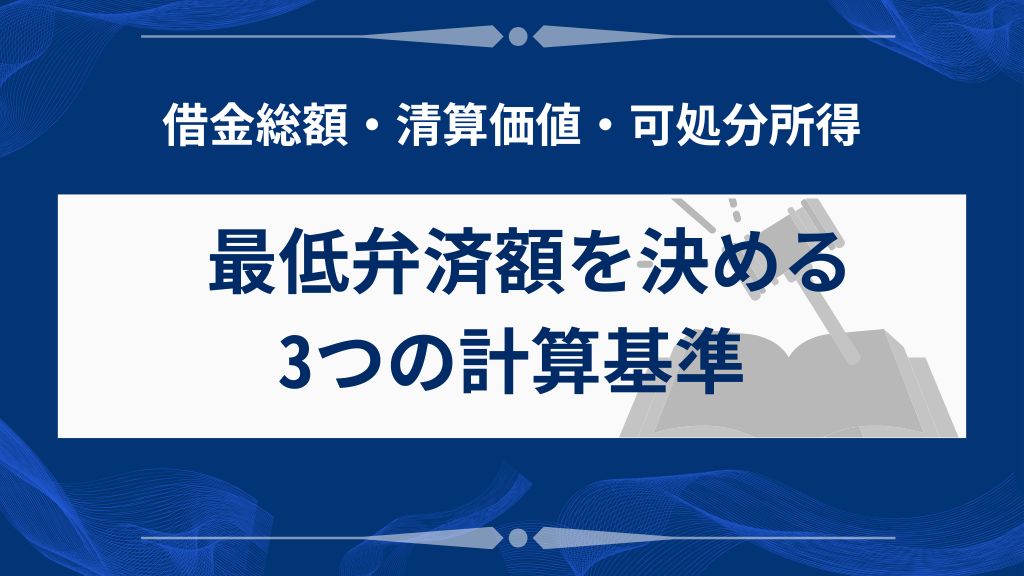
個人再生の最低弁済額は、3つの基準を比較して決まります。このうち最も高い金額が最低弁済額として採用されるのです。それぞれの基準を正確に理解することで、将来の返済額をある程度予測できます。ご自身の状況にどの基準が当てはまりそうかを知っておきましょう。
①借金総額による基準(債務総額500万円未満なら100万円など)
1つ目の基準は、借金の総額に応じて最低返済額が決まる「法律上の最低弁済額」です。この金額は法律で明確に定められています。借金が多いほど最低弁済額も高くなりますが、それでも大幅な減額が可能です。
借金総額別の最低弁済額一覧
具体的な基準額は以下の通りです。
| 借金総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金総額全額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1,500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円以上5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
【補足】 住宅ローンは、この「借金総額」には原則として含まれません。住宅ローン特則を利用する場合は、住宅ローン以外の借金が上記の基準に適用されます。
債権者リストの作成と借金の洗い出し方法
最低弁済額を正しく計算するには、借金の総額を正確に把握することが重要です。そのためには、すべての債権者(借入先)をリストアップし、残高を確認する必要があります。
消費者金融、クレジットカード会社、銀行のカードローン、知人からの借金などもすべて対象です。少しでも漏れがあると、正しい計算ができなくなります。過去の取引履歴を取り寄せて「引き直し計算」を行うことで、実際の残高が減ることもあります。
※引き直し計算:利息制限法に基づき、過払い利息を差し引いて正しい残高を算出する方法
これらの作業は専門性が高いので、弁護士に依頼がおすすめです。
②清算価値による基準(あなたの財産の評価額で保障)
2つ目の基準は「清算価値」です。これは、もし自己破産した場合に、所有する財産をお金に換えて債権者に配るとしたらいくらになるかを見積もった金額です。個人再生では、債権者が自己破産よりも不利にならないよう、この清算価値分は最低限返済するというルールが設けられています。
不動産・車・保険解約返戻金の具体的な価値計算
清算価値に含まれる主な財産と、その評価方法は以下の通りです。
- 不動産
不動産の時価から住宅ローン残高を差し引いた額が清算価値に含まれます。
※時価とは現在の市場価格で、不動産鑑定や固定資産税評価額などを参考にします。 - 自動車
車の「時価」が20万円を超える場合、その超過部分が清算価値になります。一般的には中古車買い取り業者などの査定額が基準です。 - 生命保険の解約返戻金
解約した時に戻ってくる金額のうち、20万円を超える部分が清算価値となります。保険会社に「解約返戻金の見込み額」を問い合わせて確認します。
退職金見込額と預貯金の評価方法
以下のような財産も、清算価値に含まれる可能性があります。
- 退職金の見込額
勤務先の退職金規定に基づき、今すぐ自己都合で退職した場合にもらえる金額を基準にします。
通常は、その8分の1(場合によっては4分の1)が清算価値に含まれます。ただし、見込額が20万円以下の場合は原則として清算価値の対象外です。 - 預貯金
銀行やゆうちょ、ネットバンクなど、すべての預貯金の合計額を確認します。合計額が99万円を超える場合、その超過部分が清算価値になります。
これらの評価は、正確に行うためには専門的な知識が必要です。とくに不動産や高額な資産がある場合は、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
③可処分所得による基準(手取り収入から生活費を引いた金額)
3つ目の基準は、「可処分所得」による計算です。この基準が使われるのは「給与所得者等再生」という手続きを選択した場合に限られます。
可処分所得とは、手取り収入から生活に必要な最低限の費用を差し引いた残りの金額です。国が定めた生活基準(政令で決まっている基準生活費)をもとに計算されます。この可処分所得の2年分(場合によっては3年分)が最低返済額の目安です。
給与所得者の可処分所得計算式
給与所得者の可処分所得は、以下のように計算されます。
年収 − (所得税 + 住民税 + 社会保険料)= 可処分所得
この可処分所得から、「最低限の生活費」を引いた残りの金額が、返済にあてるべき金額です。最低限の生活費は、政令で定められた基準(家族構成や地域などによって異なる)に基づきます。
扶養家族がいる場合の生活費控除
生活費として控除される金額(政令基準額)は次の要素で決まります。
- 居住地域(都市部か地方か)
- 扶養家族の人数(配偶者や子どもなど)
扶養家族が多いほど、生活費として認められる金額も大きくなります。その分可処分所得から差し引かれる金額も増えるため、最低弁済額が低くなることが多いです。逆に、独身で収入が高い場合は控除額が少なくなり、最低弁済額が高くなる傾向があります。
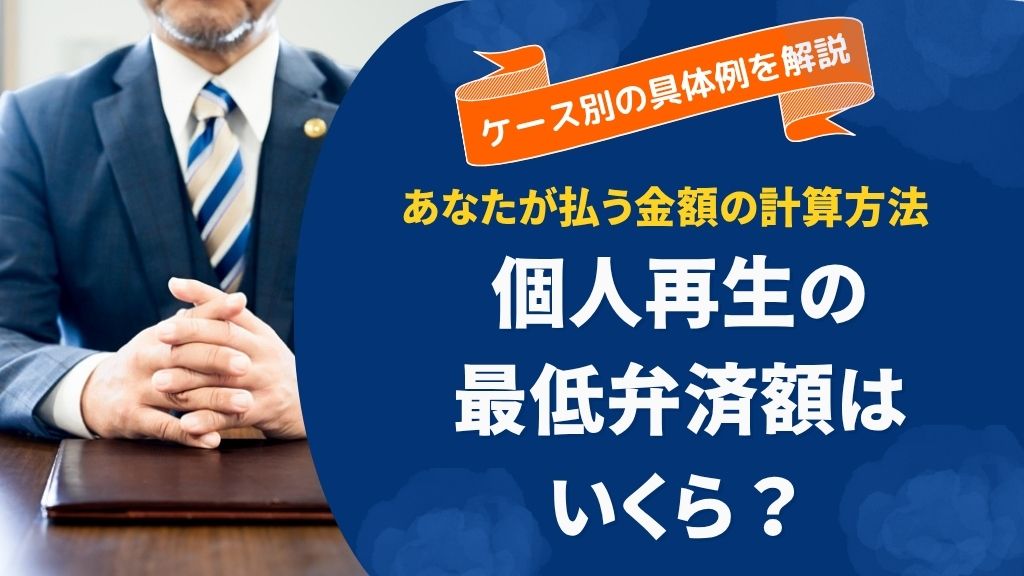
個人再生の最低弁済額はいくら?あなたが払う金額の計算方法と具体例を徹底解説
個人再生は、借金を大幅に減額しながら残った債務を3〜5年かけて分割で返済していく...
弁護士相談で避けられる計算ミスと手続きの落とし穴
個人再生の最低弁済額は、3つの基準を比較し、最も高い金額で決まります。この計算には法律や制度の知識が必要で、非常に複雑です。専門知識のない方が自力で手続きを進めると、計算ミスや書類の不備などで手続きが失敗するリスクがあります。
財産評価を間違えると最低弁済額が大幅に変わるリスク
清算価値の計算では、不動産や自動車、生命保険、退職金など、すべての財産を正しく評価することが必要です。この評価を誤ると、最低弁済額が大きく変わってしまいかねません。
評価額が低すぎると、再生計画が裁判所に認可されないこともあります。逆に実際より高く見積もってしまうと、返済負担が本来より重くなってしまうリスクもあります。
たとえば、退職金の見込額の計算方法や生命保険の解約返戻金の扱いなど、財産評価には細かなルールが存在します。これを正しく運用するには正確な知識が不可欠です。
債権者との交渉で有利になる専門知識の重要性
個人再生の手続きでは、債権者との間で意見が対立することがあります。とくに「小規模個人再生」の場合は債権者の同意が必要です。
このような場面では法律の専門知識を持った弁護士が交渉に入ることで、同意を得やすくなります。債権者との信頼関係や交渉力も重要なポイントです。また、再生手続きでは裁判所への申し立て書類の作成、再生計画案の策定、債権者集会での説明など、多くの専門的な対応が求められます。
複雑な手続きや債権者との交渉を一人で抱えるのは大きな負担です。経験豊富な弁護士に相談すれば、あなたの再生計画を確実に前へ進めるサポートが得られます。
具体例で理解する最低弁済額のパターン
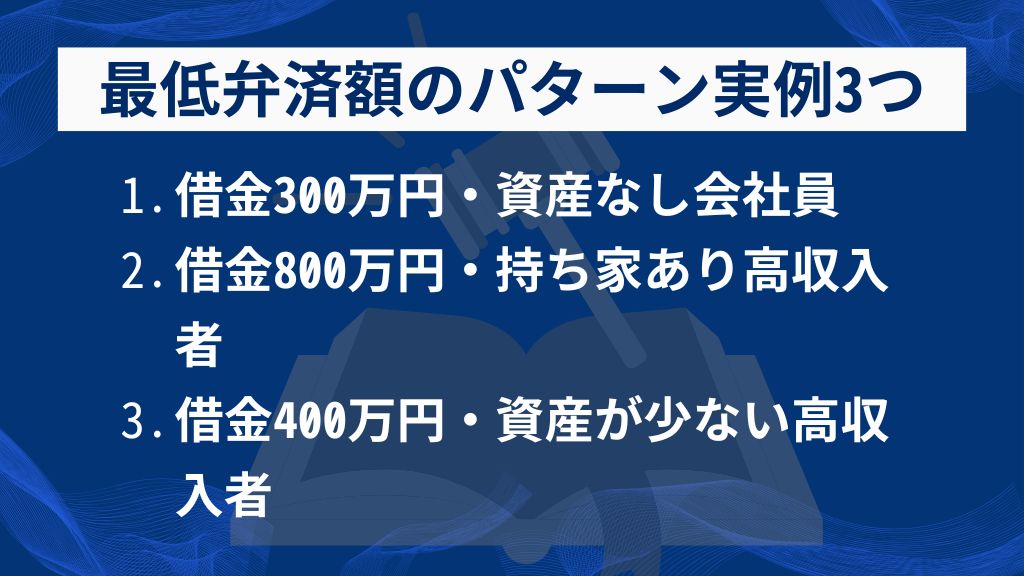
ここまで、最低弁済額を決定する3つの基準について解説してきました。ここからは、実際のケースをもとにそれぞれの基準がどのように適用されるかを見ていきましょう。
収入や借金の額、財産の状況によって返済額は大きく変わります。ご自身のケースと近い事例があれば、ぜひ参考にしてみてください。
借金300万円・資産なし会社員の小規模個人再生ケース
まずは、比較的シンプルなケースとして、30代の会社員Aさんの事例を紹介します。
| Aさんの状況 | 詳細 |
|---|---|
| 借金総額 | 300万円(クレジットカード・カードローン) |
| 月収(手取り) | 25万円(手取り20万円) |
| 資産 | 預貯金30万円、車(時価40万円) |
| 家族構成 | 独身 |
3つの基準での計算結果と最終決定額
Aさんの最低弁済額は、次の3つの基準をもとに比較して決まります。
① 借金総額による基準
Aさんの借金総額は300万円です。 これは「100万円以上500万円未満」に該当するため、最低弁済額は100万円と定められています。
② 清算価値による基準
Aさんの預貯金は30万円で、これは99万円以下のため、清算価値には含まれません。 一方、自動車の時価は40万円で、清算価値への算入基準(20万円)を超えています。 したがって、超過分の20万円が清算価値に含まれます。
→ 清算価値の合計:20万円
③ 可処分所得による基準
Aさんは「小規模個人再生」を選択しているため、この基準は適用されません。
※可処分所得基準は「給与所得者等再生」の場合のみ使用されます。
小規模個人再生では、以下2つのうち高い方が最低弁済額となります。
①借金総額による基準(100万円)
②清算価値による基準(20万円)
よって、Aさんの最低弁済額は「100万円」です。
月々の分割返済額と年間返済計画
Aさんの最低弁済額は100万円と決まりました。これを原則3年間(36ヶ月)で分割返済すると仮定した場合、次のような返済計画になります。
- 月々の返済額:約2万7,778円(=100万円 ÷ 36ヶ月)
- 年間の返済額:約33万3,336円
Aさんの手取り月収が20万円であれば、毎月の返済額は収入の約14%程度にあたります。これは、生活費を差し引いても無理なく返済を続けられる範囲と考えられます。
借金800万円・持ち家あり高収入者のケース
次に、持ち家があり、高収入である40代会社員Bさんの事例を見てみましょう。
| Bさんの状況 | 詳細 |
|---|---|
| 借金総額 | 800万円(カードローン、事業資金など) |
| 月収(手取り) | 50万円(手取り38万円) |
| 資産 | 持ち家(住宅ローン残高1,500万円、時価2,000万円)、預貯金100万円、車80万円 |
| 家族構成 | 配偶者・子供2人 |
清算価値が高額になる場合の対応策
Bさんの借金総額は800万円です。最低弁済額は、次の3つの基準を比較して決定されます。
① 借金総額による基準
Bさんの借金総額は「500万円以上1,500万円未満」に該当します。
この場合、法律で定められた最低弁済額は借金の5分の1とされており、800万円 × 1/5 = 160万円が基準となります。
② 清算価値による基準
Bさんは高額な資産を保有しており、清算価値が大きくなるケースです。
まず、持ち家の時価は2,000万円で、住宅ローンの残高が1,500万円あるため、差額の500万円が清算価値に含まれます。
次に、預貯金は100万円あります。99万円までは算入されませんが、ここでは簡略化し、全額の100万円を清算価値として扱います。
さらに、自動車の時価は80万円であり、控除基準の20万円を超えているため、差額の60万円が清算価値に加算されます。
これらを合計すると、清算価値は
500万円(不動産)+ 100万円(預貯金)+ 60万円(自動車)= 660万円となります。
③ 可処分所得による基準
Bさんは「小規模個人再生」を選択しているため、この基準は適用されません。可処分所得基準は、「給与所得者等再生」の場合にのみ使われる方式で、手取り収入から国が定めた生活費を差し引いた残額をもとに最低弁済額を算出します。
小規模個人再生では、①の借金総額基準(160万円)と②の清算価値基準(660万円)を比較し、高い方の金額が最低弁済額として採用されます。
よってBさんの最低弁済額は「660万円」となります。
このように、不動産や預貯金など高額な資産を保有していると、借金総額に比べて清算価値が大きくなり、最低弁済額が大幅に増えることがあります。
たとえば、660万円を3年間(36ヶ月)で返済すると、月々の返済額は約18万3,333円となります。これは家計への大きな負担となりかねません。
このような状況では、次のような対応策を検討しましょう。
- 返済期間の延長(最大5年まで)を裁判所に申し立てる
- 任意整理や自己破産など、個人再生以外の手続きも視野に入れる
- 資産の見直しや処分も含めて、弁護士と綿密に相談する
このように、資産が多い=再生手続きが有利とは限らない点にも注意が必要です。手続きに入る前に、専門家のアドバイスを受けながら、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
住宅ローン特則併用時の注意点
Bさんは持ち家を維持するために、住宅ローン特則を利用することになります。この特則を利用することで、住宅ローンは個人再生の減額対象から除外され、他の借金のみが減額の対象となります。
しかし、上記の例のように、住宅の資産価値(時価からローン残高を差し引いた額)が清算価値に大きく影響を与えるため、思ったほど借金の減額効果が得られない可能性も十分にあります。
住宅ローン特則の利用ができるかどうか、またその結果として清算価値にどのような影響が出るかについては、法律と不動産の知識を前提とした専門的な判断が必要です。そのため、利用を検討する際は必ず弁護士に相談し、正確な資産評価と制度適用の可否を確認するようにしてください。
可処分所得基準が支配的になるケース
最後に、高収入だが資産が少ない方が「給与所得者等再生」を選択した場合のケースです。会社員Cさんの状況を見てみましょう。
| Cさんの状況 | 詳細 |
|---|---|
| 借金総額 | 400万円 |
| 月収(手取り) | 70万円(手取り50万円) |
| 資産 | 預貯金150万円のみ |
| 家族構成 | 独身 |
給与所得者等再生が必要になる事情
Cさんのように高収入で、かつ債権者の同意を得るのが難しい(例えば、債権者が多数にわたる、または個別の債権者が同意しない可能性がある)と判断される場合には、「給与所得者等再生」の選択が検討されます。
この手続きでは債権者の同意が不要なため、合意をとりまとめる手間や難しさを避けられます。ただし、後述するように弁済額の計算には注意が必要です。
収入が一定以上ある債務者の計算例
ひきつづき、給与所得者等再生を選択した高収入の会社員・Cさんの事例を見ていきます。
この手続きでは、最低弁済額を決めるにあたって、3つの基準すべてを満たす必要があります。つまり、借金総額による基準、清算価値による基準、可処分所得による基準のうち、最も高い金額が適用されます。
① 借金総額による基準
Cさんの借金総額は400万円です。
これは「100万円以上500万円未満」に該当するため、借金基準による最低弁済額は100万円となります。
② 清算価値による基準
Cさんの預貯金は150万円あり、これは99万円を超えるため清算価値に全額算入されます。したがって、清算価値の基準は150万円です。
③ 可処分所得による基準
Cさんは独身で、手取り月収が50万円あります。
国の基準により、独身の最低生活費を月額15万円と仮定すると、毎月の可処分所得は35万円(=50万円 - 15万円)です。
これを年額にすると420万円、給与所得者等再生では2年分(420万円 × 2)= 840万円が最低弁済額となります。
給与所得者等再生では、①借金基準(100万円)、②清算価値基準(150万円)、③可処分所得基準(840万円)のすべてを満たす必要があります。 したがって、この中で最も高い③可処分所得基準の「840万円」が最低弁済額として適用されます。
よって、Cさんの最低弁済額は「840万円」となります。Cさんのケースでは借金総額は400万円と比較的少額ですが、可処分所得が高いために最低弁済額が2倍以上(840万円)となってしまいました。このように、収入が高い方は、給与所得者等再生を選ぶと返済額が非常に大きくなる可能性があります。
小規模個人再生 vs 給与所得者等再生の選択基準
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、どちらを選ぶかによって最低弁済額の計算方法や手続きの進め方が異なります。ご自身の状況に合った手続きを選択しましょう。
| 項目 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
|---|---|---|
| 主な特徴 | 債権者の同意が必要だが、柔軟な減額が可能。 | 債権者の同意は不要だが、可処分所得基準が加わる。 |
| 最低弁済額の決定 | ①借金総額基準と②清算価値基準のうち高い方で決まる。 | ①借金総額基準、②清算価値基準、③可処分所得基準の全てを満たす必要がある。 |
| メリット | ・可処分所得基準がないため、高収入の方でも返済額を抑えられる可能性が高い。 ・債権者の同意が得られれば、より柔軟な再生計画が立てられる。 | ・債権者の同意が不要なため、手続きの確実性が高い。 ・債権者の数が多い、または一部の債権者からの反対が予想される場合に有効。 |
| デメリット | ・債権者の同意が必要で、過半数の反対があると手続きが失敗するリスクがある。 ・債権者が多様な場合、同意を得るための調整が難しい可能性がある。 | ・可処分所得基準が加わるため、高収入の方の場合、返済額が高くなる可能性がある。 ・安定した給与収入があることが必須要件となる。 |
| 向いている人 | ・債権者の数が比較的少ない方。 ・高収入で、可処分所得基準が適用されると返済額が過大になる恐れがある方。 ・返済額をできるだけ抑えたい方。 | ・債権者の数が多く、同意を得るのが難しいと予想される方。 ・特定の債権者からの反対を確実に避けたい方。 ・可処分所得が他の基準(借金総額・清算価値)を上回らない方。 ・安定した給与収入があり、今後の返済計画に自信がある方。 |
「できるだけ返済額を抑えたい」「収入が高く、可処分所得基準で返済額が跳ね上がるのが心配」という方は、小規模個人再生の検討が一般的です。ただし、この手続きでは債権者の同意が必要になるため、その点には注意が必要です。
一方、「債権者が多く、同意が得られるか不安」「できるだけ確実に手続きを進めたい」という方には、給与所得者等再生が向いています。この場合、ご自身の収入に基づく可処分所得基準により返済額が大きくなる可能性があるため、事前に慎重なシミュレーションが欠かせません。
どちらの手続きがより適しているかは、借金総額、資産、収入、債権者の状況などを総合的に判断する必要があります。迷った場合は、個人再生に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
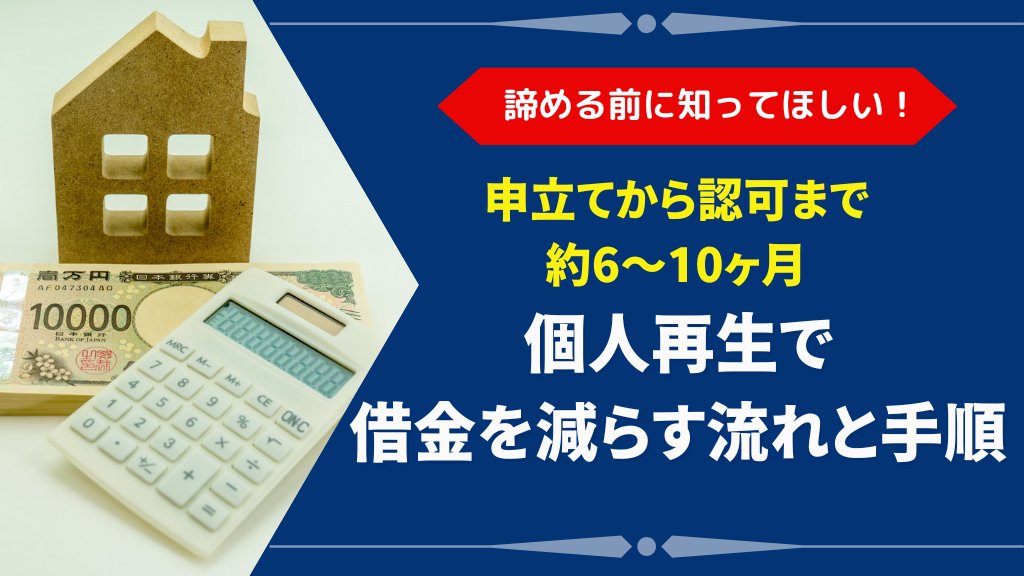
個人再生の流れを14ステップで完全解説!手続き方法と成功事例を紹介
返済に追われる毎日から抜け出したいと思いながらも、自己破産は避けたいという方にと...
最低弁済額が決まった後の返済ルール
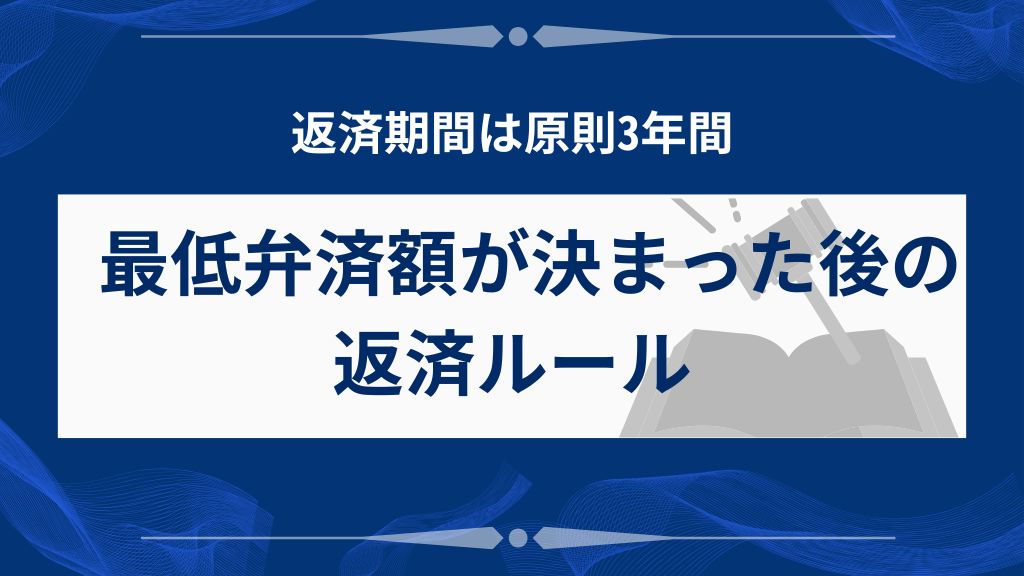
再生計画が裁判所で認可され、最低弁済額が確定したら、いよいよ返済が始まります。この返済には、あらかじめ決められた期間や方法があるため、事前の確認が大切です。
返済期間は原則3年間(特別な事情で最長5年まで延長可能)
個人再生で決定された返済額は、原則として3年間(36か月)で完済することが法律で定められています。これは債務者が生活を立て直しながら返済できる現実的な期間であり、債権者にとっても借金を合理的に回収できる年数として設定されています。
なお、特別な事情がある場合には、最長で5年まで返済期間を延長することも可能です。
3年返済が法律で定められた理由と根拠
個人再生は、債務者の生活再建を目的とする一方で、債権者の回収権も保護するバランスの取れた制度です。返済期間が原則3年と定められているのは、こうした両社の利益を調整するためです。
3年という期間は、債務者にとっては早期の再出発を可能にしつつ、債権者にとっても一定期間内に弁済を受けられる合理的な年数とされています。
この原則は、民事再生法第229条に明記されています。
5年延長が認められる具体的な事情とは
「3年での返済は厳しい」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。以下のような「特別な事情」が認められる場合には、裁判所の許可を得て最長5年間(60か月)まで返済期間を延長することが可能です。
- 家族の介護費用や子どもの教育費など、継続的に高額な支出がある場合
- 本人や家族の医療費が高額になっている場合
- 病気や災害などにより、一時的に収入が減少している場合
- 住宅ローンと合わせて返済することで、家計が著しく厳しくなる場合
ただし、「支払いが苦しい」というだけでは延長は認められません。裁判所に納得してもらうには、家計収支表や診断書などの具体的な資料を提出し、3年間での返済が現実的に困難であることを客観的に証明する必要があります。
この判断には法律や実務に関する専門知識が必要です。延長を希望する場合は、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
3カ月ごとの分割払いが基本ルール
個人再生の返済は、原則として3か月ごとに分割して支払うのが基本です。つまり、年に4回のペースで、各債権者に決められた金額を振り込んでいく形になります。
毎月払いではなく3カ月ごと払いになる理由
この支払いサイクルは、給与所得者が毎月の収入を少しづつ貯めてからまとめて支払うことを想定しています。毎月の家計に無理をかけず、計画的な返済を続けやすくするために、現実的な頻度として「3か月ごと」が選ばれています。
債権者の分配手続きと返済方法の選択肢
返済が始まると、債務者は裁判所が選んだ再生委員(通常は弁護士)や申立代理人の指示に従い、各債権者に直接振り込みを行います。ただし債権者の同意があれば、毎月払いなど他の支払い方法に変更することも可能です。実際には家計管理のしやすさから毎月払いを選ぶ人も少なくありません。
支払いの開始時期は、再生計画の認可決定が確定した月の翌月から始まるのが一般的です。
月々いくら払うかの計算方法
実際の返済額は、確定した最低弁済額を返済期間で割って算出します。以下に具体的な計算例を示します。
最低弁済額を返済期間で割る計算例
- 【3年(36か月)返済の場合】
最低弁済額:300万円
月々の返済額:300万円 ÷ 36か月 = 約8万3,333円
※3か月ごとの支払いなら、1回あたり約25万円を年4回支払います。 - 【5年(60か月)返済の場合】
最低弁済額:300万円
月々の返済額:300万円 ÷ 60か月 = 5万円
※3か月ごとであれば、1回あたり15万円を年4回支払います。
家計に無理のない返済計画の立て方
返済期間を延ばせば月々の負担は軽くなります。しかし返済総額が減るわけではありません。また、長期になるほど途中で収入や生活環境が変化するリスクもあります。返済計画を立てる際は、次の点を確認しましょう。
- 手取り収入から、住宅費・生活費・固定支出を差し引く
- 残るお金で、返済が無理なく続けられるかを検討する
- 数ヶ月先の支出も見据えて、余裕をもったプランにする
計画づくりでは、弁護士が家計の状況を丁寧にヒアリングし、現実的なアドバイスをしてくれます。「払えない」よりも、「確実に払える」プランを選ぶことが再スタートにおいては大切です。
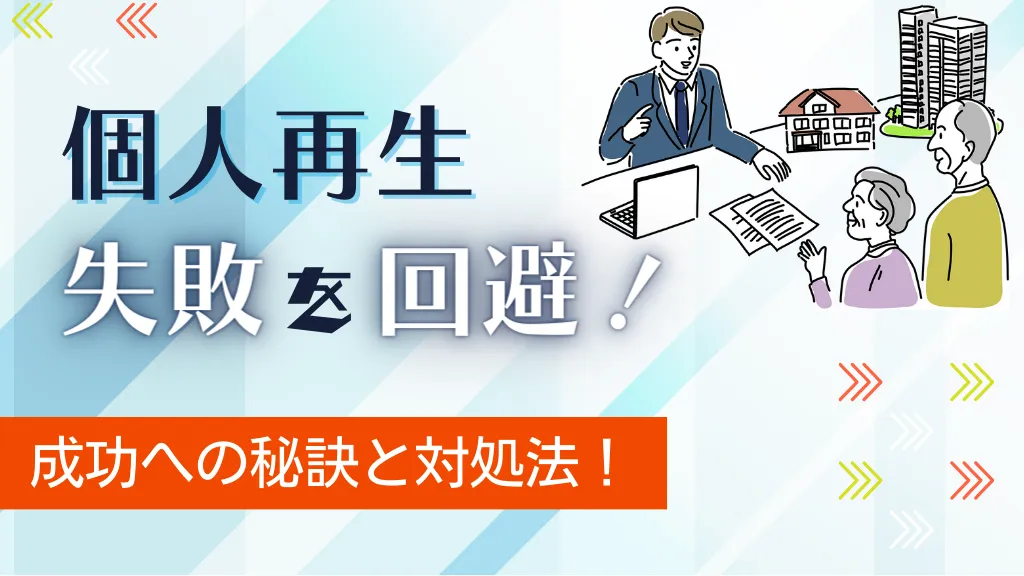
個人再生で失敗した体験談と確実に成功するためのコツを紹介!
借金問題に悩んでいる皆さん、個人再生で失敗せず、前向きに解決する方法を知りたくあ...
支払いが困難になった時の2大リスクと対処法
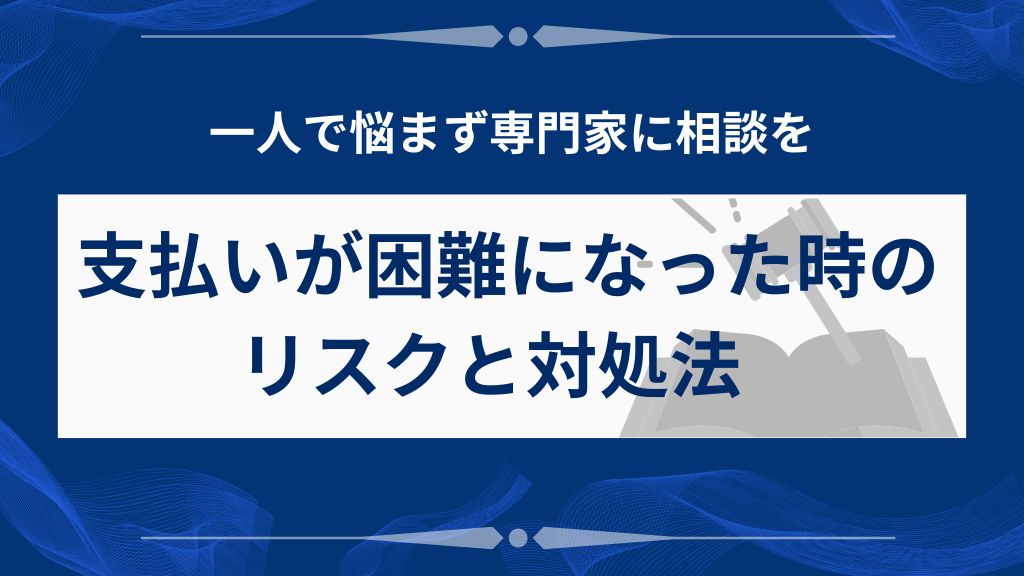
個人再生は、計画通りに返済を継続することで借金問題を解決できる有効な手段ですが、予期せぬ事態によって支払いが困難になる可能性もゼロではありません。そのような状況に陥った場合のリスクと、適切な対処法を事前に理解しておくことが重要です。
個人再生取消で元の債務が復活する仕組み
再生計画に沿った返済を怠ると、裁判所が再生計画を取り消す可能性があります。その場合、減額された借金は元の金額に戻ってしまいます。
たとえば、800万円の借金が個人再生で160万円に減額されていても、計画が取り消されれば再び800万円の債務が復活します。さらに、遅延損害金が加算されることで借金は債務はさらに膨らむ恐れもあります。
このような事態は債務者にとって、もっとも避けたいリスクの一つです。返済が困難なときは、滞納する前に早めに専門家へ相談しましょう。
債権者による給料差押えなど強制執行の可能性
再生計画が取り消されると、債権者は元の借金全額を請求できる権利を取り戻します。その結果、給料や預貯金の差押えといった強制執行手続きが開始される可能性が高まります。
強制執行が実行されると、次のような事態になることが考えられます。
- 生活費の確保が難しくなる
- 職場に差押えが通知され、知られてしまう可能性がある
- 社会生活や信用に深刻な影響が出る
払えなくなった場合の対処法
返済が難しくなった場合でも、状況に応じて再生計画を維持するための救済措置が用意されています。一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが重要です。早期に対応すれば、計画の見直しや支払猶予など、柔軟な対応が取れる可能性もあります。
返済期間を5年に延長する救済方法
返済が困難になった場合でも、やむを得ない事情がある場合には返済期間を最長5年までのばすことができます。これは、もっともよく使われる救済策の一つです。たとえば以下のようなケースが該当します。
- 病気や失業により収入が減少した
- 家族の医療費や介護費などの負担が増えた
これらの事情をもとに裁判所に申し立てを行い、必要な証拠(診断書や家計収支表など)を提出することで、延長が認められることがあります。
再生計画の変更とハードシップ免責による解決方法
返済が難しくなった場合でも、状況に応じて裁判所に申し立てることで、次のような対応が可能です。
| 再生計画の変更 | 一時的な収入減など、将来的に返済の見込みがある場合には、再生計画の内容を見直すことで対応できることがあります。例えば「返済額はそのままで返済期間を延長する」「一時的な支払い猶予を認めてもらう」などがあります。 |
| ハードシップ免責 | すでに返済の大部分(おおむね4分の3以上)を終えており、その後の返済がどうしても困難になった場合、残りの債務を免除してもらえる制度です。ただし適用要件は厳しく、認められるケースは限られているので最終手段として検討されます。 |
これらの手続きは、いずれも裁判所への申し立てが必要であり、法的な知識と経験が不可欠です。早めに弁護士に相談し、適切な対応を検討しましょう。
支払いが困難になったら一人で悩まず専門家に相談を
返済が滞り始めたり、滞納しそうになったりしたときはすぐに弁護士に相談することが非常に重要です。放置すると状況が悪化し、選べる選択肢が限られてしまいます。
法的手続きには期限があるため適切な対応が重要
再生計画の変更や返済期間の延長、ハードシップ免責などの救済措置には、申立て期限や要件が厳しく定められています。対応が遅れると、再生計画が取り消され、借金が元に戻るリスクもあります。
専門家に相談すれば、必要な手続きをタイミングよく進めることが可能です。
早めの相談で解決の選択肢を広げる方法
弁護士は、あなたの収入・支出・資産状況を丁寧に確認し、以下のような点を一緒に検討してくれます。早めに動くことで、利用できる制度も広がり、精神的な負担も軽減されます。
- 再生計画の変更・延長が可能か
- 他の手段(自己破産など)も含めたベストな方法は何か
- 今後どのように家計を立て直していくべきか
多くの法律事務所では初回相談が無料です。まずは一度、ご自身の状況を話してみることから始めましょう。
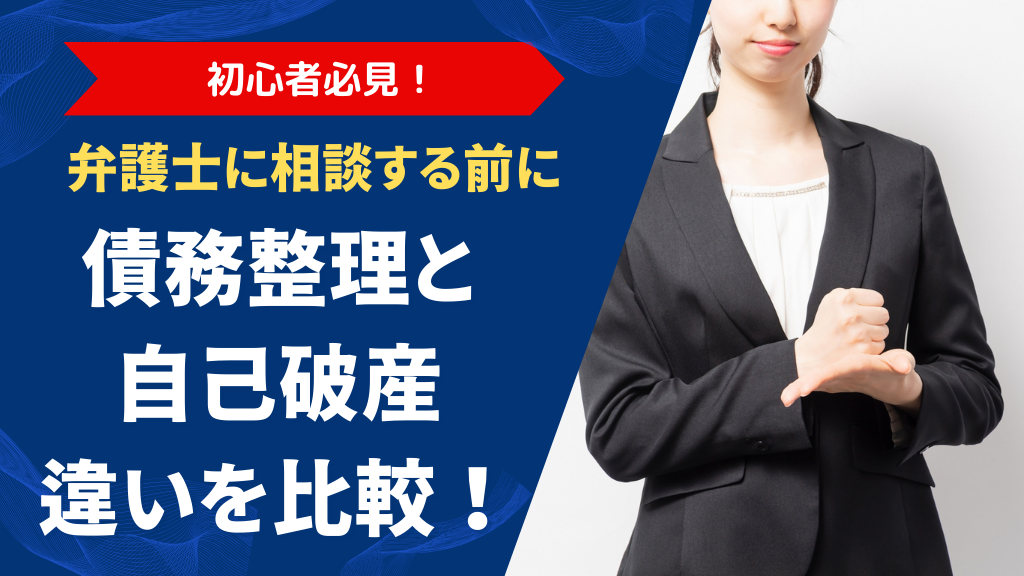
債務整理と自己破産の違いを比較!弁護士相談前に知るべきポイント
借金の返済が難しくなると、毎月の支払いが大きな負担となり精神的にも追いつめられる...
まとめ|最低弁済額を理解して賢く債務整理を進めよう
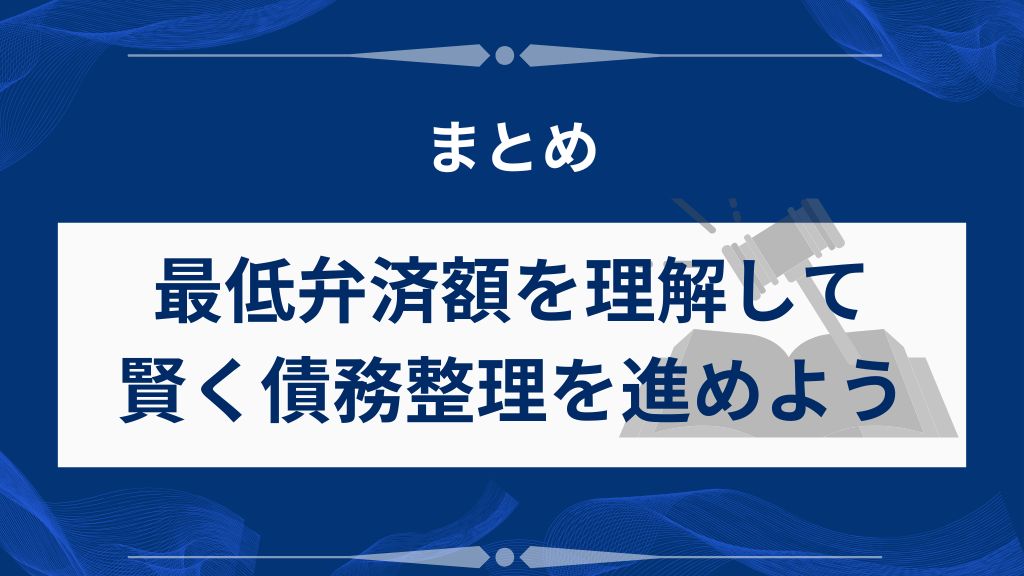
最低弁済額は、個人再生で返済額を決める重要な基準です。これには以下の3つの基準があり、その中でもっとも高い金額が採用されます。
- 借金総額
- 財産(不動産・預貯金・保険など)
- 収入(可処分所得基準)
もし、この仕組みを理解しないまま進めると「思ったより返済額が重い」「資産を失って生活が不安定になる」などの後悔につながるおそれがあります。 とくに住宅ローン特則を使いたい場合や、退職金・保険の解約返戻金など資産がある場合は、事前のシミュレーションが不可欠です。
逆に最低弁済額を抑えられれば、毎月の返済負担を軽くしながら、3年~5年の期間で債務を整理できます。督促や取立てから解放され、生活を立て直すことも可能です。
ただし、最低弁済額の計算や手続きは複雑で、書類不備や計算ミスがあると認可されないリスクもあります。 そのため債務整理に詳しい弁護士に相談し、あなたにとって最適な返済計画を一緒に作成することが非常に重要です。
多くの事務所では初回相談を無料で行っており、秘密も守られます。ひとりで悩まず、まずは専門家の意見を聞くところから始めましょう。
この記事の監修者
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。 当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
この記事に関係するよくある質問
- 個人再生の最低弁済額はいくらですか?
- 個人再生を検討されている方にとって、返済額の目安となる「最低弁済額」は気になるポイントではないでしょうか。 個人再生における最低弁済額は原則100万円と定められていますが、実際の返済額はこれに加え、お持ちの財産価値や可処分所得(返済に充てられる収入)などを考慮して決定されます。 具体的な金額はケースによって異なるため、早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
- 個人再生で一度も返済していない場合はどうなりますか?
- 個人再生の手続開始後に一度も返済が行われていない場合、債権者から異議が出され、再生計画が裁判所に認可されないおそれがあります。 特に「小規模個人再生」では、債権者の過半数の同意が必要となるため、未返済の債権者が多いと不認可となるリスクが高まります。 このような場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、再生計画の変更(リスケジュール)やハードシップ免責の申立て、あるいは自己破産への切り替えなど、適切な対応を検討することが重要です。
- 個人再生の費用を支払えなくなった場合はどうすればよいですか?
- 個人再生にかかる費用を支払えなくなった場合は、放置せずにすぐ専門家へ相談することが大切です。 弁護士や司法書士と相談のうえ、分割払いや後払いの交渉が可能なケースもあります。 また、経済的に余裕がない方は、法テラスの民事法律扶助制度を利用して費用を立て替えてもらうこともできます。 費用の滞納を放置すると、専門家の辞任や債権者からの督促再開につながるおそれがあるため、早めの対応を心がけましょう。
- 個人再生の弁済はいつ終わりますか?
- 個人再生の返済がすべて完了すると、原則として追加の手続きは不要です。 ただし、裁判所から「完済証明書」などが自動的に発行されるわけではありません。 また、返済を終えても一定期間は信用情報機関に事故情報が登録されたままとなるため、クレジットカードやローンの利用が制限される場合があります。 もっとも、この情報は永続的なものではなく、完済後おおむね5〜10年で回復する可能性があります。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。