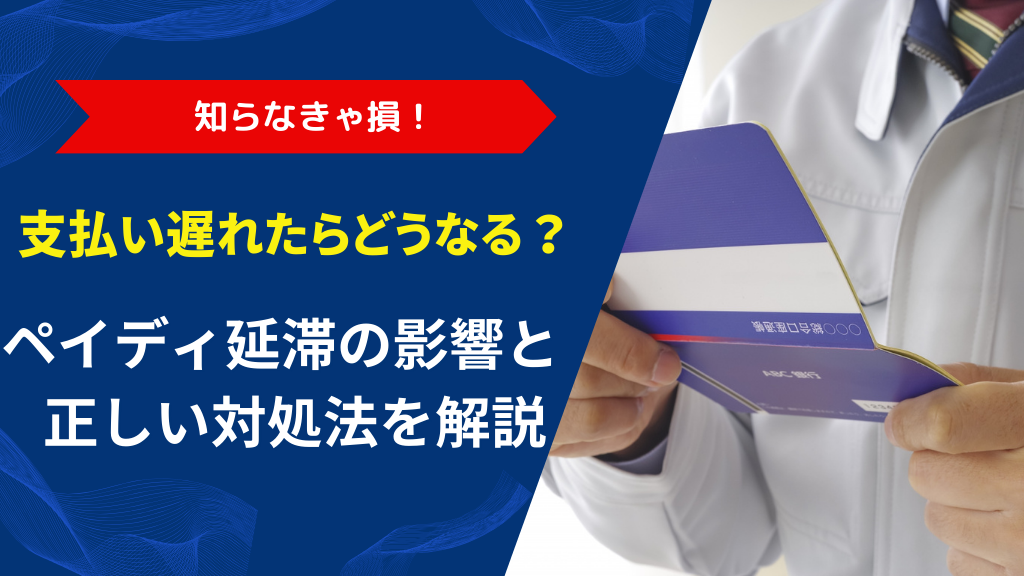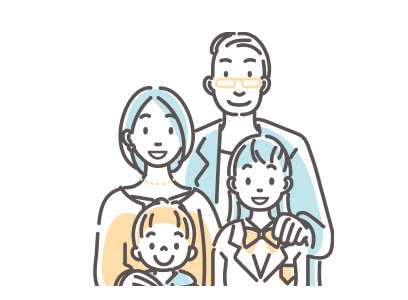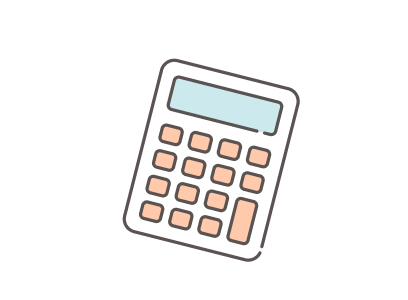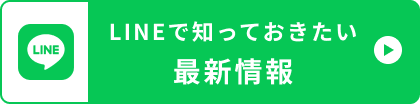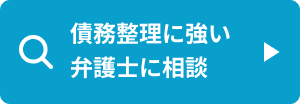生活保護受給者必見!自己破産するのに必要な費用やデメリットなどを解説
自己破産
2024.03.20 ー 2025.12.10 更新
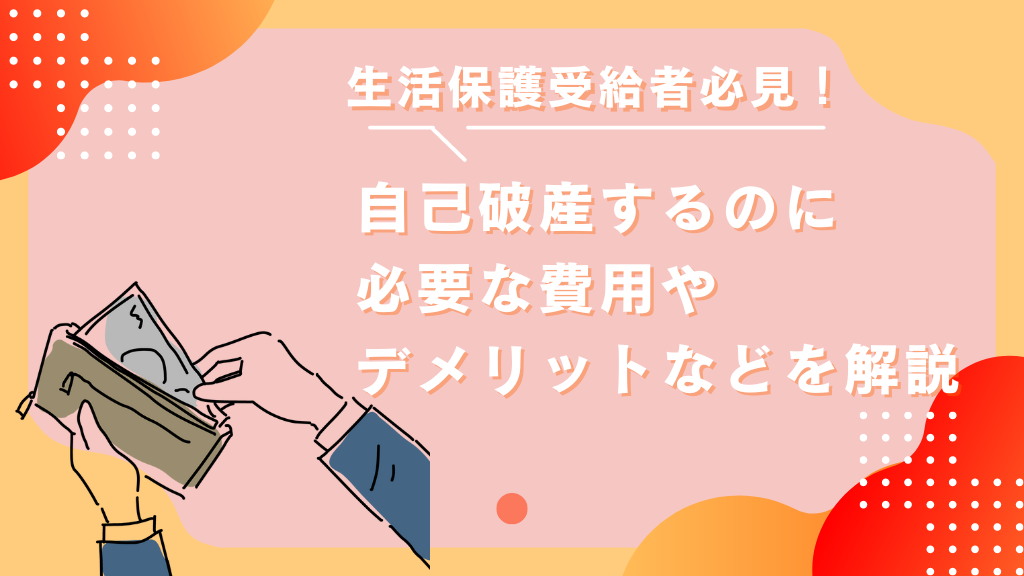
借金に悩み、自己破産を考えている方やすでに手続を終えた方の中には、「生活保護は受けられるの?」「支給額に影響はある?」と不安に思う方も多いはずです。この記事では、自己破産と生活保護の関係や、申請時の注意点、受給後の支援制度まで、わかりやすく解説します。再スタートを切るために必要な知識を知り、不安を少しでも軽くしましょう。
こんな人におすすめの記事です。
- 自己破産を検討中または手続き中で、生活保護の利用可否に不安を感じている方
- 借金問題を抱えながら、今後の生活再建に向けて具体的な支援制度を知りたい方
- 自己破産後の生活費や住居、就労支援などについて、実際に使える制度を知って前向きに対処したい方
記事をナナメ読み
- 自己破産をしても生活保護の申請・受給は可能であり、法的に制限されることはない
- 生活保護以外にも就労支援や貸付制度など再建を支える公的支援が複数ある
- 不安や誤解を避けるためにも、早めに専門機関や窓口に相談して正確な情報を得ることが大切
自己破産者も生活保護を受けられる? 受給の可否と支給額への影響

自己破産をしても生活保護を受けることは可能です。この二つの制度はそれぞれ異なる目的を持っており、一方が他方の受給を妨げることはありません。自己破産は借金を整理する手続きであり、生活保護は生活困窮者を支援する制度です。したがって、自己破産後も生活が困窮している場合、生活保護の申請は妥当です。
ただし、自己破産が生活保護の支給額に直接影響を及ぼすことは通常ありませんが、個別の事情により異なるケースも考えられます。このため、申請前には詳細な相談を行うことが重要です。生活保護の審査においては、収入や資産の状況が考慮されるため、自己破産によって資産が大幅に減少している場合でも、受給資格の確認は慎重に行われます。各自治体の担当部署や専門家に相談し、必要な手続きを適切に進めることで、生活保護を通じた支援を受けることが可能です。
生活保護とは? 基本的な制度の仕組み
生活保護は、最低限度の生活を保障するための制度であり、経済的に困窮している人々を支援することを目的としています。この制度は、法律に基づき自治体が担当し、その可否は申請者の収入や資産状況、家族構成などを考慮したうえで決定されます。申請が通ると、必要な生活費、医療費、教育費などが支給されますが、具体的な金額は各家庭の状況に応じて異なります。
生活保護を受けるにあたっては、個人の自助努力や親族の扶養が優先されるため、これらの支援が不可能な場合に限り制度が適用されることになります。また、生活保護の受給中は定期的な報告義務があり、収入や資産に変更があった際には速やかに自治体に報告する必要があります。このようにして、生活保護制度は社会のセーフティネットとして機能し、困窮した人々の生活を支えています。
自己破産しても生活保護の受給は可能?
自己破産をしたからといって生活保護の受給が不可能になるわけではありません。法律の観点から見ても、自己破産と生活保護は独立した制度であるため、自己破産が理由で生活保護申請が拒否されることはないのです。自己破産は個人の負債を法的に整理する手続きであり、一方で生活保護は、最低限の生活を支えるための社会保障制度です。そのため、自己破産によって経済的に困窮した際には、生活保護の受給が可能となるケースが多いのです。
ただし、生活保護の申請には資産状況や収入に関する詳細な審査が行われます。そのため、自己破産したからといって自動的に生活保護が受給されるわけではなく、個別の審査に合格する必要があります。このような背景から、自己破産後の生活保護受給は法律上は可能ですが、実際の受給に至るまでには慎重な手続きと準備が必要です。場合によっては、各自治体の福祉事務所に相談し、適切な助言を受けることも求められるでしょう。
自己破産が支給額や受給頻度に及ぼす影響
自己破産は、個人の財産を整理する法的手続きであり、これにより債務の免除を受けることができます。一方で、生活保護は最低限の生活を支えるための公的な支援です。自己破産が生活保護の支給額や受給頻度に及ぼす影響は、直接的なものは少ないですが、間接的には影響を及ぼすことがあります。具体的には、自己破産によって得られる生活再建のための資産状況が変わることで、生活保護の必要性が判断される場合があります。
自己破産後は、資産がほぼゼロになることが一般的で、これにより生活保護の受給に必要な条件を満たしやすくなります。しかし、自己破産の手続き中や直後は、経済的な不安定さが増すことから、生活保護受給の申請が増加する傾向もあります。ただし、自己破産をしたことで他の収入源が減少するケースがあるため、個々の状況によっては支給額に影響を及ぼすことが考えられます。このように、自己破産のプロセスは複雑であり、生活保護との関連性も多面的であるため、具体的な状況に応じた相談を行うことが重要です。
自己破産後に生活保護を申請する方法と受給条件のポイント

自己破産を経た後でも生活保護を申請することは可能であり、適切な手続きと受給条件を満たすことが重要です。その申請方法については、まず市区町村の福祉事務所に相談し、生活保護の必要性を具体的に伝えることが求められます。申請には、収入や資産状況を証明するための書類が必要で、自己破産の手続きが完了していることも確認されます。さらに、受給条件としては、持ち家や高額な資産がないこと、就労が困難な状況であることなどが考慮されます。
ただし、地域や個別のケースにより条件や手続きが異なる場合があるため、担当者と十分な相談を行うことが欠かせません。生活保護の受給は、経済的な再建を目的とするため、無理のない範囲での復帰計画を立てることが求められます。
自己破産後の生活保護受給の流れと条件
自己破産後に生活保護を受給するためには、適切な手続きを理解しておくことが重要です。まず、自己破産は経済的再生を目的としており、この手続きが生活保護の申請を妨げることはありません。むしろ、自己破産により負債が整理されることで、生活保護の基準を満たしやすくなるケースもあります。生活保護を申請する際には、本人の資産や収入を詳細に把握する必要があり、これに基づいて生活保護の可否が判断されます。
申請者は、各自治体の福祉事務所へ出向き、自身の状況を正確に伝えることが求められます。ここで注意したいのは、自己破産後の生活費や住居費など、必要不可欠な支出を考慮した上で申請書を作成することです。福祉事務所では、ケースワーカーが丁寧にサポートしてくれるため、不明点があれば相談を重ねることが推奨されます。
条件としては、収入が最低生活費を下回ることや資産が規定額以下であることなどが挙げられます。住民票や所得証明書、医療費など生活状況を証明する書類も用意が必要です。また、ケースワーカーは生活の安定を目指し、継続的な支援を行ってくれますので、正直な情報提供を心がけることが重要です。
申請時に必要な書類と手続きのポイント
自己破産後に生活保護を申請する際には、具体的な書類と手続きが必要です。まず、必要書類としては、住民票、所得証明書、資産に関する書類(例えば預金通帳のコピーや土地、建物の登記簿など)が挙げられます。また、自己破産に関する裁判所の判決書や、債権者一覧表も用意しておくとスムーズです。手続きのポイントとして、自身の収支状況を正確に把握することが重要であり、ケースワーカーとの面談では、誠実かつ正確な情報提供が求められます。
特に、自己破産の手続きが完了している場合、それに関する経緯や現状を詳しく説明することが、生活保護受給の審査において有利に働くことがあります。しかしながら、地域によっては要求される書類に多少の違いがあるため、事前に自治体の窓口で最新情報を確認することが肝要です。これにより、手続きの不備を未然に防ぎ、スムーズな受給開始を目指せるでしょう。
生活保護受給者が自己破産する際の必要書類と費用免除の可能性

生活保護受給者が自己破産手続きを行う際には、いくつかの必要書類が求められます。大きく分けると、収入や資産を証明する書類、そして生活保護受給の証明書などが挙げられます。費用に関しては、法テラスを活用することで、一定の収入要件を満たす場合には負担を軽減または免除される可能性があります。しかし、必ずしも全てのケースで費用が免除されるわけではないため、事前に十分な確認が必要です。
また、自己破産手続きの進行にあたっては、生活保護受給に影響を及ぼさないよう、慎重に計画を立てることが求められます。具体的な必要書類や手続きについては、専門の法律相談窓口での助言を仰ぐことが推奨されます。法テラスの利用やケースワーカーとの相談は、手続きの効率化に役立つでしょう。
自己破産の手続きに必要な書類一覧
自己破産の手続きを行う際には、必要書類をしっかりと揃えることが不可欠です。まず最初に求められるのが、破産申立書です。これには、破産を申立てる理由や債権者の一覧、資産の現状などを詳細に記載します。次に、給与明細や預金通帳の写しが必要です。これらは、収入や資産の状況を正確に把握するためのものであり、収入が少なければそれを証明する資料としても利用されます。
また、過去に借金の取引があったことを示す契約書類や請求書も準備が必要です。これらにより、債務額や取引履歴を明確にすることが可能です。さらに、住民票や身分証明書も必要となりますが、これらは本人確認を行うためのものであり、間違いや不備がないよう最新の情報を用意します。これら書類は、多岐にわたる情報を求められるため、準備には十分な時間と注意が求められます。そのため、事前に必要書類を整理し、弁護士や司法書士に相談しながら進めることが安心です。
生活保護受給者は自己破産の費用が免除される?
生活保護受給者が自己破産を検討する際、通常問題となるのが費用の負担です。自己破産の手続きには裁判所への申し立て費用や弁護士費用がかかりますが、生活保護受給者の場合、これらの費用が免除または軽減される可能性があります。まず、法テラスの支援を受けることで、弁護士費用や申し立て費用が無料または分割払いになるケースが多いです。法テラスは経済的に厳しい状況にある人を対象にした支援制度で、生活保護受給者もその対象となります。
この制度を利用することで、生活保護受給者でも自己破産を進める際の金銭的負担を軽減することができます。ただし、具体的な免除内容や条件については、個別の事情により異なるため、詳細は法テラスや担当弁護士に確認することが重要です。この支援が受けられるかどうかは、暮らしに直接関わる重要な問題であるため、慎重な確認が求められます。
法テラスを活用する方法
法テラスは、自己破産を考えている方が抱える法的問題を相談する際に非常に有用な機関です。まず、法テラスは適切な法的アドバイスを提供することで、自己破産の手続きに関する不安を軽減します。相談は無料で行える場合が多く、経済的に困窮している方でも利用しやすいのが特徴です。加えて、法テラスでは弁護士や司法書士とのつながりを持ち、自己破産手続きのサポートを受けることが可能です。
さらに、収入や資産状況によっては弁護士費用の立て替え制度も利用できるため、自己破産に伴う費用の負担を軽減することができます。ただし、法テラスを利用するためには一定の条件や手続きがあり、その点は事前に確認しておく必要があります。これにより、自己破産手続きがスムーズに進む可能性が高まります。法テラスの活用は自己破産の第一歩を踏み出す際の重要なサポートとなるでしょう。
自己破産と生活保護、どっちを先にすべき? メリット・デメリットで比較

自己破産と生活保護を選ぶ順番には、それぞれのメリットとデメリットがあります。まず自己破産を先に行うと、抱えている借金を法的に整理でき、生活基盤を整えるための新たなスタートを切りやすくなります。しかし、手続きには時間がかかり、短期的には経済的な不安定さが続く可能性があります。一方、生活保護を先に受給する選択には、迅速に生活の基礎を確保し、最低限の生活を維持する助けになります。
ただし、生活保護を先にしてから自己破産を行う場合、特定のケースでは受給額や手続きの複雑さが増す可能性もあります。どちらを選択するかは個々の事情によりますが、福祉の相談窓口でのアドバイスが役立つでしょう。最終的には、生活の安定を最優先に考え、時には専門家の助言を受け入れることも重要です。
自己破産を先にするメリット・デメリット
自己破産を先に行うことには、いくつかのメリットとデメリットがあります。メリットとしては、借金の免除によって経済的負担が大幅に軽減される点が挙げられます。これにより、精神的な安定を取り戻しやすく、再出発の一歩を踏み出しやすくなります。また、裁判所による免責決定を受けることで、法的保護を得られるのも大きな利点です。
しかし、デメリットも存在します。自己破産の手続き中や直後には一定の制約が課され、信用情報にも長期間記録が残るため、将来の金融活動には注意が必要です。さらに、生活保護の申請を意図する場合、自己破産を先に行うことで申告内容が変わり、役所の審査が厳しくなることも考えられます。これにより、手続きの複雑さが増し、結果的に受給条件が不利になる可能性もあるため、細心の注意が求められます。
生活保護の受給を先にするメリット・デメリット
生活保護を先に受給することのメリットは、自己破産の手続き前に生活の基盤を確保できる点にあります。生活保護を受けることで、最低限の生活費が支給され、破産手続きによる生活の混乱を少しでも軽減できる可能性があります。ただしデメリットとして、生活保護の受給が始まった後に自己破産を行うと、手続きの際に役所との調整が必要となることがあります。
また、自己破産後に生活保護を受けた場合、破産の影響で将来の生活設計に不安が残ることがあります。支給額に明確な影響は提示されていませんが、地域や担当者による微妙な調整が行われることもあり、最終的には個別の状況に依存するため、一概に判断しづらい面もあります。生活保護と自己破産を組み合わせる際、どちらを優先すべきかは、本人の生活状況や将来の計画によって異なるため、十分な検討が必要です。
どちらを選ぶべきか? 判断のポイント
自己破産と生活保護の選択においては、個々の状況を慎重に評価することが重要です。自己破産は多額の借金を整理する法律手続きであり、一方で生活保護は生活が困窮している人々に対する最低限の生活支援を提供する制度といえます。この2つの手段をどちらも利用することは可能ですが、どちらを優先するかは経済状況や今後の生活見通しによって異なります。
自己破産を優先すべき場合は、特に借金が生活を圧迫している場合が考えられます。これに対し、生活保護を先に検討するのは、急ぎ生活の基盤を整える必要がある場合です。加えて、自己破産手続きは一時的に生活が不安定になることがあるため、可能であれば生活保護の申請も早めに準備しておくことが望ましいとされます。
ただし、自己破産が生活保護の受給に影響を及ぼすわけではなく、自治体によって解釈や対応が異なる場合もあるため、担当のケースワーカーに相談しつつ判断するのも一法かもしれません。以上のように、両制度の特徴を理解し、自身の状況に最も適した選択を行うことが求められます。
ケースワーカーに自己破産を相談する際の注意点と伝え方

ケースワーカーに自己破産について相談する際には、タイミングとコミュニケーションの工夫が重要です。まず、自己破産の意向を早めに伝えることで、支援を受ける準備を整えやすくなります。しかし、説明の際には簡潔かつ正確な情報提供を心がけることが求められます。具体的な事情や理由を整理し、相談内容を明確にすることで、ケースワーカーとの円滑な意思疎通が図れます。
また、自らの状況や生活保護を受ける理由を伝える際には、個人の事情に沿った具体的な説明を心がけることが大切です。共感を得つつ、相手に誤解を与えないように細心の注意を払いましょう。このように、ケースワーカーとのコミュニケーションは慎重に進めるべきです。最良の結果を得るためには、具体的な相談内容と自分の状況をしっかり把握し、臨機応変に対応することが求められます。
ケースワーカーに自己破産を伝えるべき理由
ケースワーカーには自己破産の事実を伝えることが重要です。まず、自己破産は生活保護の申請や受給に直接的な影響を与えないものの、申請者の状況を正確に把握するためには欠かせない情報であるからです。ケースワーカーは申請者の経済的背景を考慮し、最適な支援策を提案する役割を担っています。自己破産を伝えることで、追加の支援が必要かどうかの判断がなされます。
さらに、自己破産によって生活保護の受給額が変わることはありませんが、家計の状況や今後の収支見通しを正確に把握するには避けて通れない情報です。伝達を怠ることで申請者自身に不利益が生じる可能性があるため、誤解を避けるためにも積極的に伝えることが求められます。場合によっては、自己破産による精神的負担を理解された上で適切な生活保護支援が受けられるかもしれません。
相談時に注意すべきポイント
自己破産者が生活保護の相談を行う際は、いくつかの注意すべきポイントがあります。初めに、自分の収入や資産状況を正確に把握することが大切です。それに基づいて、生活保護を受ける必要があることを具体的に説明できる準備をしておきましょう。また、自己破産の手続きが進行中である場合、その状況も詳細に伝えることが求められます。特に、破産手続きの進捗や、予想される生活の難しさについて話すことが重要です。
ケースワーカーには、破産による経済的困窮の具体的な影響を理解してもらうため、実体験に基づいた説明を行うと効果的です。さらに、相談においては、感情に流されず冷静な態度を心がけることが信頼関係の構築に繋がります。時には、誤解が生じる場合もあるため、不明点があればその場で確認する姿勢が必要です。問題解決に向けて、双方の協力が欠かせないため、オープンなコミュニケーションを意識しましょう。
トラブルを避けるための上手な伝え方
自己破産を経験した方が生活保護を申請する際、トラブルを避けるためには、自身の状況を適切に伝えることが重要です。まず、正直かつ誠実に自己破産の経緯を説明し、生活保護の必要性を明確にしましょう。ケースワーカーに対しては、自己破産によって日常の経済状態がどのように変化したかを具体的に伝えることが大切です。財産の状況や収入の減少など、具体的な事実に基づいた情報提供は、理解を助けます。
ただし、自己破産と生活保護の制度そのものに対する誤解を防ぐため、法的な側面を含めた詳細な説明にも気を配るべきです。口調は冷静かつ丁寧に保ち、不安や焦りを過度に表現しないように心掛けます。これらの工夫によって、円滑な申請手続きが進むケースが多く見られますが、状況に応じて予期せぬ問題が発生することもあるため、日頃から情報を整理しておくと良いでしょう。
自己破産後の生活保護以外の再建支援制度とは

自己破産をした後でも、生活保護以外に利用できる再建支援制度は複数あります。これらの制度を正しく理解し活用すれば、無理のない形で生活を立て直すことが可能です。返済や滞納に追われていた日々から抜け出し、安定した暮らしを続けるためには、個人再生や任意整理といった債務整理以外の選択肢も視野に入れることが大切です。手続や提出書類には注意点も多く、同時に複数の制度を利用する場合は管轄する機関や業務の重複にも配慮が必要です。申請を進める際は、破産管財人や福祉窓口と連携し、基本的な流れを理解した上で取り組むことが成功への鍵となります。
就労支援や職業訓練による自立支援
生活保護費に頼らず再出発を目指す人にとって、就労支援や職業訓練は大きな助けになります。自治体やハローワークでは、無料で参加できる就労支援プログラムや職業訓練校が用意されており、世帯の収入状況や支払い能力に応じた内容が提供されます。参加には申し立てる必要がある場合もあり、日程や受付方法を事前に確認しておくのがポイントです。
訓練中は一定の手当が支払われる制度もあり、お金の不安を抱えながらもスキルを身につけることができます。職業訓練は税金によって支えられている公共サービスであるため、不正受給がないよう注意しながら、正規の手続を踏んで利用することが求められます。滞納や過払い金返還請求に追われていた人にとっては、新たな収入源を得るチャンスでもあります。
住居確保給付金による家賃支援制度
住居確保給付金は、住宅ローンの返済が困難になった人や家賃の支払が難しい人を対象とした支援制度です。原則として一定の収入以下であり、就労意欲があることが条件ですが、生活保護費を受ける前段階の援助として活用されることもあります。この制度では、家賃を直接大家に支払う形で給付が行われ、滞納や督促を未然に防ぐ効果も期待できます。
申請時には住民票や世帯の収支証明等を提出し、支給が認められた場合には最長9ヶ月程度の支援が可能です。申し立てる際には、対象条件や支援額などの詳細を自治体に問合せて確認することが大切です。支援は猶予的な性格を持つため、支給期間終了後に自立できる見込みが必要です。
自治体による家計改善支援・相談窓口
多くの自治体では、家計が破綻した世帯や、返済・支払が困難になった人々を対象に、家計改善支援を行っています。家計の収支状況を専門の相談員とともに見直し、今後の支払計画を立て直すためのアドバイスが受けられます。自己破産後の支援としても利用可能であり、任意整理や個人再生など債務整理の種類にかかわらず相談することができます。
税金の滞納やクレジットカードの使い過ぎなど、日常の金銭管理に関する問題点も指摘されるため、自分では気付かなかったリスクに気づくこともあります。相談は予約制の場合が多く、利用者数に応じて受付時間が限られていることもあるため、事前の問合せが欠かせません。無料で利用できるところが多く、生活保護費に頼る以外の解決策として注目されています。
社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、自治体や社会福祉協議会が実施している公的貸付制度で、急な支払いや予納金の確保などに活用されます。返済義務はあるものの、無利子または低利子での貸付が基本であり、生活保護を受けていないが困窮している人にとって心強い支援となります。この制度には種類がいくつかあり、世帯の状況や申請目的によって利用できる内容が異なります。
貸付には原則として償還計画の提出が必要で、支払能力が認められるかどうかも審査されます。申し立てや提出書類には細かい指定があるため、事前に機関へ問合せし、必要な情報を整理してから申し込みましょう。万が一返済が滞ると、再申請や追加支援が難しくなるため、返済計画は慎重に立てる必要があります。
地域NPO・支援団体による再出発サポート
地域のNPOや民間支援団体も、自己破産後の再出発を支える大切な存在です。お金の問題に関する無料相談、就労支援、住まいの確保など、行政とは違った柔軟な援助が受けられることが特徴です。生活保護の手続が難しい場合や、支給の打ち切られた後の対処法としても有効です。中にはクレジットカードの利用トラブルや過払い金返還など、債務整理に関係する業務に詳しい団体もあり、幅広い問題に対応しています。
こうした団体の利用は予約が必要なことも多く、支援の内容や対象範囲もそれぞれ異なるため、事前の確認が重要です。何から始めればよいかわからないときこそ、身近なNPOや団体に問合せをすることで、新たな一歩を踏み出す手がかりが得られます。
まとめ:自己破産後も利用できる生活保護と支援制度のポイント

自己破産をした後でも、生活保護や各種支援制度を活用すれば再出発は可能です。借金問題を解決したいなら、まずは自分に合った制度を選び、正しい手続を進めることが重要です。たとえば生活保護を申請する際も、管財事件でないか、他の収入があるかなど、基本的な確認事項があります。必要書類を提出するタイミングや、支給の許可がいつ出るのかも事前にわかると安心です。
取り立てが止まらない、請求が続いているという人は、債務整理と同時に支援制度の利用も視野に入れましょう。現在、生活に困っている方でも、時効の援用や支払い減額など、法的手段で解決できるケースは少なくありません。相談は気軽に行えますし、内容がバレる心配も基本的にありません。専門家への依頼が不安な方も、概要だけでも知っておくと、結論を出す際の判断材料になります。
この記事の監修者
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。 当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
この記事に関係するよくある質問
- 生活保護を受けた場合、それまでの借金はどうなりますか?
- 生活保護をもらっても、借金の状況は変わりません。借金があっても生活保護の受け取りは可能ですが、受け取った生活保護費を借金の返済に使うことはできません。この点に関しては後ほど詳しく説明しますが、生活保護費を借金返済に充てると、不利益を受けることになります。
- 生活保護を受けている間に新たに借金をすると、その事実は分かるのでしょうか?
- 生活保護受給者の金融取引については、福祉事務所が銀行口座の出入金をチェックできる権限を持っています(生活保護法第29条第1項に基づく)。これにより、新しい借金がある場合は速やかに発覚します。また、ケースワーカーが定期的に訪問して生活状況を確認するため、「生活水準が高い」と見られると、その時点で借金の存在が明らかになることもあります。
- 自己破産を進めている間の日々の生活費はどうなるのでしょうか?
- 自己破産手続きの期間中でも、仕事を続けることに制限はありません。仕事から得た収入を、生活費として使用することも問題ないです。ただし、企業や事業主自身が破産手続きを開始した場合、事業が停止し、それによって収入が途絶えてしまうことがあります。
- 生活保護を受けると、どのようなものが無償になりますか?
- 生活保護受給により、医療費や介護サービスが実質無料で提供され、保育料についても免除されます。生活保護を受けている人々は国民健康保険の対象外となるため、医療費の全てが医療扶助によってカバーされます。
- 生活保護受給中に分割払いの契約を結んだ場合、それが明らかになるでしょうか?
- 生活保護受給中に借金をしたり、ローンを組んだりすると、その情報は福祉事務所に知られることになります。福祉事務所は、銀行やクレジットカードの利用状況に関する調査を行う権限を持ち、これらの金融機関は調査要請を拒否できないからです。したがって、借入れや分割払いの利用は発覚するため、控えるべきです。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。